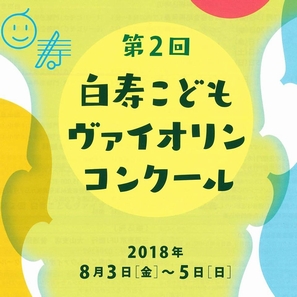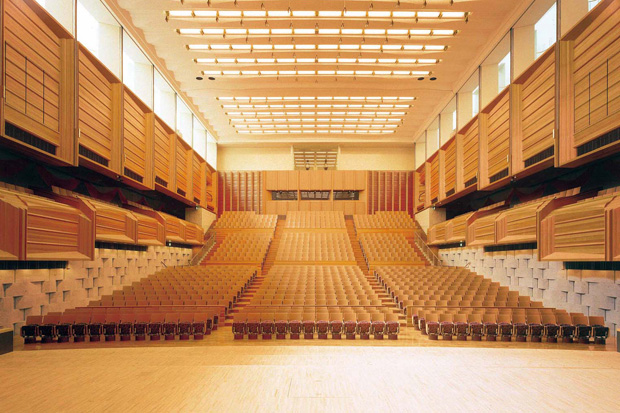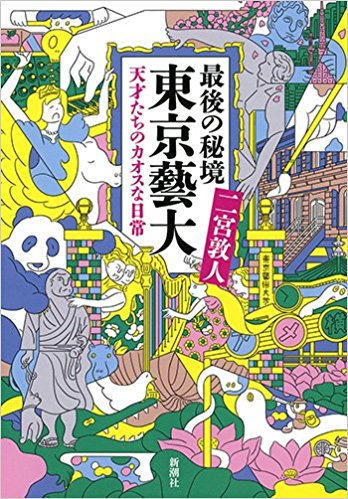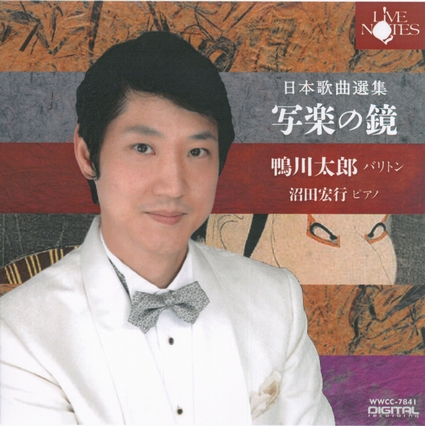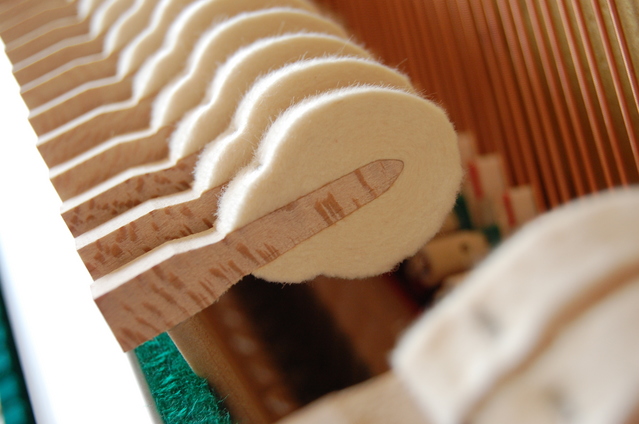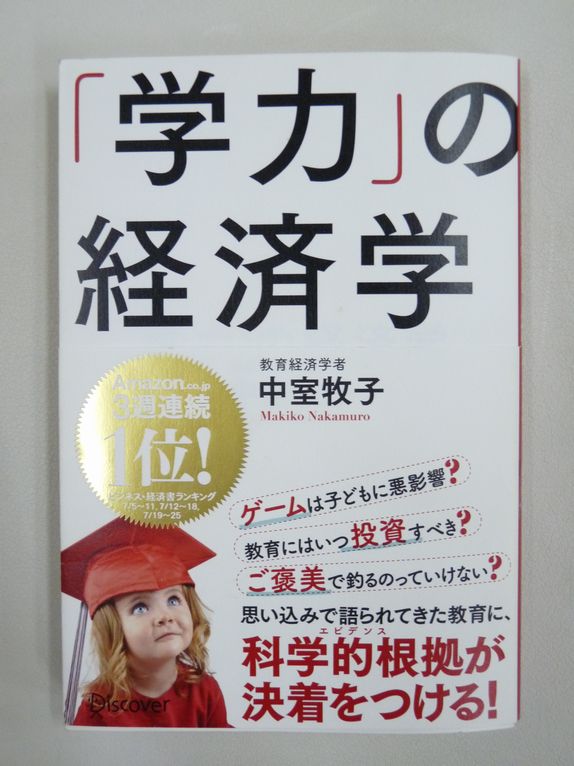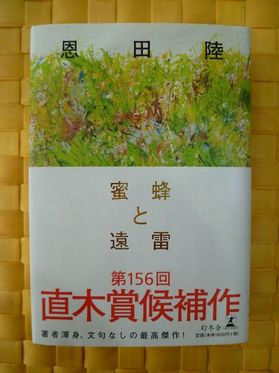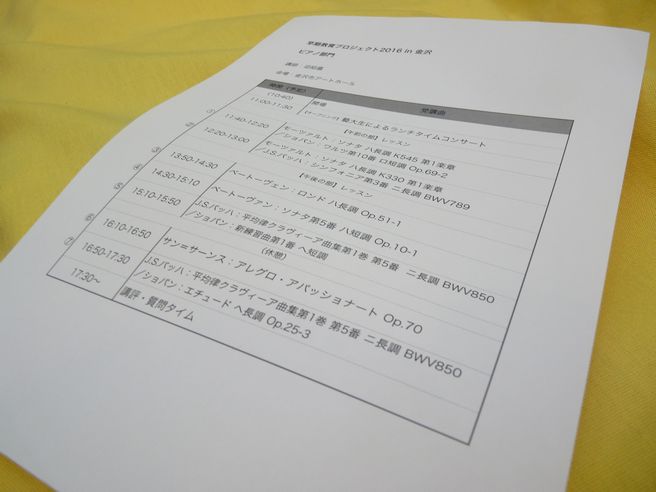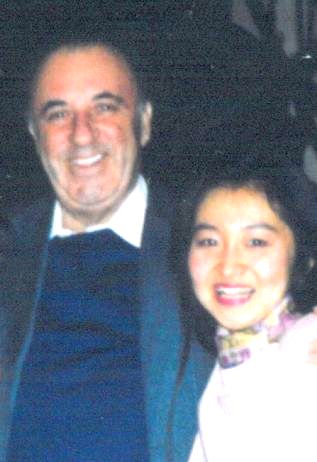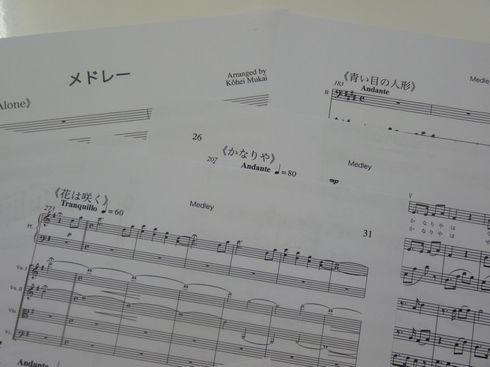�\���C���G�b�Z�C
���y�E����E�ЂƁE�H�E�{�E�E�E�����G�b�Z�C��

- 4��6���i�y�j�ŐV�E���i���!!
�@�P�X�W�R�N�J�݂̓����y�����́A���N�łR�T�N�ڂ��}���܂��B �@�g���߂���ō��̉��y���h�����b�g�[�ɏ�������̋���̑����搂��A �n���ɃR�c�R�c�ƃ��b�X���𑱂��Ă��܂����B �@�������ł́A�u�t�̗p�ɂ�����A����������������܂��B�Y���w�@�C���� �ł��邱�Ɓi�Y�呲�⎄���̉��呲�Ǝ҂́A���t�͂�w���͂ɂ����āA����� ���l������ȏ�ƔF�߂���ҁj�A�w�����邱�ƂɔM�ӂ����邱�ƁA���i�� ���邭�l�i�I�ɗD��Ă��邱�ƁA�̂R�_�ł��B �@�S���I�ɂ݂�A���̂悤�ȏ����ɊY������搶�͑�������������ł��傤 ���A���̃��x���̐搶���������Ń`�[����g�ݎw�����Ă��鉹�y�����́A�S�� �ł��܂�ł��傤�B����́A�Q�n���ݏZ�ł��A��蒼���Ȃ��ėǂ��ō����x���� ���b�X���������Ă��������Ƃ����n�Ǝ҂̎v���̌����ł��B �@�ЂƂ�̐l�Ԃ̎v�����A�F�X�ȕ��̋����Ƃ����͂āA�傫���������t�� �Ȃ�܂����B �@�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z��ⵋȂ�S�����i�����j���[�X�� �P�����Ōf�ڂ��܂������A�R���P�Q���̓����Y�p��w���i���\�ł́A�Q�������i���A ����ɕ����܂����B �@�Y��ɍ��i�����͎̂��̒ʂ�ł��B �@�s�A�m��U K�N�i�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�j �@���B�I����U A����i������{��w�����w�Z�j �@�Y�������Y��̓����̓G�X�J���[�^�[���ł͂Ȃ��A���Z�A�\���t�F�[�W���A �Z���^�[�����S�ĊO�����Ɠ��ȖځA�������ŐR������܂��B�P���A�Q�������ł� ���Z�̏o����������Ηe�͂Ȃ����Ƃ���܂����A�Z���^�[�����ł��_�����B�� �Ȃ���A�ŏI���i�Ɏc�邱�Ƃ��o���܂���B�Ƃ�����ŁAK�N���撣���Ď�� ���ꂽ���i�ł��B �@A����͏��w�R�N���̎��Ƀ��@�C�I�����̃N���X�ɓ����B�����͎�ŁA�Ƃ��� ���Ƃł������A����܂ŏK���Ă����Ȃ̂����^�|�@�𐔔N�Ԃ����Ē����܂����B �T�N���̎��ɉ��y�Ői�w���邱�Ƃ����ӁB���i��ΐ搶�̒��J�Ȏw���Ń��L���L�� �r���グ�A���@�C�I�������Y����܂��傤�A�Ɛ搶�Ɍ����Ă��������郌�x�� �܂ŏ�B���܂����B�R�O���N�L�O�R���T�[�g�̎��̎���搶�̃��B�I�������܂�A ���̉��Ɋ������ă��B�I���ɓ]�����邱�ƂɁB���Q����y������B�I���Ɏ����ւ��A �����̐搶�Ɏt�����܂����B���B�I���֕ύX���ĂP�N���A��������Ɛg�ɕt���� ���@�C�I�����ł̑t�@�ƖL���ȉ��y���A�����ĉ��F���]������A�Y�����S���̓S�ǂ� ���B�I���g��ł��j��A�����Y�升�i�Ƒ�����܂����B �i��N�S���قǂ̃��B�I���g�Ȃ̂ł����A�O�����Ƃ��č��N�͂P���A�V�䂳�� �@�����ɓ������̂ł�!! �j �@�\���t�F�[�W��������A����ł������A�Ō�̒ǂ����݂��f���炵���A�ԍۂ� �������Ԃŕʐl�̂��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂́A�܂��Ɋ�Ղł����B �@�@ �@�ۑ�Ȕ��\�̏H����n�܂�A�P�����{�̃Z���^�[�����A�����Œ��̂Q���Q�T������ �P�������E���i���\�A�Q�������E���i���\�A�R�������ƌo�āA�ŏI���\�̂R���P�Q�� �܂ŁA���͖͂ܘ_�̂��ƁA�C�͂Ƒ̗͂����Ɉێ����A���̋��Ȃ��I�[���}�C�e�B�� �d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Y��̓�������߂ĔF���������N�̎ł����B �@���͂Ƃ����ꖳ���ς�Ńz�b�Ƃ��Ă��܂��B �@�Y��Q���A�Y���P���A��������P���A���i�����F����A�{���ɂ��߂łƂ��������܂��B �@����ł悤�₭�X�^�[�g���C���ɗ����Ƃ��ł��܂����ˁB���ꂩ��̊F����̊���� �傢�Ɋ��҂��Ă��܂��B
- 12��1���i�y�j���Ȃ��҂ɐ����Ȃ�
�@�������̂łQ�O�P�W�N�����Ǝc���Ƃ���P�����A�N��������ƍ���V�c�� ���O�ވʂ���A�������ς��܂��B �@���a���܂�̎��ɂƂ��ẮA�N�����ς��̂͂Q�x�ڂ̌o���B���������� �R�O�N�o�������Ƃ��v���Ɗ��S�[�����̂�����܂��B �@�吳���܂�̐l�́A���N����ɂȂ�ꂽ�̂����ׂĂ݂�ƁA�吳�P�T�N (����P�X�Q�U�N)���܂�̐l���X�Q�A�吳�V�N(����P�X�P�W�N)���܂ꂪ �P�O�O�B�����S�T�N(����P�X�P�Q�N�A��������Ō�̔N)���܂�̐l�� �P�O�U�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�P�O�U�Έȏ�̂������҂������ÁX�Œ��� ����A���{�ɂQ�T�O�O�l������������̂������ŁA�������~�܂�܂���B ���N�T���܂Ő����Ă�����A�����A�吳�A���a�A���������ĐV�����ƁA�T�� �����ɂ܂������Đ����邱�ƂɂȂ�A�S���������Ƃł��i�g�����h�ȊO�̌��t�� ������܂���j�B �@�O���ŕ�炵�Ă���ƁA���{�̌�����S���g��Ȃ��Ȃ邽�ߌ����͂���Ȃ� �悤�ȋC�����Ă��܂����A����U�S�T�N�̑剻�̉��V�ȗ��A���X�Ƒ����Ă��� ���{�̗��j�Ƃ������錳���ł������Ɍq���ł����������̂ł��i�剻�ȑO �ɂ��������������Ƃ�������_���V�c����R�T��c�ɓV�c�܂ŁA�V�c�̖��O�� �N��\���Ă����ȂǁA�F�X�Ȑ�������܂����A������ɂ��Ă����E�Ɍւ�M�d�� ���{�̗��j��Y�ł��j�B �@�\���C���͍��N�n�݂R�T���N�A���{�̗��j�Ɣ�ׂ�Ƃق�̈�u�ł����A�T�N ���݂̋��̔N�ƂȂ�܂����B �@�\���C���J�݂ɂ�����A��b���d�������\���C���̋��炪�A�l���P�O��������Ƃ� �s�Œʗp����̂��ƍl������A�n�߂�̂��S�O�����Ƒz�����܂����A������挎���� �q�ׂ��ʂ�A�M���v���Ɛ��������ŃX�^�[�g�B����ł��R�T�N�������Ă���ꂽ�� �ł�������v�͂������̂ł��ˁB �@�\���C���̐搶�́A���t�ƂƂ��Ă̋Z�p�I�Ȋ�͖ܘ_�ł����A�����邱�Ƃ� �D���Ŗ��邢�l�A�Ƃ����̂��̗p�����ɂ���܂��B �@�\���C���̐��k����ƕی�҂̕��X���A���邭�đO�����ȕ�����B�͎̂q���� �S�R���K���Ȃ��E�E�E���A�s����Y�݂�i����������܂������A���݂͊F���� �O�����ɖ��邭�撣���Ă��������Ă��܂��B �@�ɓ������A�R���L���A�����W��ȂǁA�����ېV�̗����҂���Ă��g�c���A�́A �]�˂⋞�s���牓�����ꂽ���݂̔��s�ɁA���m�A�������m���J���A�g���̕��� �u�Ė����m��������w�����܂����B �@���A�́A�m���̗ǂ��Ƃ����I�m�Ɍ����A�����J�߂邱�Ƃ��ƂĂ���肢 ��A������L�����߂̕����Â�����肾�����Ƃ����܂��B �@���Ō����Ƃ���̃|�W�e�B�u�V���L���O�̎�����ŁA�������ꂽ�肵���s���� ������A��ɑO�����Ŗ��邩�����Ɠ`�����Ă��܂��B �@�ܘ_�A�J�߂邾���łȂ��A�u�𗧂āA���C���o���ēw�͂�����������܂����B �@���Ȃ��҂ɗ��z�Ȃ��A���z�Ȃ��҂Ɍv��Ȃ��A�v��Ȃ��҂Ɏ��s�Ȃ��A �@���s�Ȃ��҂ɐ����Ȃ��A�̂ɖ��Ȃ��҂ɐ����Ȃ��B �@�������̊i�����₵�����A�ł����A���̊i���͓��ɗL���ł��ˁB���t�������� �Ղ��̂ŁA�����������Ƃ��X�g���[�g�ɓ`����Ă��܂��B �@���邳�͂ƂĂ���Ȃ��ƁB���邭��������Đl�������ł����������̂ł��B �@���N�P�N�L��������܂����B���N���X�~�����肢�������܂��B �ǂ��������������}�����������B
- 11��3���i�y�j�i�L�j���~�G�[���n��50���N
�@�\���C���������y�����̕�̂ł���(�L)���~�G�[�������N�n�ƂT�O���N���}���܂����B �@�P�X�U�W�N�i���a�S�R�N�j�U���A���c�s�V�����ɏ����̔��ƂƂ��ēX�܂��I�[�v���A ��\��������эG�q���Q�V�̎��ł����B �@�������̖��Ƃ��Đ��܂�A�c�����͕s���R�̂Ȃ������������悤�ł����A�V�N�ɘj�� ��e�̓��a�����i�Q��a�@�ł̒��N�̓��@�j�łł������Ô�x�����̂��߂̑��z�̎؋��ŁA ��w�i�w�ǂ���ł͂Ȃ��A�Ȃ�S�����ĈӋC�������Ă������e�ɑ����Ƃ��x���邽�� �����n�߂܂����i���a�R�O�N�㓖���A���c�Ǝ҂ւ̌��N�ی��K�p�͔C�ӂ������̂ŁA���� ���Ă��Ȃ������悤�ł��j�B �@�����O�����Ŗ��邢���i�̏��т́A�؋���ԍς��邽�ߋN�Ƃ����ӂ��܂��B �@�Q�n���͐D����ߕ��������`���I�Ȓn��Y�ƂƂ��Đ��������߁A�ߕ������̎d���� �������������߂ł��傤���A�ߗނɎh�J����d�����n�߂܂��B���i�Ɏh�J����Ƃ����d���� ���s���n�߂����ł����B���̐V��������ɏ��A���l���̂��j�q������ق��Ď�����l�Z���� �����A�Q�S�̎��A���؋��ʼnƂ����Ă܂����i�{�l�͂��ꂪ�����ł����j�B�h�J�̎d���� ���s��Ȃ��Ȃ������ɂ́A�o�X�̎������~�����Ă����Ƃ������Ƃł�����A�]���撣���� �̂ł��傤�B �@�������������炪��ςł����B�����҂̍Ȃƕ���������Ȃ��Ȃ����v�͊Ԃ��Ȃ������A �Q�l�̖��Ǝ��Ƃ̕��A�č�����̋`���{���单���Ƃ��Ďd����簐i���܂��B �@�d�����g�p����ł����B�����ɍs���悤�ɂȂ�ƃI�C���V���b�N�A�܂�����ƃo�u�� ����A�傫�Ȕg�ɗh�炳�ꑱ���Ȃ���A�o�X�͉���܂ŋy�сA�������X�ܖʐς��g�傳���A ���N�̖����������c�w���ԊX�̘H�ʂɓX���\���܂����B �@���ԊX�̃r�����w���������A���т͐V���Ȃ�����̖������������܂��B �@���Q�l�������ŏK���Ă���搶�����̃��b�X����n���̑��̎q�����ɂ������Ă��������A �Ƃ��������v�����特�y�������J�݂����̂ł��B�P�X�W�R�N�̂��Ƃł����B �@�����������E���w���̍��܂ŏK���Ă����n���̐搶�ƁA���勳���⋳����������Љ�ꂽ �����̎Ⴂ�搶�����Ƃ̃��b�X�����e�Ⴂ�ɋ����������т́A�e�N�j�b�N�A���y�≹�F�̍������A �{����m���Ă���搶�ɏK�����Ƃ������ɑ���A�g�ɐ��݂Ċ����Ă��܂����B �@��b�����������ɋ�����ꂽ�q�������傫���Ȃ��Ă�蒼���Ȃ��Ă��悢�悤�ɑ������� ������Ƃ����搶�ɐG�ꂳ���Ă��������A���т̔M���v�������Ŏn�܂������y�����ł��B �@���т̎v���́A���N�R�T���N���}�����\���C���������y�����̑��Ɛ������ɂ���Ďp����� ���܂��B �@�Â��͔_�ƁA�ߑ�ł͍H�ƂŐ��������̂̕����s�т̒n���������c�s�̃\���C���������y�������� ��v����𑲋Ƃ������Ɛ����A�����O�̃R���N�[���Ő��ʂ������A�������z���Đ��E���Ŋ��Ă��܂��B �@�\���C���������y�����o�g�҂��A���呲�ƌ㑾�c�ɖ߂�A���E���E�����w�Z�̉��y�̐搶�Ƃ��� �A�E������A���y�����̐搶�ɂȂ�����A����ŋ������J���Ă��邱�ƂŁA���c�ߕӂ̉��y���琅���� �m���ɏオ���Ă���͂��ł��B �@�P�l�̑n�Ǝ҂̎v�����S���Ȃ�����ɂ��p������Ă���̂͊��������Ƃł��B �@��̂�(�L)���~�G�[���̕����A���ꂩ�����Ɍq���Ă��������ł����A��������ɂ������� ��ɂ��Ă������т̃��b�g�[�A�g�ŏ�����ō��̋����!!�h��Y�ꂸ�A���ꂩ�������܂��^���� �w�͂��Ă������Ǝv���Ă��܂��B �@
- 10��6���i�y�j�������ǂ����@�C�I�����R���N�[��
�@�V�Ђ��������{�ł����A���N�͑��Ô����R�̕��ɂ͂��܂�A�����{���J�A�F�J�s�œ��{�j�� �ō����L�^�����ҏ��A�����̒ܐՂ��c�����䕗�A�����Ėk�C���n�k�ƁA���r�ЊQ�w��̑�K�͂� �ЊQ���A�������N�ɂȂ�܂����B �@�V�ƒn���������h�ꓮ���A�܂�Ő������̏�≺�ŕ�炵�Ă���悤���Ɗ�����͎̂������� ���傤���B �@���̍��ɏZ�ނƂ������Ƃ́A�V�ЂƋ��ɕ�炷�o�傪�K�v�ł��B�����A���ꂾ���V���n���ω� ����y�n�Ƃ����̂́A�G�l���M�[�����Ă���Ƃ������������A���̓V�ƒn����̐��܂��� �G�l���M�[�����āA����̃G�l���M�[�ɕς��Ă������Ƃ��ł���A�f���炵���d�����ł��� �Ǝv���̂ł��B �@�O�����ɍl���Đ����Ă������Ƃ��̐S�ł��ˁB �@���N�̉ẮA�C���⎼�x�����낵�����������ł����A�q�������̃R���N�[���ł��M���撣��� �����Ă���܂����B �@�Q�O�P�W�N�W���R������T���ɍs��ꂽ�s��Q�����ǂ����@�C�I�����R���N�[���t�ɂ����āA T����i���c�s�㍇���w�Z�S�N�j�����܂��܂����B �@���̃R���N�[���́A�ߍ����s��̏��Ǝ�`�i�����ׂ��H�j�ی����̃R���N�[���ƈ�����悷�A ��ω��l�̂���R���N�[���ł��B �@�����L���̃R���T�[�g�z�[���Ƃ��Ė�����Hakuju Hall�I�[�v���̍ہA�u�Ⴂ���y�Ƃ̉��t�@��� ���v�Ƃ����ړI���f���A���̃R���N�[���𑫂�����ɖ����̃A�[�e�B�X�g���y�o����邱�Ƃ��肢�A (��)�������Ȋw���������A(��)���{���@�C�I�����̋��͂̉��A�n�܂�܂����B �@���̃R���N�[���A�R�����̊�Ԃ�����J�������O��Ă���̂������B���N�̐R�����͑�J�N�q�搶�A �������q�搶�A�v�ۓc�I�搶�A������������@�C�I���j�X�g�ł���Ȃ���A�����Y��A�˕�����A �@��������̊e�����i�������܂ށj�ł����������ŁA�m���Ȏ��ŐR������Ă���̂��킩��܂��B �@�����Ă��J���������I�P�ʂ̎q�ɂ́A�A�}�e�B�̕������@�C�I�������Q�N�ԁA�Q�ʂ̎q�ɂ͂P�N�� �ݗ^����܂��B���S�N�O�ɐ��삳�ꂽ���l����y�킪�A�J�e�S���[�P�i���w�P�E�Q�N���j�A�J�e�S���[�Q �i���w�R�E�S�N���j���ꂼ��̂P�ʂƂQ�ʂ̎q�ɑ݂��o�����Ƃ����̂ł��B�R�ʓ��҂܂ł� Hakuju Hall�ł̃R���T�[�g���o���ł��܂��B �@T���o�ꂵ���J�e�S���[�Q�Ɋւ��ẮA�^���R���łQ�T�����I�o����ė\�I�ɏo��A�X�ɂX���� �i���A�W���T���̖{�I�ɗՂ݂܂����B�c�O�Ȃ���T����͂R�ʂ܂łɂ͓���܂���ł������A�{�I �o��̂X���S�������܂Ƃ������ʂɏI���܂����B �@�����̃A�[�e�B�X�g����Ă邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���R���N�[���Ƃ�����������A�\�I�E�{�I���ɁA �R�����̐搶���S�����A�o��҂P�l�P�l�Ɍ����ŃR�����g�����������������ł��BT����͂R�l�� �搶������A�����[�^����� ���@�C�I�������t�� ��Q�Ԃ̉��t�ɂ��āA�t�@�≹�y���Ɋւ��� ��ϖJ�߂Ă��������A�t�����Ă���搶�̖��O���ꂽ�Ƃ������Ƃł�����A��ۂɎc�鉉�t�� �ł����̂ł��傤�BT����Ɩ��i�搶�̌����Ɋ��t�ł��I �@���̂R�l�̐搶������J�߂Ă����������̂ł�����A����̗��K�̃��`�x�[�V�������オ�邱�� �ł��傤�B���Ă��ꂽ�Ƃ��̌�������̊��������ȗl�q���Y����܂���B �@�s��P�����ǂ����@�C�I�����R���N�[���t�̓��҂������A���N�̑S���{�w�����y�R���N�[���� �e�҂ł��������Ƃ���݂Ă��A���̓��܂͉��l�̂�����̂ƌ�����ł��傤�B �@���ꂩ����ǂ����t���R�����A�[���������K�����A�v�X��Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �@T����A�R���N�[�����܂��߂łƂ��������܂��I �����Ă��ꂩ��̊����y���݂ɂ��Ă��܂��I
- 9��1���i�y�j�R���N�[��������
�@�W���Q�X��(��)�A����Е��s�A�m���T�C�^�����J�Â��܂����B�吨�̂��q�l�ɂ��炵�Ă��������A �������Ƃ��Ȃ����̑�R�̂��ԂՂ��܂����B�����Ɍ���\���グ�܂��B �@���N�̂W���͎��ɐ����R�ȂP�����ł����B �@���{�łP�E�Q�𑈂������x���̃s�A�m�R���N�[���A��S�Q��s�e�B�i�s�A�m�R���y�e�B�V������ �Q�l�̐��k������A�\�I�E�n���{�I�Ə����ɒʉ߂��A�Q�l�����Đ���̑S�����ɏo�ꂷ�邱�Ƃ� �ł��܂����B �@B���ɏo�ꂵ��K����i����܍��ۃA�J�f�~�[�������S�N�j�́A�Q�O�P�S�N�Ɋ�����������̂�݂��� ��蒬�z�[���AD���ɏo�ꂵ��K�N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������Q�N�j�́A�Q�O�P�O�N�Ɋ���������� YAMAHA�z�[���Ƃ������{�L���̃R���T�[�g�z�[���ʼn��t����@��Ɍb�܂ꂽ���Ƃ́A�Q�l�ɂƂ��Ă悢 �o���ɂȂ������ƂƎv���܂��B �@���ɎQ���l���̑���B���́A��N�̃f�[�^�[�ɂ��ƃG���g���[�����l�B�̒�����1.7���̐l�����S�� ���ɏo��ł��Ȃ��Ƃ����̂ł�����A�@���ɓ�ւȃR���N�[�������킩��܂��B �@�c�O�Ȃ���Q�l�Ƃ����܂͊����܂���ł������A�S�����o��Ƃ������ʂ��ւ�Ɏv���A�v�X�撣���� �����ė~�����Ǝv���܂��BK����AK�N�A�S�������I���߂łƂ��������܂�!!! �@�����ċx�݊��ԁA���y�̎�������N�͖����ꏏ�ɗ��K����Ƃ������Ⴊ�A���ꂱ��Q�O�N�ȏ� �����Ă��܂��B���X���A�_��̑�����n�܂�A�R�[�����[�u���Q���V�Ȏ������̃\���t�F�[�W�����݂āA ���̌�̂��Ă����܂��B �@���܂Ő�����R�̐l�����ƃg���C���Ă��܂������A�ċx�ݒ��A�����Ƃ����̂͑����L�c�C�炵���A �I��荠�ɂ͎��悤�Ȋ�Ŏu�]�Z�̕ύX�������Ă�����A�̒�������Ē��~�ɂȂ�����A���������Ă� �{�[���Ƃ��ĕ���������Ȃ��Ȃ����肷��l�������A�̗͂̒ቺ�ɔ����C�͂̒ቺ��i����l�������ł����B ����������ōŋ߂́A���ʂ������Ȑl�����Ɍ����Đ����|���A�g���C����悤�ɂ��Ă���̂ł����A ���N�̎q�́A���������肻�����Ɠ���Œ��킷�邱�ƂɁB �@���͉����Ɍ������Ē��킵�Ă������ƁA���Ɏ���D���ł��B�����ǂ�ȕ��ɂł���悤�ɂ��Ă������� �ڈ����͂����肳���A�����I�A�Z���I�ȖڕW�Ɍ������ė��K����Ƃ����ߒ����y�����Ďd��������܂���B ���Ɋ�X�Ƃ��ĕt�������̂͂��̊y���݂����L�����Ă��炦�邩��ł��B �@���ɕt�������������ςł��傤���A���y�͎������g�Ŏ����̖{���̐������Ƃ��ł��Ȃ����߁A �{���Ȃ�Η��K�ɃR�[�`�̑��݂͕K�{�Ȃ̂ł��B �@�̂��y��ł�����̂̏_����d�v�B������A�_��̑������ĂˁA�ƌ��Ō����Ă��A��������l�͋H �i�F�����Ɏ~�߂Ă��܂��܂��I�j�B�Ċ��W�����K�ł͕K��������܂��B�P��������Ă���Ɛ����� �_�炩���Ȃ���̂ł��B�ꏏ�ɂ��l������Ɗy�������A���`�x�[�V�������オ��܂��B�K���t�����ł���� ���R�Ƃ��̂܂�1�l�ł������Ă������Ƃ��ł��܂��B �@���N�̎��͂ւ����ꂸ�A�S�O���Ԋ撣��ʂ��܂����B��������̐L�тɑ傢�Ɋ��҂���Ƃ���ł��B �@���E�ǂȂǂ̃I�[�P�X�g���y��̐搶���́A���i����W�c�ōs�����邱�Ƃ��������߂��A�ċx�݂Ȃǂ� ���������˂ĎR��n���ʼnĊ��u�K���s�����������悤�ł��B�\���C���̐��k�������A�k�C���� �I�z�[�c�N�C���݂ł̍u�K�ɏo�|���čs���܂����B������ʂ�z���āA�Ȃ��������ł��ˁB �@���@�C�I������Y����i�����Y�p��w���y�w�����������w�Z�P�N�j�����]�t���ۉ��y�R���N�[�����y�핔�� ���Z�̕��ő�Q�ʂɓ��܂��܂����I���߂łƂ��������܂�!! �@�撣�����Ă̗��K�̐��ʂ��A�H�ȍ~�̑f���炵���B���Ɍ��т��Ă������Ƃ�����Ă��܂��B
- 8��17���i���j��{��m�邿���Ƃ����l
�@�c��������A������ǎ��Ȃ��̂ɐG��Ă����̂͂ƂĂ���ł��B�|�p������A�X�|�[�c������B �����������炻�̕���ő�z�����l�╨�ɐG��Ă���ƁA���ӎ��ɁA���̂悤�ɂȂ낤�A�����o���� �悤�ɂ��悤�A�ƈ���Ă����܂��B �@���̃G�b�Z�C��ǂ�ł��������Ă����l�̕������̒��ɂ́A�����Ȃǂ̃X�|�[�c��K�����ɖ����� �Ȃ��Ď�g����Ƃ̂�����������ł��傤�B���K�������Ɍ��ʂ��o�Ȃ�������A�̂��̏Ⴕ���� ���āA�w�͂��`�ɂȂ炸�s�{�ӂȌo�������ꂽ���͂�������Ⴂ�܂��B �@�������������R�̏K�������Ă����o���̒��ŁA��{���������Ă���������搶�ɏK�������m�Î��́A ���Ƃ����ꂪ��͈̔͂ł��A�����������鎋�_���g�ɂ��ȂǁA��{�̒ʂ����f�l(��)���`������� �̂��������Ă��܂��B��{�����������Ȑ搶�ɏK�����K�����́A���ʂ������Ȃ��������Ƃ��o���ς݂ł��B �@�v����ڎw���Ȃ�A�v���ɂȂ�܂łɗ^����ꂽ���Ԃ͌����Ă���̂ŁA��{��������Ƌ����ĉ����� �搶�T�����K�{�ł��B��蒼���Ă��鎞�Ԃ͂Ȃ�����ł��B���̏K�����́A�e�̋��͂Ȉӎu������ꍇ�� �����A���F�B������Ă��邩��A�ߏ��ɐ搶����������A�Ȃlj��炩�̋��R����X�^�[�g���܂��B�n�߂� �݂���y�����āA�ꐶ�������K������A�Ⴆ�Ζ싅�Ȃ�A�����Ƒ�����������悤�ɁA�����Ɨ͋��� �łĂ�悤�ɁA�Ƃ����ӎu�������āB �@�������ė��K���d�˂Ă��������ɃR���g���[���ǂ�������������悤�ɂȂ�A�ŗ����オ���Ă����܂��B �������A�w�N���オ��Ɩ����ȗ��K���M���Č���ɂ߁A����ɂ߁A���x�����Ђ��L�т��A�Y�ނ悤�ɂȂ����� ���܂��B�����ŏ��߂ċؓ��̏_���̂̎g�����ɂ��ĕ����n�߂邱�ƂɂȂ��ł��B �@�t�H�[����̂̎g���������ƂƁA�L�^��L�����Ƃ͈�x�ɂ͏o���Ȃ��ł�����A���ԂƂ̒ǂ����������� �W�����}�Ɋׂ��Ă����܂��B �@�싅�̐��E�ł́A��{����Ƃ������Ƃ��A���K�̏��߂��番�����Ĉ�Ă�ꂽ�̂��A�C�`���[�I�� �ł��傤�B �@���炭�C�`���[�I��̕��e�̎��s��ƂɁA�̂̎g�����̑�P������t��������ŋ�����ꂽ�C�`���[�́A �S�O���z���Ă��̏�Ȃ��A�Ȃ��i���������Ă��܂��B �@�l�ԍ���ł���̕���̍Ⓦ�ʎO�Y�䂪�A��{�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �@�@�����Ƃ����l����A��������Ƃ�����{������邱�Ƃ��d�v�ł��B�g�ςȕȂ�t���Ȃ��h���Ƃ� �@��ł�����B�g�̂Ɍ̏Ⴊ�N�������ɁA�����������ɂ���Ă����ǂ��������ɂł����p�������A �@�Ƃ����̂��u��{�v�B�����g�ɂ��Ă����ɐi�����Ƃ���ƁA�ǂ����Ă����Ԃ�������B������A �@�Ȃ̂ق��ɑ��肪���ɂȂ邯��ǁA��������ƒx���ꑁ����s���l�܂鎞������B�����I�Ɍ���A �@�ǂ��炪�����͖��炩�Ȃ��ƂȂ�ł��B �@�g��{��m�邿���Ƃ����l�h�́A���̓��̃X�y�V�����X�g�Ȗ�ŁA�ꐶ�����̏C���ʼn߂����Ă��� ���܂�����A�l�ԓI�ɂ��s�V�b�Ƌ��ʂ��Ă��āA�l�i�I�ɂ��D�ꂽ���͓I�Ȑl���������̂ł��i������ �Ȃ��l���ܘ_���܂��k�l�j�B�g��{��m�邿���Ƃ�����l�h�ɁA������������ڂ��邱�Ƃ͂ƂĂ� ��Ȃ��ƁB���̂Ȃ�l�Ԃ́A�T�ɂ���l�ɒm�炸�m�炸�̂����ɍl������s�������Ă��邩��ł��B �@�w�a�y�x�Ƃ����������́w���ׂĂ͕���̔��̂��߂� �Ⓦ�ʎO�Y�x�Ƃ������b�N�{����肵�ăp���p�� �ǂ�ł�����A�����Ɍf�ڂ���Ă����ܒ~���錾�t�Ɉ����t�����A�����̃G�b�Z�C�������܂����B �@�������X�^�[�g���悤�Ƃ��Ă�����ɓ͂���ꂽ�A�l�ԍ���̑f�G�ȃ��b�Z�[�W�ł��B
- 7��7���i�y�j�u�Y���̌��J���Z�����v�����^
�@�U���P�V���i���j�E�Q�Q���i���j�̗����A�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�i�ȉ��A�Y���j�� ���J���Z�����ɍs���Ă��܂����B �P,�P�O�Q�Ȃ��Y��t�y���͂قږ��ߐs������Ă������Ƃ���A�l�X���Y���ւ̊S�̍������M���܂����B �Y���̃��x����m���D�̋@��ƌ�����R���T�[�g�`���̎����ł��B �@�Q�N�O�ɏ��߂Ē��������ɂ́A�P�V�`�P�W�̔N��̎q�B���A�S�����������Ă��̂悤�Ȑ����ʼn��t ����̂��ƁA�����������A���|�����������܂����B���ɖ������̉��t�Ƃ����������̏W���́B �@����܂Œ��N�ɘj��l�X�ȃR���T�[�g��T�C�^���A�R���N�[���A�����Ď��������ɍs���܂������A �o���ґS���������āg�����h�ȉ��t��ڎw���Ď��g��ł���̂������̂́A���܂�Ďn�߂Ă̌o���� �����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �@�s�A�m�͎������ԂQ�O���A���͂P�T���A���ꂼ��̐��k���e���̂́A�����A��Ȃƌ�����Ȃ���ł��B �~�X�Ȃ��e���͓̂�����O�A������ȉƂɑ��������ȑz�Ɖ��F�ŁA���Ԃ������ė���グ���Ȃ����t���� �����܂��B �@�P,�P�O�Q�Ȃ̍L���L���t�y��������ł����悤�ɐÂ܂�Ԃ钆�A���䒆���܂łQ�O���������ē��B���� �������Y�����i���ɏ��̎q�͐g���P�T�O�p�O��̎q������!!�j������̑傫���䂦���A��菬���������܂��B ���܂�̏������ɁA���v�Ȃ̂��낤���A�v���b�V���[�ɉ����ׂ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���ƐS�z�� �Ȃ�̂ł����A���t���n�߂�Ƃ��̓��X�Ƃ������t�Ԃ�ɐS�z�̓X�[���Ɖ����A�t�y�����ɖ苿������ ���|����Ă����܂��B �@�Y�����̒��ɂ́A�x���ȂǂP���P�T�`�P�U���ԗ��K����q������ƕ����܂����i�w�Z��������́A�A��� �����Q�Đ[��P���߂��ɋN���A�w�Z�ɏo�|����܂ł̂U���Ԃ���K�p�Ɋm�ۂ���q���I�j�B�����̗��K�� ���ԑт���@�ȂǁA�����ɍ����������ŁA�x����������Ǝ���đ̒��𐮂��Ȃ���A�����̈ӎu�ŗ��K����A ���ɏC���҂̂悤�Ȗ����𑗂��Ă���q������悤�ł��B�P���R���Ԃ������K���Ȃ��Ƃ������҂����āA ���������q�͐搶�̎w�����I�m�ŁA���K�̏W���͂����܂����̂��낤�Ƒz�����Ă��܂��B �@����͓��{�����T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�ɗN���܂������A���[���h�J�b�v�̏o��I��ɂ��Ă��A �I�����s�b�N�̑I��ɂ��Ă��A�c��������t���ɂ����āA�P�̂��Ƃɂ����W�����ďC�Ƃ��Ă��� �ނ�̗E�p�ɂ͂����������o���܂��B �@����͉��ł���A���������Z���Ȏ��Ԃ������Ƃ��ł��A�����̎����Ă���\�͂��Ɍ��܂ō��߂��� ���������Ă���l�͖{���ɍK�����Ȃ��A�Ƌ����v���܂��B�C�Ƃ�ςݏグ�A�����̔\�͂����߂Ă����� �K���ƁA�������č��߂�ꂽ�Z���I���A�������ĉ�����l�X�Ǝ������L�ł���K���B �@�����̔\�͂̌��E�ɒ��킷��@����P�V�`�P�W�ŗ^����ꂽ�Y���������́A�A�C�Ȏq�ȂǂP�l�����Ȃ��āA �F�A���邭����₩�ȋC�ɖ������A�f�G�Ȏq��������ł��B���X�����Ă��邩��A�����s���Ƃ����� ���̋C�����������Ƃ������̂ł��傤�ˁB �@���N�U���̂R�T�ڂɂ��̌��J���Z�������Y��̑t�y�����ŊJ�Â���܂��B�P�O��̒���҂����̉��t�� ���ۂɒ������Ƃ��ł��܂��̂ŁA�@��������琥�o�|�����������B�ڂ������Y����HP�ŁB �@�W���Q�X��(��)18:00����A�Y���s�A�m��U�R�N���̊���Е��N���A���c�s�w�K�����Z���^�[�����o�z�[���� �s�A�m���T�C�^�����s���܂��B �@�h�C�c�E���}���h�̋Ȃ𒆐S�ɁA�V���p���A�t�H�[�������t����v���O�����ł��B���ꖳ���B����ɂ� ���������K�v�ł��B�������̓\���C���������y�����Ŏ�舵���Ă��܂��B���U�����킹�̏�A�吨�̕��� �����ꂢ����������Ǝv���܂��B �@
- 6��2���i�y�j�}�N���r�I�e�B�b�N�͉䂪�Ƃ̃��Z�b�g�H
�@�ȑO�A�����ȃs�A�j�X�g�̃��b�X���𑧎q�����ہA���F�≹�y�ɂ��āA���ɑf���炵�������� �����������̂ł������A�y�Ȃɂ��Ă̒��ӂƂ͕ʂɁA���̂悤�Ɍ���ꂽ�̂���ۓI�ł����B �u�ǂ����y���̂��ܘ_������ǁA�G��������A�f����ς���A�{��ǂ�A���G�̗ǂ����̂� �@������A�����������̂�H�ׂ��肷��̂͂ƂĂ���Ȃ��Ƃł��B�]�́A�܊��̂ǂ̊��o������������ �@��������Ƃ������Ƃł�����A�܊��̐F�X�Ȋ��o���o�����邱�Ƃ��A�s�A�m�ŕ\�������łƂĂ� �@�d�v�Ȃ̂ł��B�v �@ �@��s�A�j�X�g�ɂ�������ꂽ�̂�����A����U���Ĕ����������̂�H�ׂ܂��傤�I�Ɗ�Ԃ̂� �H������V�̕�ł��鎄�B �@���̗��Ŕ����������̂ɂ��ď����ƁA�K���ƌ����Ă悢���炢�F�X�ȕ����犴�z�����������܂��B ���̎���ɂ�����������X�́A�H�ׂ邱�Ƃɑ���S�������A��s�A�j�X�g�H���A�g�܊��i�̈ꕔ�H�j�� �������܂���Ă���h����������Ƃ�����ł�(��)�B �@�������ŏo�`�����A�Z���ȃo�^�[��N���[���ƍ��킹���\�[�X�ŐH���`���I�ȃt�����X������A �u�ߕ���g�������������ؗ�������D���ł����A�ߍ��́A���o�`�ł����A������A���̌b�݂����ŗ������� �}�N���r�I�e�B�b�N�ɂ��Ƃ��Ă��܂��B �@�}�N���r�I�e�B�b�N�͓��{���܂�̒����@�ł����A���N�ɊS�̂��鉢�Đl�A�Ⴆ�}�h���i��g���E �N���[�Y�Ȃǂ��A�}�N���r�I�e�B�b�N�̗����l����{���珵���ė�������点�Ă���̂͗L���ł��B �@�}�N���r�I�e�B�b�N�́A�ӂ�����Ɛ��������Ă��тƁA�����ő��⍩�z�ł��o�`�����������C�� �����Ղ�̂����X�`�A�Ђ��n�߂Ă���R�N�ȏ�o�߂����`���I�Ȑ��@�ɂ��~���ƍ��Y�̍�����Ӗ��� ��荇�킹����{�B����ɐ花���卪��Ђ����̎ϕ��A�����@���̂���҂�A���̐������킹�Ȃǂ� �Y���܂��B�������ɔ������Ƃ���ނ͎g���Ȃ��̂ŁA�Â݂͍������₨�Ă��������ē��Ȃǂŕ₢�܂��B �������Â݂����A��Z�Ə������~�l�����������Ő������킹��������Z�́A���悢�Â݂��������� ��ɑ̂����܂閜�\��ł��B �@�R�N�O�A���q�̎��ɑ̒�������{���{���������܁A���̒����@�����������Ƃł������茳�C���� ���Ă���A�䂪�Ƃ̃��Z�b�g�H�Ƃ��Ē蒅���Ă��܂��B�@ �@�t�����X�����⒆�ؗ����A�Ă����W���E�W���E���̂ē�A��ɉ̂��O�Ȃǂ̓G�l���M�[��[�ɕs�� �ł����A�̒�����������A�̂̉��������ɂ����Ȃǂɂ̓}�N���r�I�e�B�b�N�͌��ʂ�����܂��B �@�₦�͖��a�̌��A�ƌ����܂����A�����Ă��Ă��葫���ƂĂ��₽���������āA�����������͉������� �s����i���Ă�����̂ł��B�}�N���r�I�e�B�b�N�����s����Ǝ葫���|�J�|�J�ɂȂ�܂��B�₦���̕��ɂ� ���ɂ��E�߂ł��B �@������̂��o�`�Ȃ�āA���������Ȃ��̂ł́@�@�H�Ǝv�����Ȃ��A���ꂪ�ӊO�Ɣ��������̂ł���B �����ő��ƍ��z�̂��o�`�ɋ���A�����A�l�Q�A�@���A�卪�A�킩�߂Ȃǂ�����ƁA��̊Â݂ƍ���A �����Ė��X�̎����Ƃ����܂��āA��q�ő��l�Ȗ����y���߁A�S���O���邱�Ƃ�����܂���B �@�`���I�Ȏ�@�ō��ꂽ����A���ؒЂ������_���y�����_���ς����A���悭�H�~��������܂��B �@��H�̐H���ɁA���h���A�Â��A�_���ς������Ɏ�荇�킹��ƁA�H�ׂ��ʂ�薞�����̕����傫�� ���Ƃ́A���̂���܂ł̌o�����番����̂ł����A���R�ɂ�����̂����̌����ŁA�����ɂ��̎�葵���� �ł���̂͗L����Ƃł��B �@���������Ɗ����邱�Ƃ͍K���Ȃ��ƁB���̊�т������Ȃ���A���N�Ő��͓I�ɁA�|�p�I�ȓ��X�������� �ō��̐l���ƌ����܂��傤�I �@����A���������Ȃ��ꂳ������������������܂����B �@�\���C���ɂQ����ʂ��Ă��Ă��邨�q���A���w���w��̎��̓e�X�g�ŁA�w�N�P��!!!������� �Ƃ̂��ƁB �@���������ӂ��ɕ������Ă����Ɨǂ��ł���A�Ƃ��E�߂��Ă��������@���A��������������s���� ���ꂽ���ʂł��I �@�������ł��ˁB �@
- 5��5���i�y�j���k����̌������Łc
�@�S���̑f���炵���ǂ����ꂽ���A�\���C���̐��k����̌�����������A���j���ɏo�|�������܂����B �@�ߍ��͒n�����Ƃ����̂ł��傤���A���̌������́A�e�ʂ₲���e�����F�l�����̔�I�����������߁A �������ɏo�Ȃ���̂͂P�T�N�U��B �@��L�ɔh��ȃo�u�������ǂ����Ƃ͎v���܂����A���j�����́A�������肽���Ǝv����悤�ȁA���邭 �₩�ȋ����Ɣ�I���ł����B �@�����g���[���������������E�F�f�B���O�h���X�A�Ԃ��Ŋ|���A�Ō�ɃL�����f�B�J���[�̃J���[�h���X�B ���i�͍T���ڂȂ��삳��Ȃ̂ŁA�������̍��Ȉߑ��R�A���Ƃ̃M���b�v�ɋ����܂������A����ł̋����� �P�[�L�J�b�g�ȂǁA���̎q�D�݂̉��炵���Â���������A�ԉł̔��������ۗ������A�K�������ڂ̌����� �ƂȂ�܂����B �@�V�Y���Z�Ղ̖���ŁA�l�\�H�Ƃ������Ƃ�����A��B����o�Ȃ��ꂽ�����Z�Ւ��Ԃ̗F�l�̏j�����A �F���j���C�����Ɉ��Ă��ĐS��ł��܂����B �@���̐��k����ł���V�w�́A�s�A�m�A���y�A�\���t�F�[�W�����T�Ύ�����Q�O���N�����A�E�ƂƂ��Ă� ���y����Ƃ��Ă��܂��B �@�ǂ�Ȃ�����ƌ�������̂�����`�H�ƃh�L�h�L���Ă�����A��͂肨����̕����A��s���Ȃ���Z�Ղ� �c��������n�߁A���w���ォ��S�����Ȃǂɏo�ꂵ�A���ł����̊����𑱂��Ă���������Z�Ղ̃v�� �̂悤�ȕ��B �@��I���ɏo�Ȃ��ꂽ���F�l���A�M�l�X�L�^�����l�ȂǁA�S������Q�W�����B�X�����Ԃ�ŁA�ނ炪 �����t���b�V���ÎZ�̖��Z�Ɉ��|����܂����B �@�����A����l�͎������̓��m�B���݂��Ɍ��シ��ڕW�������Ă��邽�߁A����̂��Ƃ𗝉��������� �f�G�ȃJ�b�v���ƌ����܂��傤�B �@�ޏ��̃s�A�m�̐搶�ł���דc�G��搶�A�\���C������̒��Ԃł��郔�@�C�I�����̐X�F�I����Ƌ��� ���t���v���[���g�����Ă��������܂����B �@�������J�ŁA�V�Y�V�w�������ƃj�R�j�R�Ί炾�����K�������ς��̌������A���̍K���������i�������܂� �悤�ɂƋP�����z�Ɍ������ċF��܂����B �@���̌������ʼn�����������ɍĉ�܂����B �@�V�w�̓������ŁA���w���̎����獂�Z�R�N���̂R���܂Ń\���C���ɒʂ��Ă��Ă���Ă���T����B �@T����́A���c���q���Z����c����w�ɐi�w�����̂ł����A���R�̂R���܂Ńs�A�m�̃��b�X���𑱂��Ȃ��� �c���ɍ��i�����ˏ��ł��B���Z���ォ����l��T����ł������A�������A��w�������Ȃ�܂����B �@�����������Ƃ������Ƃł�������A�ޏ����lj��Ɍb�܂�邱�Ƃ�����Ă��܂��B �@���Ɛ��Ƃ����A�T���獂�Z�R�N���̂R���܂Ń��b�X���ɒʂ��Ȃ���A���ȑ�w�ɍ��i����B���� ���Ȉ�t���Ǝ����ɍ��i�����ƘA��������܂����B �@���C��Ƃ��Đ_�ސ�̕a�@�ɋΖ����Ȃ�����X���C�ɗ��ł���Ƃ̂��ƁB���Ɛ��̊���͂ǂ̕���� �H�����Ă����Ă����������̂ł��B �@���̏t�͓����Y�啍�����Z�i���@�C�I������U�j���͂��߂Ƃ��鉹�y��w�A���y���Z�ɂS�l�����i���A ���N��ĂĂ������k����̌����A���Ɛ��̊���̕ȂǗǂ��j���[�X�������܂����B �@�l���ǂ����Ƃ���N����킯�ł͌����Ă���܂��A�ǂ��Ǝv�����k�����Ƌ��ɂ���܂� �������������ʁA���������`�ōK���������ł���Ȃ�āA�l���̂Ă����̂���Ȃ��Ǝv����f�G�ȏt�� �Ȃ�܂����B
- 4��5���i�y�j�Y��E�t�y���̃p�C�v�I���K���Łs�C�����F���V�����t
�@���̂Q�O�N�ԁA�����Q�n�ł��C�����X�_���܂ʼn����邱�Ƃ͖ő��ɂȂ������̂ł����A ��N�Ɉ����������̓~���X�_���̓��������������܂����B �@��N�͉ԗ₦�ł��Ԍ��ɏo�|���悤�Ƃ����C�ɂȂ�܂���ł������A��C�ɒg�����Ȃ��� ���t�́A�����Ƃ����Ԃɍ������J�ɂȂ�A�����ċC�t�������ɂ͎U���Ă��܂��Ă��āA ���N�����Ԍ����ł��Ȃ������͎̂c�O�ł����B �@����ɂ��Ă��{���ɒg�����߂����₷���t�ɂȂ�܂����B���N�̎��S�l�������i�w���A �tࣖ��̒��A���w���ɗՂނ��Ƃł��傤�B �@�t�x�ݒ��A�w�����Y�呁������v���W�F�N�g���ʊ��`�t�y���̃p�C�v�I���K����J.S�o�b�n �s�C�����F���V�����t��e���Ă݂悤�x���J�Â���܂����B �@�ߋ��R�N�ԂɁw�Y�呁������v���W�F�N�g�x�̃s�A�m���b�X������u�������E���w�����G���g���[ ���i��^�����A���O��DVD�R���ɍ��i�����l���Y��t�y���ɐݒu���Ă����p�C�v�I���K���� �e�����Ƃ��ł���Ƃ������ʊ��B���̐R���������ʉ߂��AK�N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������Q�N�j�� �M�d�ȑ̌������Ă��܂����B ���̊��́A�v�����u���q�������̂��߂ɁA�����̗D�G�ȉ��t�Ƃ̈琬��ړI�Ƃ����Y�傪�W�J ���Ă���v���O�����̈�B�s�A�m��e���l���e����ł���o�b�n�́s�C�����F���V�����t�� �p�C�v�I���K���Œe�����Ă��炦��Ƃ����̌��^�w�K�ł��B �@�����́A�Y����̃p�C�v�I���K�����ݒu���Ă��郌�b�X�����ŁA���O�̑ł����킹�����Ă��� �{�ԂɗՂ݂܂����B�w�ʼn��F�⋭���e��������s�A�m�ƈႢ�A���F�⋭����A�X�g�b�v���o�[�� �Ă������̂悤�Ȃ��̂̑���ɂ���čs���܂��B�X�g�b�v���o�[�̒����ɂ��t���[�g�n�A �g�����y�b�g�n�Ȃǂ̉��F��I��A�������X�g�b�v���o�[�̒����ƒe�����Ղ̒i��ς��邱�Ƃ� �����\�����܂��B�ł�����A���t�O�̃Z�b�e�B���O���d�v�ł��B �@���[�h�n�̌y�₩�ȉ��F��I��Łs�C�����F���V�����t��No.10��e��������N�A�s���s���Ɩ� �����̚e�����������i�I���K���̑���ɂ���Ĕ����鉹�炵���E�E�E�j�A�c���n�т𐁂��n�� �t�̕��̂悤�Ȗ��邭���炵���ȂɎd�オ��܂����B���̑�I���K����e���@��ȂǁA���ʂł� �����Ȃ��̂Ŗ{���ɋM�d�Ȍo���ł����B �@�Ȃ��Ȃ��������̂悤�ȑ̌�������ƁA�����o�b�n��e�����ɁA�����e���Ă��郂�_���s�A�m�� ���Œe�����A�p�C�v�I���K���Œe���悤�Ȃ��ɒe�����A�������̓p�C�v�I���K������������ �g�߂ȃ`�F���o���̂悤�ȉ��F�Œe�����A�Ƃ������̑I������������ł��傤�B��x�e�����p�C�v�I���K���� �����Ƌ߂����݂ɂȂ�܂�����A�p�C�v�I���K���̉��y�������ƒ������Ƃ����C�����܂�ł��傤�B �ŋ߂悭���t����Ă���p�C�v�I���K���̉��y�̓o���b�N����̏@�����y�ɏW�����Ă��܂�����A ���܂ŋ����������Ƃ����Ȃ������o���b�N���y�ɋ}�ڋ߂���D�@�ɂȂ邩���m��܂���B �@�H�ׂ������̎q���́A�H�̌X�����C�����邽�߂ɁA���̎q�̌����Ȗ����Ă邱�Ƃ���n�߁A ����̎�Ŏ��n����������g���ė�������Ɗ��ŐH�ׂ�悤�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȏ������ʂ� ����܂��B����Ɠ��l�A�����̉��y�Ƃ����ɑf�G�Ȍo����^���邱�Ƃ��A�����I�ɉ��y�Ǝ��g�� �͂�L���Ȕ��z�ޗv���ƂȂ�͖̂��炩�ł��B �@���̌o�����A�����̖��I���K�j�X�g��a�������邫�������ɂȂ邩���m��܂���B �@�q���̏����͑f���炵���o���ɂ��\�����L����܂��B�\�����L����o�����R������ �����������̂ł��B
- 3��3���i�y�j�w�Ō�̔鋫�`�����Y��x�^�ʎO�Y��̋��P�Ɋw��
�@��N�AJR�̒��݂�L���Ő���ɐ�`����A�J�Řb�蕦�������w�Ō�̔鋫 �����Y�� �V�˂����̃J�I�X�ȓ���x�i��{�l���j��ǂ݂܂����B �@�Y��ɂ͉��y�w���Ɣ��p�w��������܂����A�������Y�咤���Ȃ̊w���ƌ����������҂��A ������̓���̓˔ɏՌ����A������Y��ɋ����������Ă����������������ʔ����� �U���܂��B �@�|��̔��p�w���Ɖ��y�w���́A��������ŏ������̈���ɑ��݂��܂��B�݂��̌𗬂� �w�ǂ���܂��A�]���E�C�������Č����̒��ɓ��ݍ���ōs���Ȃ�����A���̋����Ƃ� �s����������܂���B �@�������̟B�̑O�ɕt���Ă���ŔƂ�������Ȃ��̂��쐬���A���p�w���Ə�쓮������ �ڂ���ӏ��Ɂw�z���T�s�G���X�x�ƌf�������b�i���p�̐l�����͉����牽�܂Ŏ���ł��� �E�E�E�j�ȂǁA�w������ɕ��������Ƃ�����G�s�\�[�h���ڂ��Ă��܂������A���p�w���� �ւ��Ă͖w�ǒm��Ȃ����Ƃ���I �@�����q�ŏĂ����߁A���T�w�������݂ɔ��܂荞�ށi���̂��߂̂Q�i�x�b�h�␆���{�� �܂ł���炵���E�E�E�j�A�b���A�����A�����Ƃ��������������Ȃ́A�V�����̓����Ȃǂ� �啨����A�N�Z�T���[�܂ł�����͈͂ŁA���H��̂悤�Ȑݔ��������Ă��铙�X�B �@���p�w���̐l�������A����������Y��Ȋi�D�������w�H�ł��т�H�ׂĂ����i����I�j ���R���킩����e�ł��B �@�������͔̂��p�w�������w�����ő��Ƃ܂łɎ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��w�Ȃ̒P�ʂ͂Q�O�P�� �i�P�O�Ȗڂ����`�j�ƁA�j�i�̏��Ȃ��B�P�`�Q�N�͂قږ����A���X�F�O�O����[���T�F�O�O �܂ʼn�������̎��Ƃ�����A�R�E�S�N��������w�ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������y�ȂƂ́A �ʂ̑�w�̗l���ł��B �@���̑���A���Ԃ͐���ɏ[�Ă邱�Ƃ��ł��A�Ƃ��w�ŖفX�ƁA��o��i���܂� ����������Ă���Ƃ����̂͌|�p�Ƃ��ۂ��ėǂ��ł��ˁB �@����A���y�w���ɂ��Ă������[�����e���L����Ă��܂��B���K�ɉ����Ԃ���₳�Ȃ���� �Ȃ�Ȃ��s�A�m�Ȃɂ��Ă͋����ɂ��Ȃ�悤�ȃG�s�\�[�h���ڂ��Ă��܂����A���݂� �U���L�q�����ڂŁA���ꂩ���Y���ڎw���l�ɂ��A�����łȂ��l�ɂ��A�Y��̃J�I�X�Ԃ� �������ɕ`���ꂽ���̖{�A���E�߂ł��I����A�ǂ�ł݂Ă��������I �@�b�͕ς��܂����A�\���C���̍��N�x�̎��S�ďI�����z�b�ƈꑧ��������A �̕���̏��`�̑��l�҂Ől�ԍ���ł�����Ⓦ�ʎO�Y��̋L����ǂ݁A���������̂� ���Љ�܂��傤�B �@�ʎO�Y��̔���������p���������Ƃ̂�����͑����ł��傤�B����������������p�Ƃ� ���ʁA�P�Δ��ŏ�����Ⴢɜ늳���A���s���ł��Ȃ��Ƃ�����Q�������Ă����c��������l���� �X�^�[�g�������Ƃ�m��l�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����̐��܂�ł͂Ȃ������l�C���`�ƂȂ�A���̔��I�Z���X�Ɠ��̗ǂ��ŗl�X�ȕ���̉����� �o�����A���o�ƂƂ��Ă����������߂��͖̂ܘ_�A�^�̗ǂ������ł͂Ȃ��̂ł��B �@���w���̍������t�@�����������߁A�����ōs���S�Ă̌������ςɍs���Ă�������������܂������A �A�����������邽�߂ɖw�ǂ̉̕�����҂�������������ɁA�q�Ȃ߂Ȃ���A�ڂ̕\��Ƃ� �S���Ⴄ�䎌�������Ă����̂ɑ��A�ʎO�Y��ƕЉ��m���q��i�����͍F�v�j��A�������O�Y �i�����͊���Y�j�䂾���͂����^���ɕ�����߂Ă��܂����B ����������ɂ͓w�͂���ł��B�w�͂ƌ����Ă������̓w�͂ł͑ʖڂł��B������Ȃ����� �@�m��Ȃ��A���ɗ����Ȃ������m��Ȃ��F�X�ȓw�͂��U�X���āA�w�͂̕�������܂��Ă��� �@�i����ł��Ȃ��Ȃ����ɂ߂��Ȃ����̂�����ǁj�A���⌒�N�ƈ��������ɂȂ鐡�O�܂� �@�w�͂��Ȃ�������Ȃ��B �����̂�邩���������藝�����Ă��ׂ����Ƃ�����B����́g�s�h�ƌ����A�g�s�h�͋��ɂ܂� �@���˂Ȃ�Ȃ��B �����̂��߂ɂ��̂�������Ȃ��Ȃ鎞�ɂ́A�V���猩���Ă���Ǝv���A���^�ʖڂɂ�邱�ƁB ���������Ƃ�����Ȃ����ƁB ���̂ɗǂ������Ȃ��̂�H�ׂ邱�ƁB �@�����͐l�ԍ���A�ʎO�Y��̋��P�ł��B �@���̏t�A�\���C������H�����Ă������Ɛ��ւ��S�ɑ����������t�ł��ˁB �@�V�������E�ɔ�ї����Ă����P�W�̑傢�Ȃ�������҂��Ă��܂��I�@
- 2��3���i�y�j���@�C�I�����ł܂��Y�����i!�I
�@�P���Q�T���i�j�A�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�̍��i���\�̓��A �\���C���͑傫�Ȋ����ɕ�܂�܂����B �@�Q�N�O�̃s�A�m��U���i�ɑ����A���@�C�I������U�̂x����i���c��E �������w�Z�j���A��ւ������蔲�������A�Y���ɍ��i���܂����B �@�x����͂R���烔�@�C�I�����̖��i��ΐ搶���艖�Ɋ|���Ĉ�ĂĂ��� ���k����Ƃ������Ƃ������т��ЂƂ����ł��B �@��͂菬���������炫����Ƃ���������Ă����q�́A�����̉ߒ��� �e�N�j�b�N����蒼���K�v���Ȃ��A���܂�Ă���܂łƂ�������ꂽ ���Ԃ̒��Ń��@�C�I�����Z�p������������̂ɒf�R�L���ł��B���߂���ǂ� �搶�ɏo����Ƃ������Ƃ͉^���ǂ������ƌ�����ł��傤�B �@�R����P�T�܂ł̂P�Q�N�Ƃ����N���E�E�E�B����Ƃ͂��݂��ݎ��Ԃ� �|������̂��Ǝ������Ă��܂��B �@���@�C�I�����́A��l���g���T�C�Y�̂P�U���̂P�T�C�Y�i��������24�p!!�j ���瑶�݂��邽�߁A�������q�������ɂ҂�����̃T�C�Y�̊y��ŏK�����Ƃ� �ł��܂��B �@�t���[�g�Ȃǂ��AU���`�̏A�w�O�̎q���p�̂��̂����݂���悤�ł����A �w�ǂ̊y��ɂ��ẮA��l���g���T�C�Y�ŏK���n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B ���̂����ł��傤���A���@�C�I�����t�҂̊����N��͋����������A�P�T�� ����P�U�Ƃ����Ă��܂��B�i�ܘ_�A�����Ƃ����Ƒ��n�Ȏq����R���܂���!!�j �@���{���y�R���N�[���̎Q���N������@�C�I�������傾���͂P�T�Έȏ�� �ݒ肳��Ă���̂����̂��߂ł��傤�B �@�Y���̎́A�Q�E�R���烔�@�C�I�������n�߂āA�P�O,�O�O�O���Ԉȏ�� ���K���d�˂Ă����q�������A�P�O�l������ƂƂ���������ɒ��킷��̂ł�����A �{���ɑ�ςȊ֖�ł��B �@�����p��^�|�̔������A�����A���y���ȂǁA����܂ŎĂ������烁�\�[�h�� ���y�ɑ����M���A�S�Ă��R���̑ΏۂɂȂ��A�t�B�M���A�X�P�[�g��̑����Z�� ���l�A���̏�̂P���ŐR�������̂ł�����A���O�ȏ����͖ܘ_�̂��ƁA ���_�͂�痂������K�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�����g�̌o������A�c��������̋���̑��������Ă��炵�����i�搶�ł����A ��b���d���������b�X�������A���k���Y���E�Y��ɓ��ꂽ���A�Ƌ��Ă���������� ������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@���@�C�I���j�X�g�Ƃ��Ċ���Ȃ�����A����҂Ƃ��Ă̂������̎g����M�� ����Ă����P�O���N�O�����������������܂��B �@�搶�Ɛ��k���ςݏグ�Ă����P�Q�N�Ƃ��������������Ԃ̒~�ς��A�ǂ����ʂ� ���т��邱�Ƃ��ł����͖̂{���Ɋ�������Ƃł��B �@�x����͓����ݏZ�Ƃ������ƂŁA�\���C���̌��݂ƈȑO�̍u�t�`�[���ŁA���ȃs�A�m �E�\���t�F�[�W���̃��b�X����ςݏd�˂Ă��܂����B�܂��̂������g�ɕt�������ƁA ���y�̃��b�X������u���Ă����̂ł��I �@���ꂩ��̂R�N�ԁA�Y��̋����w�̃��b�X�������T���A�S������W�܂��Ă��� ���s�����Ɛ�����������������̒��ŁA���Ă�͂�傫���傫���L�������Ăق����� ����Ă��܂��B �@��������Q�n�܂Ń��b�X���ɒʂ��ė��Ă���Ă���撣�艮�̂x����̍���̊���� ���҂��Ă��܂��I �@�x����A���i�搶�A�Y�����i���߂łƂ��������܂��I �@
- 11��4���i�y�j���K���Ԃ̍����\�͂̍��ɒ���?!
�@�P�O���P�T(��) ��R�P��Q�n���s�A�m�R���N�[���{�I���J�Â���܂����B �@���N����R�����̐搶������ς��A�V�����̐��ł̌Q�n���s�A�m�R���N�[���A �\���C������Q�����G���g���[���܂����B �@���w�R�E�S�N���̕��ŗD�G�܂���܂����͖̂ؑ��K��i����܍��ۃA�J�f�~�[ �������R�N�j�B���w���̕��ł́A��������N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�������P�N�j�� �������D�G�܂���܂��܂����B�Q�l�����Ă̎�܁A���߂łƂ��������܂��I �@�ؑ�����͏��w�P�N���Ń\���C���ɓ����A�Q�n���s�A�m�R���N�[���̗\�I��˔j�������A �Ƃ��������v��������Ă��F�B�̂��Љ�Ń\���C���ɁB���b�X���ŏK�������Ƃ����Ƃ� ������Ɨ��K����撣�艮����ŁA���y��\���������Ƃ����v���������ς������Ă��� �K��́A���������\�I�˔j�����łȂ��A�����D�G�܂���܂��܂����B���\���ɂ́A �Ђ傤�Ђ傤�Ƃ��Ă���{�l��育�Ƒ����܂𗬂��Ċ��ł����ƕ����A���̔��܂��� �G�s�\�[�h�Ƀ\���C���������邭�a�₩�ɂȂ�܂����B �@�����N�͂���܂ŁA�o�ꂵ���Q�n���s�A�m�R���N�[���̑S�ẴJ�e�S���[�ɓ��܂��� ���܂����i���w�Z�R�E�S�N���̕��D�G�܁A���w�Z�T�E�U�N���̕��ŗD�G�܁j�B �@����͒��w���̕��ɒ���B�a�������\���C�����ォ��R�c�R�c�ςݏグ�Ă������݂� ���傭��̐i�x�ɁA�G�`���[�h�ȊO�̉ۑ�Ȃ̐��������x�҂�����ƍ����Ă��ĕ��� �Ȃ邩��Ƃ������f�ŁA���N���g���C���邱�ƂɁi���N�G�`���[�h�͉ۑ�ȂɎ��グ ���܂���j�B �@�R���N�[���ɒ��킵������t�@�C�^�[�̒��ɂ́A�w�ǃR���N�[���Ȃ������j�n��� �悤�ɗ��K��������q�����������Ƃ������Ƃ��悭�����܂����A�\���C���ł́A�n�m������ �w�̌P���̋��{�ƃG�`���[�h�A�����ăo�b�n�Ȃǂ̃o���b�N�Ȃ̓R���N�[���̗L���� �ւ�炸�ӂ�Ȃ��i�߂Ă��܂��B �@�G�`���[�h�̗��K�ɂ��A�^�w�̑��x�͖ܘ_�ł����A�Ȃ�\�����鎞�ɕK�v�ȋؓ��E���� �`����������A���������Ƃ͂ł��܂���B�ǂ�ȉ��ł��o����e�N�j�b�N��g�ɕt���邽�߂ɁA �ڐ�̂��Ƃ�ǂ������łȂ��A�����X�p���ň�ĂĂ������Ƃ͊̐S�ł��B �@�����N�͍��ăs�e�B�i�E�s�A�m�R���y�e�B�V����D���n���{�I�ł��D�G�܂���܂��܂����B ��b���ɁA���ꂩ����撣���Ă����Ăق����Ǝv���܂��B �@�t�����_�B����w�A���_�[�X�E�G���N�\���������A�ꗬ�ƒ��ꗬ�̈Ⴂ������ ����������܂��B �@�����Ώۂ́A���E�I�ȉ��y�Ƃ𐔑����y�o���Ă���x�������|�p��w�̃��@�C�I�����Ȃ� �w���ł��B �@�x�������|��͓��w���邾���ł�����ւȑ�w�ł�����A�w���S�����ꗬ�ƌ����܂����A ���̒��ł��ꗬ�ƒ��ꗬ�̍����o�Ă���̂́A���܂���̍˔\���A����Ƃ��ςݏd�˂� �w�͂��A������𖾂��邽�߂Ɏ��̂悤�Ȍ������s���܂����B �@���@�C�I�����Ȃ̋����ɁA�@�������E�g�b�v�N���X�̃��@�C�I���j�X�g�ɂȂ邱�Ƃ� �m���Ȑ��k�A�A�D�G������ǂ����E�Ŋ�����ł͂Ȃ����k�A�B�����R�[�X�ɐi�ސ��k�A �����ꂼ��P�O�l���I�o���Ă��炢���K���Ԃ����܂����B �@���ʂ́A�P�W�ɂȂ�܂ł̗��K���Ԃ̍��v�����ꂼ�� �@�V�S�P�O���ԁA�A�T�R�O�P���ԁA�B�R�S�Q�O���ԁ@�ŁA ���K���Ԃ̍������̂܂ܔ\�͂̍�?!�ɒ������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B �@�S�����h�C�c�ō��̉���ɍ��i�����˔\����w���ł����A���̒��ł����K���Ԃ̍��� �\�͂̍��Ɍq�����Ă���Ƃ�����ł��B �@�ނ�̒��ɂ͔�r�I���Ȃ����K���Ԃō����\�͂��l�������A������V�˂͂��Ȃ����� �Ƃ������Ƃł��B �@�l���D�ꂽ�\�͂邽�߂ɂ͐l��葽���̗��K��ςނ����Ȃ��Ƃ����������ʂł��B �@�G���N�\�������́A�_���X�E�e�j�X�E���w�E�`�F�X�ȂǑΏۂ�ς��ē��l�̌������s�� �܂������A�\�͂̍��͗��K���Ԃ̍��Ő����ł��������ł��B �@�p���I�y�����o���G�̓`���I�G�g���[���A�m�G���E�|���g���̖��~�e�L�E�N�h�[���A ���e�����E�I�ȃ_���T�[�Ƃ͂����A�p���I�y�����o���G�w�Z�̕��ی�̎��ԂƓy�E���ɂ́A ����ŕ��e�̎w���̉����b�X�����Ă����ƌ����܂����i�ܘ_�A��փp���I�y������ �o�����[�i�ɂȂ�܂����j�A�C�`���[�͏��w�R�N���̎�����A�ߌ�R������Q��܂ł̎��ԁA ���e���t������Ŗ싅�̗��K�����Ă����ƌ����܂��B �@���܂�Ȃ���̓V�˂͂��Ȃ��̂ł��B �@�ǂ����F����A�������Ԃ����ɔz�����A������V�˂Ɉ�ĂĂ����ĉ������B
- 10��7���i�y�j���t�̍����͊ӏ܂ł��I
�@�H����̐��X������̉��A�H���ɐ�����Ȃ���^����Ŋ���F����̎p���A ���K�ł����܂������Ă������炩��z������A���܂����v�������ł��B �@�|�p�̏H�A�����S���̃\���C���`�[���́A�R���N�[���ő��X�g�͂��Ă��āA ����̏H�Ɍ������ă��X�g�X�p�[�g���ɓ���܂����B���k�̊F����͖ڕW�Ɍ������� ���X�w�͂��d�˂Ă��܂��B �@��ʂɁg�|�p�̏H�h�ƌ����܂����A���[���b�p�ł͖�O�ł̊������I���H���炪�A �{�i�I�Ȍ���̃V�[�Y���̓����ł��B �@��[��������������̂Ȃ���Ȃ̂��A����Ƃ��Z���Ăɖ�O�œ��𗁂т�K�v���� �����������Ȃ̂��A�����ł����[���b�p�̉Ẵz�[���͉��ڂ����Ȗڂł��B�������A �V�[�Y���ɓ˓�����ƈ�ς��A�ǂ̃z�[�������͓I�ȃv���O�����ł����ς��ɂȂ�܂��B �@����̐搶�����A�ߔN�A���𑵂��Č����Ă������Ƃ��ӂƎv���o���܂����B�ߍ��� ���y��w���̓A���o�C�g�ŖZ�����A�R���T�[�g��I�y���ɍs���Ȃ��̂ł���A�����Ȃ��� �������ݏo���Ȃ��̂ɂˁA�ƌ����Ă����̂��B���̎��͂����Ǝ���̗���Ȃ̂ˁA�� �C�ɂ����߂Ȃ������̂ł����A���₢��Ⴄ�A�S��������������ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ� �m�����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B �@�R���T�[�g�ɍs���ƁA�K���ƌ����Ă����قǑ�������̂́A�����p���Y�啍�����Z���B �@�ۑ�����Ȃ����߂Ɉ�������Ԃ����K���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ނ�ł����A�{���ɂ悭 �R���T�[�g���ɏo�|���܂��B�C�O����̒����ȉ��t�Ƃ̃��T�C�^���Ȃǂł͉��Ȃ� ���Ƃ͂Ȃ����A�Y��̐搶�̃��T�C�^���A��y�⓯�����̃��T�C�^����R���T�[�g�A ���������o�ꂷ��R���N�[���Ȃǂɂ��ǂ�ǂ�o�����A�Ȃɂ�����Ɛw����Ă���l�q�� �s�ςł��B �@�R���T�[�g�ɍs���A�Ƃ�������K�����ƒ�̒��Ɍ��X���������Ƃ��v���ł��傤�B �����������特�y�D���ȉƑ��ɘA����ăR���T�[�g�ɍs���y���݂�m��A���ꂪ������ �ꕔ�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B�R���T�[�g�ɍs�����Ƃ����シ��f�G�Ȑ搶�Ƃ̏o��� �K���������̂�����A�Ƃ��z�����Ă��܂��B �@������ɂ��Ă��A���ꂪ�ނ�̉��y�̌�����ƂȂ��Ă���̂͊m���ł��B �@�����l�������������̖̂������ۂɖ��������A��Ƃ���R�̔��������̂�������A �����Ƃ��{��ǂ܂����Ă悢��i������Ȃ��̂Ɠ��l�A���t�̍����͊ӏ܂ł��B �@����DVD��CD�����l�ȏ�A�ꏊ��I���ӏ܂ł���悤�ɂȂ�܂����B��B�̌|�p�� �傢�Ɍ������A�����̖L���Ȏq�������i�ܘ_��l���j�ɁA�z�����Ă��炢�����Ɗ肤 ����ł��B
- 9��16���i�y�j���쑾�Y�搶�ECD�w�ʊy�̋��x�����[�X
�@���̉āA���쑾�Y�搶���A���{�̋Ȃ�CD�������[�X�����̂ł��Љ�܂��傤�B�肵�āw�ʊy�̋��x�B �@���{�̋Ȃ̌ÓT�̂悤�ȁs���Z���t��s�I���X�t�Ȃǂ̍�i����A����搶���V�쏉������ �s�r�r���o�̃h�h���p�t�A�s���̎g�ҁt�A�X�ɂ͕\��ƂȂ��Ă�����{�̋Ȃ̖���s�ʊy�̋��t�Ȃ� �S�P�V�Ȃ����^����Ă��܂��B �@���̒��ł��������E�߂Ȃ̂́ACD�̃����[�X�ɐ旧���Đ��E������e���ĉ����������яG�Y�搶 �i�s���t���t��s�܂����ȏH�t�̍�Ȏҁj�̑�\��s�ʊy�̋��t�ƁA���{��ɂ����{�I�y���̑n���� �ꐶ����������{�I�y������㑍�ēŁA���s���܂�̑�ꊰ�搶�ďC�ɂ��A�D�ꌾ�t�̂��̈����� ���m���[�O���̋ȁs��Ƃ̕���t�ł��B �@���яG�Y�搶�̎P���̂��j���Ŋ���搶�����́s�ʊy�̋��t���̂��A���ѐ搶�����ł����������悤�ł����A �c�O�Ȃ��ƂɁA����CD�̃����[�X�Ǝ����قړ��������A���{�̋Ȃ��x���Ă���ꂽ���̂Q�勐������������A ���������ĒǓ���CD�ƂȂ�܂����B �@������ɂ͂���܂ł̂�����Ɋ��Ӑ\���グ�A�S��育���������F�肢�����܂��B �@������������܂�����A�������������B �@CD�̓\���C���Ŏ戵���Ă��܂��B
- 9��9���i�y�j�v���E�s�A�j�X�g������Ŗ��키�����̑̌��Ƃ�
�@�w�l�G���w�ƒ���x�̂X�����̃e�[�}�́g�y��������h�B �@���@�C�I�����̖���X�g���f�B���@���E�X�A�s�A�m�̃X�^�C���E�F�C�A ���E�Ɍւ���{�̃t���[�g���[�J�[�����t���[�g���쏊�̏������̃t���[�g�A �m��l���m�镟�䌧�̐R�n�[�v�ȂǁA����ߒ�����j�ɂ��Ă̋L�q�� �������ʐ^���ڂŁA�y��D���ɂ͊���Ȃ����e�ł��B �@���y�̊y���ݕ��́A���t�A�ӏ܁A�����Ċy��̃R���N�V�������A�l�X�ł��B �@�y��D���A�Ƃ������͊m���ɂ��炵�āA�Ö̃��@�C�I����������� �~�����Ă��܂�Ȃ��Ȃ�A�Ƌ��Ă�����ɂ���������Ƃ�����܂��B �@�L���L���P�����I�ȃt���[�g�ȂǁA�G�肽���A�~�����I�Ǝ����v���Ă��܂� �܂����̂ˁB�i�����ď���������Ƃ�����ł͂���܂���I�j �@�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ���������ǁA�������y��Ɉ͂܂�A���y�Ɉ�ꂽ�y���� ���X���߂����Ă�����X�����l�Љ��Ă��āA�������Ƃ��Ȃ����ʎd�l�� �A�j�o�[�T���[�E�X�^�C���E�F�C������ɒu���Ăɂ��₩�ɒe���Ă�����A �Q�S������v���`�i���̃t���[�g�����L���Ă��邾���łȂ��A�������� ���t���y���ނ��߂̃R���T�[�g�E�T���������Ă������ڂ��Ă��܂����B ���t�ƃR���N�V�����Ƃ����Q�̑��ʂŋ��ɂ̊y���ݕ�������Ă���������́A ���̂悤�ȉ��y�Ƃ̊ւ����A�y���ݕ����ǂ����̂ł��B �@�w�ƒ���x�̓����ɍ�N���؏܂Ɩ{����܂��_�u����܂����w���I�Ɖ����x�� ��ҁA���c������̃C���^�r���[���f�ڂ���Ă����̂ł��Љ�܂��傤�B �@�w���I�Ɖ����x�́A���ۃs�A�m�R���N�[���ł́A�ו��ɘj��o��l����ݒ�̕`�ʁA ���y�\���̌�b�̖L�x���ɐ����������i�ł������A��������̂͂��A���f���ƂȂ��� �R�N�ɂP�x�J�Â����l�����ۃs�A�m�R���N�[���ɁA�S�x�����^�сA���x�ɘj��\�I ����{�I�܂ł��̑S�Ẳ��t���������Ƃ����̂ł�����A�j�S��˂�����i�ɂȂ��� �̂��[���������܂��B �@���y�ɓ_����t�����ʂÂ�����͖̂����������ƁA�ƌ����Ȃ�����A���̖����Ǝc������ �܂߂ẴR���N�[���͖ʔ����A�h���}�e�B�b�N�Ȍ������ƂȂ��Ă���A�ƌ������c���B �@���ꂾ���ǂ��Ղ�ƃR���N�[���ɂ͂܂�����҂��A�v���̃s�A�j�X�g���X�e�[�W�� ���키�����̑̌��Ƃ��̍K���x�̍����́A�@���I�ȑ̌��ɋ߂��ƌ��_�Â��Ă���̂ɂ� �����ł��܂����B �@�����̒��Ŋe�R���e�X�^���g���e���Ȃ̃v���O���~���O�ɋ�J�����Əq�ׂĂ��܂����A ���̋�J���悭�킩��l�������ꂽ�f���炵���Ȗڍ\���������͈̂�ۓI�ł����B�Ȃ� �悭�m��l�䂦�̔Y�݂ƌ����܂��傤�B �@���ꂪ�����āw���I�Ɖ������y�W�x�Ƃ���CD�������[�X���Ă��܂����Ƃ����̂ł�����A �����̂���l�͐����Ă݂Ă��������B �@�����ƂƂ��Ă̎����͂���܂œǂ�ł����{�̈����o�����珬���������Ă���A �ǂ܂Ȃ��l�͏����Ȃ��Ǝv���ƒ��҂͌����Ă��܂����A����Ɠ������A�l�̉��t�� �����Ȃ��l�͐������Ȃ��Ǝv���A�Ɖ��y�Ƃɑ��ēK�m�Ȉӌ����q�ׂĂ��܂��B �@�ꗬ�̉��y�Ƃ͑��̐l�̉��t���悭�����Ă���A�l�̉��t���Ȃ��l�͐������Ȃ��A �悭�����Ȃ��l�͂悭�e���Ȃ��A��҂̂��̂悤�ȍl�����쒆�̂S�l�̃s�A�j�X�g�� ���e�����w���I�Ɖ����x�A���̃C���^�r���[�̓nj�A�܂�������p�x���炱�̖{�� �y���ނ��Ƃ��ł������ł��B �@���̐l�̉��t���l�͉��y�̈����o���������ς��ɂȂ���ɂȂ�܂���\�\�A ���c������̑f�G�ȃ��b�Z�[�W�A���������ł��I
- 8��5���i�y�j��l�����サ�܂��傤�I�q���ɕ������ɁI
�@�A��������悤�ȏ����������Ă��܂��B �@�Ă̓R���N�[���̃V�[�Y���A�s�A�m�E���@�C�I�����E���y�̊e����A �T����P�W�̐��k�����킷��M���Ă�����Ă��܂����B �@���̎��_�őS���\�I���ʉ߂��A���y�̍b�q���͂܂��܂������܂��B �@�\���C���̐��k����̒��ɂ́A�v���̉��t�Ɩڎw���Ċ撣���Ă���l�A �v���ɂȂ����͂Ȃ�����lj��y���y�����ďK���Ă���l�����܂��B �ċx�݂̊ԁA�����̖ړI�͉��ł���R���N�[���Ɍ������ė��K�ɗ��� ����p������Ǝq�������̐��̖����������܂��B �@�b�q���Ȃǂ����Ă���Ǝq���̍�����ł�����ł������Ƃ����Z�R�N�� �ĂŏI����Ă��܂��A�Ƃ����悤�Ȍ��t���悭�����܂��B �@�v���ɓ��c�ł���l�͂ق�̈ꈬ��̐l�����ŁA�ꕔ�̐l�����͑�w�� ���ƒc�ɓ����č��܂Œʂ葱�����邯��ǂ��A�w�ǂ̎q�����͍��Z�� �싅�͑��Ƃł��B����͖싅�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A�o���[�{�[���ł� �o�X�P�b�g�����l�B �@�ܘ_�A�q���̍��Ɉ�̂��Ƃɑł�����ł����Ƃ����̌��⒇�ԂƂ� �R�~���j�P�[�V�����ȂǁA��l�ɂȂ��Ă���ł͊l��������ɂȂ�o���́A ���������̂Ȃ����̂ł��傤�B �@�������A�C�Ɗ��Ԃ������Ă��܂�����́A�����ɘj���đ����邱�Ƃ� ����Ƃ����_�Ŗ{���ɖܑ̂Ȃ����Ƃł���Ǝv���̂ł��B������������ ���K���ďC������Ɗw�K�������ǂ��A���̓y��̏�ɉ��N�ɂ��j���� �������ςݏグ�Ă䂭�ƁA����N��ȏ�ɂȂ������̌���̓x������ ��������ŁA���̗ݐς̖��x�͔N�����|���Ă������Ƃł������킦�܂���B ���ꂪ���킦�Ȃ��̂ł́A����Ӗ��l���̊�т��̂ĂĂ��܂��Ă���悤�� ���̂ł��B �@���̓_���y�͑f���炵���ł��ˁi��O���X�I�j�B �@������������t�@�̏C���ɏ[���Ȏ��ԂĂ邱�ƂŋZ�p�̓A�b�v�� ���_�C�{�ɂȂ��A�����ł����܂��A�Ƃ����N��I�Ȑ��������Ȃ��B �@�t�ɉ^���ʂ�K�v�Ƃ��镪��ƈႢ�A�̗͂��Ȃ��Ȃ�N��ɂȂ��Ă� �ł��邱�Ƃ����_�ł��B �@�����̔\�͂��A�N��Ƃ����g�ɂƂ���邱�ƂȂ��J���ł��镪��� �I�\���C���̐��k�����͉^���ǂ��ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���I �@�R���N�[���┭�\��ɏo������̂́A�l�O�ł悢���t�����邽�߂̗��K�ł��B ��ł���Ă���̂Łc�A�Ƃ������̒��ɂ͔��\��ɏo�����Ȃ��������܂����A �����Ȃǂ̃X�|�[�c�ŗ��K����������悤�ɁA���ۂ̎�����ʂ��Ċw�Ԃ��Ƃ� �����͂��ł��B �@�������ŗ��K���������Ȃ����͂���܂���B���������邱�ƂŃL���b�`�{�[���� �s�b�`���O�A�o�b�e�B���O�Ȃǂ̕������K�����ł͓����Ȃ������̗���̒��ŁA �R�c��^�C�~���O��͂�A�����̑���Ȃ��Ƃ����m�����肷��ǂ��@��� �Ȃ邩��ł��傤�B �@�l�O�Œp���������߂ɏK���Ă���̂���Ȃ��A�Ƃ������ӌ�������Ǝv���܂����A �p�����������Ď����ɏo�Ȃ��Ɩ싅�̘r�O�����サ�Ȃ����Ƃ͒N�̖ڂɂ����炩�ł��I �@�p�������Ȃ�āA��l�ɂȂ�����Ȃ��Ȃ��o���ł��邱�Ƃł͂���܂��A ��O���N���A���Ȍ���̂��߂ɂ����ň�x㵒p�S���̂ĂĂ݂�̂͂������ł��傤���H �@�\���C���̑�l�̐��k����̒��ɂ́A�U�O���߂��Ďn�߂����y�̃��T�C�^���� �W�O�ŊJ�Â�������A����R���T�[�g����悵�ďo�����Ă������������R���܂��B �@���シ��͎̂q�����������ɔC���Ă͂����Ȃ��I �@��l���������݂�ڎw���Ăǂ�ǂ��B���悤�ł͂���܂���!�@
- 7��8���i�y�j�u�傫�イ�Ȃ�����ǂ����Ă�����Ȃ��v�Ƃ�������
�@�����������狳���Ă������k����B�����w���⍂�Z���ƂȂ�A�ȒP�ɂ� �ł��Ȃ��������Ƃ��X���b�Ƃł���悤�ɂȂ�̂�����̂͊��������̂ł��B �@�Z�p�I�Ȃ��Ƃ͖ܘ_�Ȃ̂ł����A���_�I�ɑ�l�ɂȂ��Ă���l�q������̂� ��������Ƃł��B�搶�ɑ��ĕs�啅���A���R����A���ߑ������A �i���ߑ����������̂͂������̕����I�Ƃ����̂͋�����搶���̌��I�j�̘A�� �������q���A�f���A�䖝�����A��ꂽ��������Ȃ��A���N�����Ɏd�オ��̂� ���Ƃ��s�v�c�Ŗ����ł��B �@���\��Ɍ����Ă̋l�߂̎����ɁA�ނ�̗��K�ɕt�������Ă���ƁA����܂ł� ���N�ɘj��C�Ƃ��A�ނ�̐��_���̌���ɑ傢�ɖ𗧂��Ă���̂��������ɂ� �����܂���B �@�s�啅�ꂽ���ȂǁA�܂�ŐS���������Ƒ��ɑ���ԓx�i�ǂ����悤���Ȃ��I�̈Ӂj �̂悤�������q���A�ڏ�̐l�ɑ���L�`���Ƃ����h��Ȃǂ��g����悤�ɂȂ�A ���̐����̗����ɋ����܂��B �@�ςݏグ�Ă������Ƃ͕K���`�ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ�ނ炩����X�������� ���܂��B �@���������Đ��܂ꂽ���_�������Ă����Ə������Ă��܂��܂��B����ꂽ���Ƃ� �����ł��銨�̗ǂ���A���܂�������≹����������ǂ������������c���� ���X���܂����A�[���ȌP�����{���Ȃ��܂ܑ傫���Ȃ�Ə��w�R�N�����炢�ŕ��ʂ� �\�͂ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@��l���������Ă����Ȃ��A���邢�͔��ɉ��̔����������Ȃ��ȂǁA���b�X�� ��u�ɉ��炩�̎x�Ⴊ����q���A�T���炢�Ńs�V�b�ƍ����Ă�����悤�ɂȂ� �܂����i�����悤�ɂȂ�ƁA����܂ł̎�u���e��S�Ĕc�����Ă���̂��m�F �ł��邩�琦�����̂ł��I�j�A�\��̏��Ȃ��q�����X�ɘb���n�߂���A�Ί�������� �悤�ɂȂ�܂��B�������̂��ƁA�Ⴆ�A�y����ǂނƂ����̕������������邱�Ƃ� �ُ�Ɍ����q�́A���N�����Ă��邤���ɁA������ˑR�ɂł���悤�ɂȂ�A���̏� ��肾�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƁA�����Ȏq���ł������������悤�ŁA���� ���̂قǒ��������ʂ��������肷��͖̂ʔ������ۂł��B �@���b�X������̂���������y�����Đ��k�����͒ʂ��Ă��Ă���Ă���� �v���̂ł����A�������C�����邽�߂ɂ͊y���������ł͍ς݂܂���B�X�e�b�v�� ����Ă����x�ɂł��Ȃ��ӏ��͂ǂ����Ă��������ŁA���ł��ȑO������悤�� �X���[�Y�ɂ͉^�Ȃ����̂ł��B �@�ł�������������i��l�Ȃ�Ύn�߂�������j�ł��Ȃ������ł���悤�ɂ��Ă��� �o����ςނ��ƂŁA�������ł������̊K�i������Ă������Ƃ��ł��܂��B �@�����ȒB�����̊l���͂ƂĂ��d�v�ł��B���̏����ȒB�����̐ςݏd�˂ɂ��A �C�Â������ɂ͗l�X�Ȃ��Ƃ��ł���l�ɐ������Ă��܂��B�����ȒB�������l������ ���߂ɑ召�̉䖝������o����ς݁A���߂Ȃ��S���炿�܂��B �@�ł�����n�߂ɏq�ׂ��悤�ȁA�䖝�͂ƒ��߂Ȃ��S���������A�l�i���D�ꂽ�l�Ԃ� ���R�ɐ������Ă����Ƃ�����ł��B �@���\��ł͂ǂ�Ȃɏ������q�ɂ����̎��̏�Ԃ�����w�L�т����d�オ��� ���߂܂��B�R�Ύ��ł�����𗝉����K���B�����Ă���܂��B�y������������Ȃ��A ���̃X�e�b�v��ł��邩��\���C���̐��k�����́A��{���ʂ��Ă��� �̂ł��B �@�ߍ��w�������������q���w����ł����̐��͈����Ȃ������x�ɁA�������j�̐l�i�`���� �e����^�����l�X�Ȑl�X�̊i�����ڂ��Ă��܂����B���̒��Œ��҂̓���̌��t�A �u�Ȃ�ڂ��삿���₩�āA�傫�イ�Ȃ�����ǂ����Ă�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��A �@���̒��ɂ͂��܂��̂�Łv �������Ȃ��Ǝv���܂����B �@���V���l�Ɋ�������A���X���X�Ɛl�������ł���ꂽ��N�X�R�̍������q����B ���̍������Ȃ����t�͗��ɃV���L�b�Ǝ��ꂪ�ǂ��B �@�ł��z���g�ɂ��̌��t�A�g�ɟ��݂܂��B���Ƃ����������Ȃ��A�����t���[�Y����Ȃ��ł����B �@�\���C���̐��k����A�s�A�m�̊���Е��N��K�N���V�b�N�s�A�m�R���N�[���ő�R�ʓ��܁A ���y����ނ����a�����Í��Z���̂��߂̉̋ȃR���N�[���œ��I���܂����B �@���т��d�˂Ă���\���C���s�A�m�`�[���A���@�C�I�����`�[���ɉ����A���y�`�[�����n���ł��I
- 6��3���i�y�j�Y�����S�l�ɂ��₩�ȉ��t��
�@��^�A�x���̂T���S���i�j�A�\���C���QF�z�[���ɂ�����Quartetto�`A�` (�N�����e�b�g �G�[�X)��P��R���T�[�g���J�Â���܂����B �@�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z(�Y��)�Q�N���S�l�ɂ�鎩���� �R���T�[�g�ł������A�e�l�̃\������A�S��E�W��̘A�e����Ɛ����R�� �v���O�����ŁA�P�U�̎Ⴋ�s�A�j�X�g�̗������̈ӗ~�Ə�M���Ђ��Ђ��� �������}�`�l�����ł����B �@��悩��R���T�[�g�����܂ł̊��ԁA���̎��g�ݕ����ԋ߂Ō��Ă��� �������̂́A�Y�����͂Ƃɂ����悭���K����Ƃ������Ƃł����B �@�\���̋Ȃ̓R���N�[����R���T�[�g�i���ɂ͊��Ƀ\�����T�C�^���f�r���[ �ς݂̐l�����܂����I�j�A�����Ȃǂʼn��t���邽�ߓ��O�ɗ��K����͓̂��R �ł��B �@�A�e�ƂȂ�ƁA�����\������ɕ肪���ȃs�A�m�t�҂́A�A���T���u�� ���邱�Ǝ��̂ɍK�������o���A���t�̊����x�������A���킹�邱�Ƃ����� �������Ă��܂������B �@�������ނ�́A���̃R���T�[�g�Ɍ����āA���P���ɘj�薈���A���T���u���� ���K�𑱂�����A�A�x���Ƃ������Ƃ�����A�O�����肵�āA���h��Ԃŗ��K ���Ă��܂����B �@�A�e�𒆐S�ɉ��t���钘���ȃs�A�j�X�g�̂Ƃ���ɂS�l�Ń��b�X���𐔉� �ɍs������A���h���A�t�@�≹�y�\���ɂ��Ē��X���~�A���݂����炸 �ӌ����o����������ƁA���������̈ӎu�ōs������p�ɗ����������o���܂����B �@���ꂼ��ɉ��y�ɑ��Ď�̐��������Ă���̂ŁA�Η�������Z�������� ���Ȃ���A���̓I�ȉ��y���o���オ���Ă����ߒ��ɂْ͋����Ɣ��͂����� ���܂����B �@�u���{�N���V�b�N���y�R���N�[�����w�Z���q�P�ʁv�̐ΐ�ށX������A �u�ʂ̍��������܃s�m�R���N�[�����w�������P�ʁv�̊�䈟�炳��A �u�S���{�w�����y�R���N�[�����Z���̕���������܁v�̊���Е��N�A �u�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[��in Asia�A�W�A����܁v�̒|����������A �e�X�����ɗ��h�ȃR���N�[���������S�l�A���i����̗��K�ʂ̎����Ȃ̂��A ���q�R���͔������������K�O���B���̗̑͂Ɋ��S������ł����B �i��P���͔��M�őO���_�E���I�j �@�t�H�[����ȁA�g�ȁs�h���[�t�����炵���R�P�e�B�b�V���ȉ��ŕ\���ł��� �������ƁA���[�[���u���b�g��ȁs���{�̉̂ɂ��t�@���^�W�[�t�ɂ����ẮA �W��A�e�Ƃ����傪����ȕҐ��̒��ŁA�悭�m��ꂽ���{�̉̂ł���q�����炳����r �q�l�ӂ̉́r�q�ԂƂ�ځr���A��_���Ƒ@�ׂ���D������A�W���Y�̃��Y���ɏ���� ���t�������ƂɊ������o���܂����B �@�����������{�̉̂��僁���f�B����������������ł��傤���A����I�ȉ��̌q����� �S�̉��ꂩ��h���Ԃ�ꂽ�v�������܂����B �@���q�l���܂���ł���������炵�āA��҂̉��t��S����y����ł��������Ă��� �l�q�ł����B �@�A�E�V�����B�b�c���琶�҂����w��Ɩ��x�̒��҂ŁA���_�Ȉ�E�S���w�҂� �r�N�g���E�t�����N���́A��|�p�͐l�̍����~���A������͂�^������̂�� �ƌ����Ă��܂��B�ǂ����y�������ƂŁA�S�邽��v������E�p�ł����Ƃ��A �������G�����āA�l���𗧂Ē����E�C���������Ƃ������b���悭�������̂ł��B �@������������b�܂ꂽ���̒��ň炿�A�F�X�ȑf���炵���`�����X��^�����Ă��� �˔\����s�A�j�X�g�̗��������A�l�X���K���ɂ��A�l�X�Ɋ��͂�^����G�l���M�[�� �X�s���b�g���������A�^�̉��y�Ƃɐ������Ă������Ƃ�����Ă�݂܂���B �@�R���T�[�g��MC�̒��ŁA���˂Ɏ��̃R���T�[�g�ɂ��ė\�������Ă��܂������A �����܂����̋@�����܂�����A����A�F�l�������Œ����ɂ��炵�Ă��������B �@�����āA���ɐG��鉹�y��t�ł鉉�t�Ƃɋ߂Â��Ă��邩�ǂ����A�ǂ����݂� �����Ă��������B�@
- 5��6���i�y�j�҈䂢�q����̍u����
�@�Ӗڂ̃s�A�j�X�g�҈�L�s���̂���l�A�҈䂢�q����̍u����S���Q�Q���i�y�j�A ���c�w����Ɍ��݂��ꂽ����̃X�N�G�r�A���X�K�ŊJ�Â���܂����B �@���t���[�A�i�E���T�[�Ƃ�����������������A�����₷���g�[���̐��F�Ɩ��ĂȌ����A �����ƏΊ���₳�Ȃ��A���p�����������ŁA���e���X�������ꂽ�u���ł����B �@�҈�L�s���͂Q�O�O�X�N�̃��@���E�N���C�o�[�����ۃs�A�m�R���N�[���ŗD���ȗ��A �}�X�R�~�ɂ��������グ���Ă���s�A�j�X�g�ł��B���̒҈䎁�𗧔h�ȃs�A�j�X�g�� ��Ă������Ƃ������ƂŁA�ŋ߂ł͂���l�����f�B�A�ɕp�ɂɓo�ꂵ�Ă��܂��B �@ �@�u����̃e�[�}�́w���邭�y����������߂Ȃ��x�B �@ �@������ۂɎc�����̂́A���o��Q�̑��q���a�����A���̏�����J���ė������݂Ȃ�����A ���q�̂��߂ɗǂ��Ǝv�����Ƃ�ϋɓI�Ɏ�����āA�����������̍s���͂ł����B �@�w�t���b�N�X�͎��̖ځx�Ƃ����҈䎁����Ă�W�ƂȂ����{�ɏo��A���̒��҂őS�ӂ� ������a����ɁA�����g�̎v����^�������J�Z�b�g�e�[�v�𑗂�A���̌エ����邱�Ƃ� �Ȃ����b�A�T�̑��q���s�A�j�X�g�ɂȂ肽���Ǝv�����������ƂȂ����Ƃ����A�T�C�p���� �V���b�s���O�Z���^�[�̃s�A�m�𑧎q�ɒe�����Ăق����ƌ��ɍs�����Ƃ��̘b�A�w���҂� ���n�T����ɑ��q�̃s�A�m���Ă�����ăA�h���@�C�X���������������Ƃ̎v������A �F�l�̎G���C���^�r���A�[�ɑ��q�̉��t�̘^���J�Z�b�g�e�[�v��n���Ă�������b�E�E�E���A ���̍s���͂ɂ͋�������܂��B �@�u����̃e�[�}�ɂ���悤�ɁA���邭�y�������Ȃ���l�̂��l�����ƂĂ����͓I�ŁA���� �悤�Ȃ���l�Ɉ�Ă�ꂽ��K�����낤�ȁ`�ƁA�v�킸�ɂ͂����Ȃ��悤�ȕ��ł����B �����Y��Ȑ��Ō��|���Ă����A�������D�����A���N�ŏ�i�Ȃ���l�Ȃ�ė��z�ł��B ���̏�A��Ɉꏏ�ɐ킢�A�l���A�x���A�s�����Ă����̂ł�����A���̎q�����悢�q�� �炽�Ȃ���͂���܂���B �@�������̂��Ƃq�ɏ��₷���Ƃ��낪����A�Ƌ��Ă��܂������A���q���R���N�[���� ���܂����Ƃ��ȂǁA�u��l�ɂȂ����琢�E�̃R���N�[���ɏo����Ǝv���I�v�ȂǁA������� ���Ƃ��D���Ƃ����Ƃ�����A�҈䎁�̂��C�̒��܂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B �@�Ԃ����̎�����A�䏊�d���ȂǂŖڂ𗣂����ɂ́A���ꂳ��̑��݂�m�点�邽�߂� �����̂��̂��Ă����Ƃ����K�����A�ނ̉��y�D������ނ̂ɑ傫�Ȗ�����S���Ă������� �ł��傤�B�܂��A��D���Ȃ��ꂳ��̉̂��̂�^���āA�s�A�m�ʼn���T���q�ŗV�ԂȂǁA ������ς��̍ō��̃R�~���j�P�[�V����������Ă����悤�ł��B �@�撣�����v���Z�X���������ȂǁA�ǂ��Ƃ���������Ă͖J�߂�悤�ɂ��A�����Ƃ���́A �u�����ƑO������g��ł���������Ɨǂ��Ȃ�ˁv�A�Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă�����ƌ����ڂ� ����Ƃ������b���A�挎���ł��Љ���w�w�͂̌o�ϊw�x�̃G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j�ɏ����� ������������@�ł��ˁB �@���q�����������ɁA���o��Q�҂̓s�A�j�X�g�ő听���Ȃ������߂������悢�A�Ƃ��� �A�h���@�C�X������l�������Ƃ������Ƃł��i�{���ɍ����b�ł��I�j���A�u���Ƃ����y�Ƃ� �Ȃ�Ȃ��Ă��A���ł������������A���������O��ɂȂ邩����v�A�Ǝv������ł��v�� �������Ƃ��A��������Ƃ����M�O�ƐS�̋���������l�Ȃ̂��ȁ`�A�Ɗ��S���܂��o�܂����B �@�l�Ԃ̉\���̑f���炵�����䂪�q���狳������Ƃ����Ă��āA���̃t���[�Y�ɂ������I �@����l�̐l���̗ǂ��A�l�ԓI�ȉ������A�����āg������߂Ȃ��h�ӎu�̗͂����W���A�q��Ă� �����ɂȂ������̂ł��傤�B �@���������l�̎q���Ɠ��ʂȕ�e�ɂ��V�˃s�A�j�X�g���ł����������Ƃ����������ł��� �ł��傤���A���ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��A���������̎q��Ăɖ𗧂q���g�������ς��̍u����ł����B
- 4��8���i�y�j����̃o�C�u���w�u�w�́v�̌o�ϊw�x
����o�ϊw����Ƃ��钆���q�q�c����w�����ɂ��w�u�w�́v�̌o�ϊw�x �Ƃ����{��ǂ݂܂����B �@�X�̑̌��k�ł͂Ȃ��A��ɃA�����J�Ō������ꂽ�Ȋw�I�؋��i�G�r�f���X�j�� ��Â�������I�����Ɉ���{�ł��B �@���̐l�����̕��@���ǂ��ƌ������A���̐l�������������c�A�Ƃ�����������E�p �ł���q��Ă̓��W�ƂȂ鋳�珑�ƌ����܂��傤�B �@���̖{�̒��Ɂw�q���͖J�߂Ĉ�Ă�ׂ��Ȃ̂��x�Ƃ����ڎ�������A�v�킸�ڂ� �~�܂�܂����B�����q��Đ^�Œ��ɗ��s�����̂́w�J�߂Ĉ�Ă�x�n�̖{�B������ �{�Ɋ�������Ă��A�J�߂邾���̌����Ď��邱�Ƃ̂Ȃ����ꂳ�}�����܂����B ������Ăǂ��Ȃ́H�Ƌ^��Ɏv���Ă����̂ő��U�����B���ɂ��F�X�����[�����ڂ� �������̂ŁA���Љ�܂��傤�B �@�g�����S�̍����q�͊w�͂�ӗ~�������h�ƕ����ƁA�Ȃ�����̒ʂ�Ǝv������� �����ł��傤�B�����������̌��ʂ� �g�w�͂������Ƃ����������A�����S�������Ƃ��� ���ʂ������炵�Ă���h�Ƃ������ʊW�������Ƃ������Ƃł��B���������q����J�߂�ƁA ���͂̔���Ȃ��i���V�X�g�ɂȂ邾���A�������ŁA�������������l���邢��I�Ƃ₯�ɔ[���B �@�g�J�ߕ��ɂ͕��@������h�Ƃ������ڂ������ÁX�B���X�̔\�́i���̗ǂ��Ȃǁj��J�߂�� �w�͂����Ȃ��Ȃ��A�ǂ����ʂ̎��ɂ͍˔\�����邩�炾�Ǝv���A�������ʂ̎��ɂ͍˔\�� �������炾�Ǝv���悤�ɂȂ�B���ʂ�J�߂�ƈ������т�������Ƃ��ɉR�����X���������B �ŏ�̖J�ߕ��́u�P���ԕ��ł����ˁv�ȂǂƓw�͂������e�������邱�ƁB�������邱�Ƃ� �������т�����Ă��w�͂�����Ȃ����߂��Ǝ���l����悤�ɂȂ�̂��Ƃ��B �@�g���J���͌��ʂ�����̂��h�ɂ��ẮA�N�ł���x�͍l�������Ƃ�����̂ł� �Ȃ��ł��傤���H�u�P���ԕ����I������炲�J�����������v�Ƃ����悤�ɁA �����̌��ʂɑ��Ăł͂Ȃ��A�w�K�s�ׂ��̂��̂ɑ��āA������߂����� �i���̏ꍇ�͂P���Ԍ�j�ɑ��Ă̂��J���ɂ͌��ʂ�����̂������ł��B �@�P�X�U�O�N�ォ�猻�݂��ǐՂ������Ă���L���Ȏ����w�y���[�c�t���v���O�����x�� �����m�ł����H �@�Ꮚ���̃A�t���J�n�č��l�̂R�`�S�Ύ��U�l������ɁA�C�m���ȏ�̊w�ʂ��������S���w�� �搶���P�l���āA�P��2.5���Ԃ̓ǂݏ����Ɖ̂̃��b�X�����T�ɂT���w�����A�܂��A�P�T�Ԃ� 1.5���Ԃ̉ƒ�K��i�e�ɑ��Ă̐ϋɓI�ȉ���j���Q�N�ԑ����A������������Ȃ������q�� ��r����Ƃ��������ł��B �@���̃v���O��������u�������������̂U�Ύ��_�ł�IQ��P�X�Ύ��_�ł̍��Z���Ɨ��A���邢�� �Q�V�ł̎����Ɨ���S�O�̎��̏����ȂǁA�����S�Ă������A�S�O�Ύ��_�̑ߕߗ����Ⴂ �Ƃ������ʂ������炳��܂����B�����Ă��̃O���[�v�̐l�����ɂ́A��蔲���́A�䖝����́A �Љ�A���[�_�[�V�b�v�A�n�����Ȃǂ́g������́h�ƌ�����g��F�m�\�́h���������Ƃ� �ؖ�����Ă��܂��B��������ɂ������ɓ����g��蔲���́h�������Ƃ������Ƃł��ˁB�c������ ����ׂ��I�ł��B����ɂ��Ă����̂悤�Ȏ������X�I�ɍs�����\�ł���A�����J�Ƃ������� ���̐[���Ƃ�������_���ɋ����ł��B �@�ł́A�傫���Ȃ������F�m�\�͂͐g�ɂ��Ȃ��̂��A�Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B ���������́A��̓I�Ɏq���ւ̐e�̊ւ������N�C�Y�`���ŏo�肵�Ă��܂��B �@�����������ł̌��ʓI�Ȑe�̊ւ����́H �@������悤�Ɍ��� �A���������m�F���� �B�����鎞�Ԃ����߂Ď�点�� �C�������ɂ��Č��Ă��� �@�����́A�C�̉��ɂ��Ă݂Ă���A�Ȃ̂������ł��B�@�̕�����悤�Ɍ����A�͑S�����ʂ� �����Ƃ������ƂŁA����y�Ȃ��̂قnj��ʂ������Ȃ��̂��Ƃ��B�e�̖������ďd�v�ŁA����� ���Ă��e���đ�ςȂ�ł��ˁ`�B �@�m�[�x���o�ϊw��܂̃V�J�S��w�b�N�}�������́A�u�e�������Ă��Ď��Ԃ������Ȃ���A ������o���邾�����Ȃ�����A�����I�ɏ����l�i�m��ƒ닳�t�j�Ȃǂŕ₦�悢�v�Əq�ׂ� ���āA����Ȃ�Ȃ�Ƃ�����ƗE�C���^�����܂��B �@�������A���������ӂ��ɋ���ɊS�������Ďq��Ă����悤�Ƃ��������͓��{�̗ǂ��Ƃ���Ȃ̂ŁA �ł��邾�������悭�A�l�Ԃ̈ꐶ����݂���Z���i�Ǝv����j�q��Ċ��Ԓ��A�e�̎��Ԃ��[���� �|���Ĉꐶ�����q������ĂĂ݂�̂��悢�Ǝv���܂��B �@����̃o�C�u���̂悤�ȁw�u�w�́v�̌o�ϊw�x�A���E�߂ł��I
- 3��4���i�y�j�v�̓����C�ɂȂ邫�������`��搶�̋L���^�厎����̌��ʁ`
���̓~�͊��g�̍����������̒�������l�����������悤�ł����A������ �����z���A�e�n���炨�Ԃ̕ւ肪�͂��n�߂܂����B �@�������Ȃ���Βg������S����L���Ǝv���Ȃ���ŁA�ǂ�����K�v �Ȃ̂�����ǁA��͂�t�̖K��͐S���e�݂܂��ˁB �@�ւ�Ƃ����A�Q�O�P�V�N�P�����ŗ��q�搶�Ɋւ���L���ɂ��đ�R�� ���������������܂����B���k�����ی�҂̕������łȂ��A�\���C���j���[�X�� ���点�Ă��������Ă��鐶�k����ȊO�̕�������ł��B���̃G�b�Z�C��ǂ�� �܂��o�܂����A�����撣��Ȃ��Ă͂Ǝv���܂����A�Ƃ͊F�l�̊��z�ł��B �@�����������̂́A���Z���̐��k����B��搶�́u���͂S�O�x�̔M�������Ă� ���b�X���ɍs�����B�M�����邩�烌�b�X���ɍs���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ��� ���t�ɋ������̂ł��傤�A�{�[�b�Ƃ�����Ń��b�X���ɗ��܂����B���������Ă� �w�ǔ����Ȃ��B���̏�ł͉��̌�������Ȃ������̂ł����A��ŕ�������M�������� �Ƃ̂��ƁB���b�X�����e���ǂ��ł��ꂻ�̐S�ӋC���]���܂����I�ǂ��Ǝv�������Ƃ� �ϋɓI�ɔ�������̂͑f���炵�����Ƃł��I �@�ŋ߃\���C���ł́A���E���Z���������撣���Ă��܂��B�P�����ɍs��ꂽ �厎����ł͑O�N���i���������t�����Ă���܂������A�\���t�F�[�W���A �y�T�̎����ł��P�N�Ԃ̐��ʂ�������܂����B �@�ܘ_�A���̉��t�ɂ͂܂��܂��[���ɏ��ɂȂ�]�n�͎c���Ă��܂����A �\���t�F�[�W���ނ������ɂ͒������l������̂ł����A���Ɉ�ۓI�������̂́A �������I�������A�����̕s�����Ă��镔����F�����A�ǂ������炻�̕����� ���߂��邩�^���ɍl���s�����n�߂����Ƃł��B �@�ł��Ȃ����������炩�ɂ����̂ł�����A�̂̐��k�����̒��ɂ͒��߂� ���܂��Ƃ��A�ӂĕ���Ă��܂��l�����Ȃ���ł͂Ȃ������̂ł����A����厎����� ���킵���l�����́A������A�O�����Ȏp����������A�X�Ƀp���[�A�b�v���Ď��g�� �n�߂܂����B �@���\���C���ݐЂ̒��E�����́A�s�A�m�E���@�C�I�����E���y�ƁA��U�̈Ⴄ�l������ �o�����X�悭�ݐЂ��Ă��܂����A�ǂ̐�U�̐��k�������A����̎����Ŏ���̉ۑ�� �����邱�Ƃ��ł����l�q�ł��B �@��̓I�ɂ́A���t�̏ꍇ�A�X�P�[���E�A���y�W�I�Ȃǂ́A�ǂ̂悤�ȃp�^�[���̉��`�ł��A ���m�ɑ��x���グ�ĉ��t�o����悤�ɂ���Ƃ��A�̂̓���ȕȂ���������i����͒E�͂ɂ� �q����ŏI�I�ɂ͉��F��\���Ɍ��т��Ă����j�A���y�\���̂��߂̉��F�̍������ӎ����� �Ȃǂł��B �@����A�\���t�F�[�W���́A�͂�����ƌ��ʂ��o��̂ő�����̂��y�B �@�y�T�́A���ڕʂɋ�������i����͈ӎ��������Ă��ł���悤�ɂȂ�̂ł��܂� ���͂Ȃ��j�B�����́A���o�I�ȕ������������߂���ȖڂȂ̂ł����A�w���ɂ���� ���シ��]�n���[������܂��B���Y���E�a���E�������o���o���ɕ������ė������邱�Ƃ� ����悤�ɂ���i���Ȃ��Ƃ��Њ���Ă���ꍇ�������̂ŁA�����ЂƂ�������� �ڊo�܂����i���������邱�Ƃ�����j�B������Y���ǂ݁E�N���ǂ݂��R�c������̂ŁA �ł��Ȃ��Ƃ������O�Ɏ��グ�ă��b�X������i�����͊�Ɣ閧!?�j�B �@���Ȃ��Ƃ́A����܂ł��܂����Ă��Ȃ������A�Ƃ����l���w�ǂł��B����Ă��������� �ł���悤�ɂȂ�܂����A�ł���悤�ɂȂ�D���ɂȂ�B�v�̓����C�ɂȂ邫����������ł��B �@����̑厎����ŁA�����̋��ȕ�������������ɂȂ�A�F��ĂɃ����C�ɉ��t�����l�q�B �@�撣�钇�Ԃ�����ɂ���ƐL�ѕ�������Ă��܂��B �@�F�Ő����������Ȃ���A�O�����ɖ��邭���l�I��ڎw���Ċ撣���Ăق������̂ł��B �@ �@���N�̑厎����Ɋ��҂��Ă��܂��I
- 2��4���i�y�j�w���I�Ɖ����x�`�t�B�N�V��������̃q���g�`
�u�l�����ۃs�A�m�R���N�[�����ނɂ��Ă���炵����A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʔ����݂���������ǂ�ł݂Ă�B�v �@�Q�T�ԂقǑO�A���q����{��n����܂����B �@�^�C�g���́w���I�Ɖ����x�B �@�ŋ߂͖{����܂ƊH���܍�i���炢���������͓ǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă��āA �p�������Ȃ���^�C�g��������Җ����m��Ȃ��������B�i���������̍�ҁA �Q�O�O�S�N�̖{����܂���܂��Ă���`�I�j���\�����{�ł����A������ �ǂݐ�銴���ł͂Ȃ������̂ŁA�y���y���Ə��߂̕���ǂ�ŖT��� �u���Ă����܂����B �@���ꂩ��P�T�Ԃقǂ��Ē��؏܂����\����A����b��̖{�ɂȂ������Ƃ�����A ���q�̓ǂ�Ł`�I�U�����������Ȃ����̂ŁA��������ēǂ�ł݂邱�ƂɁB �@���͕̂ς��Ă���܂����A��͂�l�����ۃs�A�m�R���N�[�������ɏ����Ă��� �Ǝv�����i�ŁA�ݒ��R�����̓m���t�B�N�V�����ɋ߂����̂́A���҂��n�� �����A�L�����N�^�[���������蕪�ނ��ꂽ���I�ȃs�A�j�X�g�������o�ꂵ�܂��B �L�����N�^�[�ݒ�ɂ͖���`�b�N�Ō������ꂵ���������c��܂����A���̏����� �`�����Ƃ��Ă���e�[�}�ƌ��t�̑��ʂ��Ɏ^�Q���ׂ��_������܂����B �@�ǂ��s�A�j�X�g�ɂȂ邽�߂ɂ͗ǂ����������Ă��邱�Ƃ��s���A�Ƃ����̂� ���̏����̂P�̃e�[�}�ł��B��҂͉��y�ɂ͑S���f�l�̂悤�ł����A���O�� �������̂��Ƃɒ��ڂ����̂͋����ł����B�g�ǂ����������Ă���h���特�y�\���� �𗧂��ʂȉ��F��\�����o����A�ܘ_����������^�����葦����A���T���u���A �ҋȁA��Ȃ����݂ɂ��Ȃ���c�ȂǂȂǁB �@�����̒��ł��G��Ă��܂����A���y�ƂɂȂ�ꍇ�A�K�v�ƌ����Ă��邢������ �v�f������܂��B�����ԗ��K�ł���̎��A�e�X�̊y��ɓK�������̓I�����i�s�A�j�X�g�� �ꍇ�́A�w�������A�肪�傫���j�A�e�p�i���l�ł���Ƃ��i�D���ǂ��ȂǁA�l�C �s�A�j�X�g�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ƃ������Ƃł��傤�j���̐�V�I�Ȃ��́B�����āA �o�ϓI�Ȋ�ՁA�ǂ��搶�Ɏt������A�ꏏ�Ɋ撣�钇�Ԃ�����A���y���n�߂邫������ �Ȃǂ́A���̐l����芪�����ł��B �@���������̕���͂����ɂ��ďڂ������y���邱�ƂȂ��i�l�����ۃs�A�m�R���N�[���� ���҂͂����̂Ƃ���͑����Ă��ē�����O�Ƃ������Ƃ��c�j�g�ǂ����h���V�I�Ɏ����� ���邱�Ƃ��A�s�A�j�X�g�Ƃ��Ĉꋉ�������łȂ����ƌ��߂镪����ł���ƒ��҂͓��킹�� ���܂��i�ܘ_���C�o�������Ƃ̉��y�ɂ��G�ꍇ���Ō��サ�Ă����Ƃ����A���̗v�f�ɂ��S�� �G��Ă��Ȃ���ł͂���܂��c�j�B �@�����ɓo�ꂷ��s�A�j�X�g�����́A���܂���ǂ����������Ă���Ƃ����ݒ�Ȃ̂ł����A �������܂��ꂽ�悤�ȗǂ����͌��X���܂�Ȃ���Ɏ����Ă��Ȃ��ƑʖڂȂ̂��Ƃ����ƁA �����Ƃ�����Ȃ��Ƃ����̂����̍l���ł��B �@�w�͂ň�ĂĂ����镔�����F�X�Ƃ���悤�Ɂg���h����Ă邱�Ƃ��ł��܂��B��R�� �f���炵�����y������A�P�����s�����Ƃŗǂ����������̂��̂ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̏����ł�����D��Ă���_�͉��y��\�����錾�t�̑��l���ł��B�Ȃ̒����A ����A���x�̕ω����A�l�X�ȏ�i��F�ʁA�����ăC���[�W����g���Đ������Ă��� ������ɂ��Ӗڂ��܂��B �@�Ȃ������̒��ŃC���[�W���鎞�ɕK�v�Ȃ̂́A�܂����t�ł��B���y�����t�ɒu�������� ���ƂŋȂ̐��i���͂����肵�\�������ʂɂȂ�܂��B���̋Ȃ�\������̂ɂ���Ȍ��t�� ����̂ˁ`�A�Ɗ��S������ł��B���t�̖��ɗ����t�̕�ɂƂ����܂��傤�B �@�\�z�P�Q�N�A��ނP�P�N�̔N�����|�������グ���s�A�m�R���N�[���h�L�������g�t�B�N�V�����A �������t�̃q���g���~�������ɂ��E�߂̂P���ł��B
- 1��7���i�y�j��Ղ̐l�E���q�搶
�@�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �@�t���v�킹��g���Ȍ��U�̒��A�P�����������̏o���q�߂��K��̗ǂ��̂͂��߂� �Ȃ�܂����B �@��N�P�Q���X���i���j�A�����C�^���A�̋Ȍ�����̗��ŁA�v�����X�s�[�M�� �̋Ȃɂ��ă��N�`���[���s���Ƃ������ƂŁA���߂ĎQ�����Ă݂܂����B �@�����C�^���A�̋Ȍ�����́A���q�搶�������グ��������ł��B���{�ɂ����� �C�^���A�̋Ȍ����̑�Ƃł���A�C�^���A���{��������̌��т�F�߂��C�^���A �哝�̂��� �g�C�^���A���a���A�т̐��R�������_�g�[���M�́h ����M����Ă�����B �Y��̋����ł��炵�����A������w�@�ŃC�^���A�ÓT�̋Ȍ����̎��ƂŎt�����܂����B �v�X�̍ĉ�ł����B��搶�͌�W�O�B �@����A�ꏏ�ɂ��H�������Ȃ����搶������Ă������������e�����܂�ɏՌ��I�� ���������̂ŁA�����ɋL�������Ǝv���܂��B �@�搶���W�O�܂ŗ���d�˂�ꂽ�̂́A�܂��Ɋ�ՓI�Ȃ��ƂŁA���w�Z����͌Ҋ߉��� ������R�N�ԋx�w�A��w���ƌ�A�t���j�ɂ��t���E�o�Ƃ�����a�������Ă��܂��B �Ҋ߉��̌��ǂŏ��t��̐���������Ă����ɂ�������炸�A���Z����ɖ����V����Â� �s�A�m�R���N�[���ő�R�ʁA�Y���U�Ȃ��C�������N�ɖ������y�R���N�[���E���y����� �P�ʂɓ��܁B�R���N�[�����܌㉉�t�ƂƂ��ẴL�����A���X�^�[�g�������̐t���E�o�ł����B �w���܂Ŏ߂ɂS�O�p�̋ؓ����ؒf����A�b����ꂽ�����D���Ă��܂��܂��B �@�ׂ����������Ă������߂ɉ̂����Ƃ��������ւ����܂������A�g���[�j���O�𑱂�����A �P�N�����̐t���̖�������ăC�^���A�ɗ��w�B�{��̃x���J���g���w�т܂����B�A����A �{��d���݂̔����ƃf�B�N�V�����i����j�A����銴��\���A�����ĉ��[���������e�� �C�^���A�̋Ȃ̕���ł͐��E�ɗނ�����̂��Ȃ��قǂ̋��n���J�܂����B �@�t�����X�̍˕Q�A�s�A�j�X�g�ō�ȉƂ̃s���C�O�����W�F���j�i�p�������R���Z�����@�g���[�������A ����Y��q�������j�Ƃ̉^���I�ȏo��ɂ��搶�̍˔\�͍X�ɊJ�ԁA���q�̖��͕s���̂��̂� �Ȃ�܂����B����l�̉��t�����́A����`���ł��B �@�����ɖ������P���悤�ȏΊ�̗�搶�ł����A�������ɂ��A�����Ē�q�����ɂ��������l�Ƃ��� �m���Ă��܂��B�H���̊Ԃ����B����̘A���ł����B �u���ł�������A������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��A�ł��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ���B �@�|���܂ł��B���ȂS�O�x�̔M�����������ă��b�X���ɍs�����B�M�����邩�� �@���b�X���ɍs���Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��B���i���̂��Ɓj���������Ȃ��Ⴞ�߂���B�v �u���̕ꂪ�ˁA�t���E�o�̌�g���[�j���O�̂��ߒ��삩�瓌���ɍs�����Č��������A����܂���� �@�t�ɚg���āA�w�t��A�t��A���x�N���オ��̂ł����A���x�܂łł����A�ہI�S�x�|��Ă����A �@���͋N���オ��˂Ȃ�ʁx���Ď莆�������Ă悱������v �@�搶�̂��������Ă�����A��̊炪�����т܂����B�������o���𓌋��ł̃��b�X���ɎԂ� ���T�A��čs���Ă��ꂽ��ł������A���鎞���M���o�āA���M�̂��߂̒��˂��Q�{�ł��A��t�� �~�߂�ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���i�ƕς�炸�Ԃ��^�]���ă��b�X���ɘA��čs���Ă���܂����B ����Ȃ��Ƃ������āA�������������Ă����b�X���͋x�݂܂���ł����B �@�����̍����_�ƌ����Ă��܂�����܂łł����A���͗�搶�̂悤�ȔS�苭�����߂Ȃ��������� �D���Ȃ̂ł��B �@�搶�̂��������Ȃ���������ċ����ʂ��ł����B�܂�ŕꂪ�����Ԃ��Ă����悤����������B �@�����Ă��炦��̂��ėL��B�����Ȃ��Ƒӂ��Ă��܂�������m���Ă���̂ŁA�s���b�Ɣw�� �L�т����ł����B �@������邩�炱���̎��B����B��搶�̈�ɏ����ł��߂Â���悤�A������������������ �v���܂��B �u���ł�������A�|���܂ł��v
- 12��3���i�y�j�w�����R����������܁^�����Y��W���j�A�E�A�J�f�~�[
�@��V�O��S���{�w�����y�R���N�[���s�A�m���卂�Z�̕��������ŁA����Е��N �i�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�P�N�j������܂���܂��܂����B �ȑO�A���̗��ł����̃R���N�[���ɂ��Ď��グ�����Ƃ�����܂����A���{���� �ł͍ł����j���Â����Ђ���w���R���N�[���ł��B���w�Z�̕��̗\�I���ɍs���Ă��A �\�I�̑O�ɏ��ސR��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����炢�o��҂̃��x���������A�\�I�� �G���g���[����̂ɐ搶�̌������`�F�b�N�������Ă���̂��z���ł��܂��B ����N������܂ʼn��G���g���[����߁i���R�͖{�l�̖��_�̂��߂ɖ������Ȃ��� �����܂����c�j�A������ŏ���܂���܂��邱�Ƃ��ł��܂����i�ǂ������ł��ˁI�j�B �w���y�̗F�P�Q�����x�Ɂw�����Y��W���j�A�E�A�J�f�~�[�x�V�݂ɂ������Ă� �C���^�r���[�L�����A�J���[�y�[�W�Ɍf�ڂ���܂����B ���w�P�N�����璆�w�R�N���܂ŁA�Y��Ń��b�X��������T������̊w�Z�ł��B ���N�̕�W�͐V���P���ƐV���Q����ΏۂƂ���S�y��܂߂Ē���P�O���i���Ȃ�!!�j�B �A�c���ȃs�A�m�ȋ������Z���Ƃ��A���ɂQ��A��Ȃ̃��b�X���i�e�U�O���j�\���t�F�[�W���� ���b�X�����s���܂��B�Y��̃X�y�V�����\���X�g�v���O�����ŏ��ق��Ă���C�O�̒������t�Ƃ� ���b�X������u�\�ɂ��Ă��������A�ƃC���^�r���[�̒��ŋ����������Ă��܂�����A�܂��ƂȂ� ���̃`�����X�����ł��B �@�䂭�䂭�͏�������ь^�̈琬�V�X�e����ڎw���Ƃ������ƂŁA����܂ŋ������Y�傪 ��ԓ��Ƃ��Ă����A���t�ƂƂ��Ċw���𐢊E�ɑ���o�������ɘj��T�|�[�g�܂ł������ ����Ă���悤�ł��B�i�Ⴆ���[�i�[�~���[�W�b�N�W���p���AApple music�ALINE Music�Ȃǂ� �A�g���z�M����Ȃǁc�B�j �@�t�B�M���A�X�P�[�g�ȂǁA�I�����s�b�N�I��琬�V�X�e�����m�������ʂ��o���Ă��镪��ł́A ���w���̍�����I����������h�`���ň�ӏ��ɏW�ߎw�����Ă��܂��B�l�l�����{�e�n�� �撣��̂ɔ�ׁA�D�G�Ȓ��ԂƎh����������̂͑f���炵�����Ƃł����A�I�����s�b�N���܃��x���� �I��̉��Z���g�߂Ō���ꗝ�z�����͂����肷��A�Ƃ������Ƃ��厖�ȃ|�C���g�ł��B�I�����s�b�N �琬�R�[�`����A�����`������ɓ��ꂽ�w��������A�q�����Ƃ����Z�������ʂȂ� �߂������Ƃ��ł��܂��B �@�n���̏������g�D�ł����X�̉��y�����ł��A�����ړI�ӎ������ғ��m���������ɏW�܂鎞�́A �݂��ɐ��������������A�l�X�ȗǂ����ʂ��c���Ă��܂����B �@���̂悤�ȍ��ƓI�v���W�F�N�g���Y��Ōp���I�ɍs���Ă��炦��A�n���ɂ����̗]�g���`���A ���y�ɑ����M���v�X�R������ł��傤���A���E�I�ȉ��y�Ɣy�o�ɑ傢�ɍv�����邱�Ƃł��傤�B �@�������w�̐ݗ��̘b�����サ�Ă���Ƃ������Ƃł��̂ŁA���t��̃e�N�j�b�N�����łȂ��A �\���t�F�[�W���⒮�o�P���i����̓W���j�A�A�J�f�~�[�ł��ۑ�ɑg�ݓ�����Ă���j�A���y�� �g�ݗ��čl���邽�߂̊�b�ƂȂ镶�w�Ȃǂ̑f�{�A���E�Ŋ��邽�߂ɕK�C�̐��J���̌�w�ȂǁA �I�[���}�C�e�B�ȌP����������Ă������������ƔM�]���܂��B �@�Ȃ��Ȃ特�y�Ƃ̓X�|�[�c�I��ƈႢ�A�ꐶ��������E�Ƃł��邽�߁A�Ⴓ�ƃe�N�j�b�N�� ���ʂ��o�������ł͈ꐶ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B �@�m���ȋZ�p�Ə[���ȋ��{�̃}���A�[�W�����A���y�ƂƂ��Ă̓��B�_�ƌ����܂��傤�B �@�����ď������ȑO�̋���̏[���ɂ́A����\���C���E�V�X�e����������� ���炢�����Ɗ���Ď~�݂܂���B �@�O�Ύ�����̋���ɂ��q�������̍˔\���[���Ɉ����o�����Ƃ��ł���̂́A ����܂łɂa�������\���C���o�g�̐��k�����S���ɂ��ؖ�����Ă��܂����B �˔\�̉�������o���A���C��|���A���C��������ށA���̏�œK�ȌP�����{���A �D��S�̉肪�炿�A���R�Ǝq�������͉ԊJ���Ă����܂��B �@�C���^�r���[�̒��ŁA�����É��y�w�������A���̃v���W�F�N�g�̓X�[�p�[�L�b�Y�� ���@�����ł͂Ȃ��A�l���ꂼ��ɐ����̃^�C�~���O���Ⴂ���Z���w�ŐL�т�q������̂ŁA �Y��ɓ��w�����w���������v���W�F�N�g�̑Ώۂł���A�Ƃ��q�ׂĂ��܂����B����̊j�S�� �˂����I�m�Ȍ����ł��B �@�q������ڂ𗣂����y���݂Ȃ����ĂĂ����ƁA�O���ƐL�т鎞���ɑ������܂��B��ʂ�A �l�ɂ�肻�̎����͗l�X�ł��B �@�b�͍ŏ��ɖ߂�܂����A����̓�����m�����搶���Ɉ͂܂�A�b�܂ꂽ���̒��ł��̐L�ю����� �������Ċ撣���Ă��銛��N�̔����A���ꂩ��y���݂Ɍ�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �@�\���C���̐��k�������ꏏ�Ɋ撣���Ă����܂��傤�I �@���܂��߂łƂ��������܂��I
- 11��5���i�y�j���ʂ��o���R���N�[���̓��X
��R�O��Q�n���s�A�m�R���N�[�����w���T�E�U�N�̕��ɂ����āA��������N �i����܍��ۃA�J�f�~�[�U�N�j���A�ŗD�G�܂���܂��܂����I �����N�͂S�̎��A�a�������\���C���N���X�ɓ����A��������𒆐S�Ƀ��b�X���� �J�n���܂����B �a�������\���C���̃��b�X���͊y�������ɒʂ��Ă��܂������A�N���X�̒��� ������Ă���s�A�m�E�́E���@�C�I�����̒��œ��Ƀs�A�m�ɋ��������������� ���Ƃ���A�A�w�O����s�A�m�̃��b�X�������悤�ɂȂ�܂����B �a�������\���C���N���X�͂U������̉̂�����ʼn̂��Ă�����̂ł����A���y �����łȂ��O����ɂ������S�������Ă��܂����B �����N�̓R���N�[�����������A�Q�n���s�A�m�R���N�[���͂P�E�Q�N�̕��ŏ���� �i���N���琧�x���ς��܂������A���̎��͏���܂��ō��܂ł����j��܂���ɁA ���R�E�S�N�̕��ŗD�G�܁A�S�N���̎��ɒ��킵���s�e�B�i�s�A�m�R���y�e�B�V���� �a���Œn���{�I�D�G�܂ƁA�����ɐ��ʂ��グ�Ă��܂����B ���N�W�����Y�呁���v���W�F�N�g��������ł́A�r�f�I�R����ʉ߂��A�Y�勳�� �� ���Ð搶�̃��b�X������u����@��Ɍb�܂�܂����B ���y�͖ܘ_�ł����A����X�|�[�c�ȂǑS�Ă̍˔\���J�Ԃ����邱�Ƃ��a������ �N���X�͖ړI�ɂ��Ă��āA���y�ȊO�̍˔\�琬�ɂ��m���Ɍ��ʂ��o���Ă��܂��B �����N���A�s�A�m�����ł͂Ȃ��A�e�j�X�������ɘr���グ�A����܍��ۃA�J�f�~�[�� �������p��͂ʼnp�����Q���̐��сB�ܘ_�\���C���̗͂����łȂ��A�����e�̋�����j�� �w�Z�̉e���Ȃǂ�����܂����A�c�����ɏ����̎h����^����i���炷��j���Ƃ� �����Ă���͂��{������̂͊m���Ȃ悤�ł��B �����N�̓\���t�F�[�W�����ǂ��ł��A���ɍ�Ȃ̊�b�ł���a���ɋ����������� ����l�q�B�V�т̉����Ŏn�߂����y���A�ނ̐��E�ς��L����b�ɂȂ��Ă���̂� ����������ł��B ��������R�O��Q�n���s�A�m�R���N�[�����w���P�E�Q�N�̕��ɂ����āAY���� �i����܍��ۃA�J�f�~�[�P�N�j�����I���܂����B Y������R����a�������\���C���N���X�ɓ������A�s�A�m�̃N���X�������� ���b�X�����Ă��܂��B���b�X���ŏK�������Ƃ��R�c�R�c�����ɏK�����Ă���A ���ɗǂ��q�̋��I���w�Z�P�N����Y������p�����Q�����i�A�o���G���撣���Ă��āA ���ꂩ�炪�y���݂ȏ��̎q�ł��B ��D���ȉ̂��̂����蒮�����肵�Ȃ���AY����̒��ɉ萶�������y�̉肪 �����L���ȉԂɂȂ�悤��Ɍ�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B ����A�\���C�����@�C�I�����`�[�����撣���Ă���̂ł����B ��Q�U����{�N���V�b�N���y�R���N�[�����w�Z���q�̕��E���Z���q�̕��ŁA �\���C���̐��k����Q�����S�����̏o������߂܂����B �S�����͒��w�Z�̕����P�Q���P�R���i�j�������V���t�H�j�[�q���Y�E �A�C���X�z�[���ŁA���Z�̕����A�����A���l�݂ȂƂ݂炢�z�[�����z�[���� �s���܂��B�����ςݏd�˂��͂��⊶�Ȃ��������A�W���͂̂��鉹�y�I�� ���t�����Ă��Ă���邱�Ƃ��F���Ă��܂��B ���N�����I������Ǝv������R���N�[���A�R���N�[���A�R���N�[���I�� ���X�������A�����Ƃ����Ԃɂ��ƂQ�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B ��N�̍������A�R���T�[�g���ɍs�������A�I�y���ɍs�������A����� �s�������A�Ƒ呛�����Ă����̂ł������A���N�͂��̊肢�������āA�X���A �P�O���A�P�P���A�P�Q���ƃR���T�[�g�O���̓��X�B�b��̔��c�����s�A�m���T�C�^���A �V���p���R���N�[���̔e�҃`���E�\���W���ƃ`�����E�~�����t���w���̃s�A�m�R���`�F���g�A �ߓ��L�q�搶�̃s�A�m���T�C�^���i���ɂ������ς��I�j�A�ǂ��������ꂪ�S�� �s�A�m�̃R���T�[�g�Ƃ�����悤�B �I�y���ɍs�������ȁ`�A���y�̃R���T�[�g���������ȁ`�A�ȂǂƖ������˂������ �����Ă��Ă͔���������`�`�`�I ���̏H�̓s�A�m�i�������Ǝv���܂��I �|�p�̏H�Ɋ��t�I �@
- 10��8���i�y�j�C�^���A�I�s
�@�X�^�P�P�`�X�^�P�W�A�C�^���A�ɍs���Ă��܂����B �@�܂��͑�P�̖ړI�ł���A�k�C�������w�E��������̐V��I�y���s���ِ푈�t�㉉�� �����B �@�O��̃\���C���G�b�Z�C�ł����b�������ʂ�A�����F���[�g�̓��[�c�@���g�����߂� �C�^���A�ʼn��t��������X�ŁA�C�^���A�E���[�c�@���g����ݒu����Ă��܂��B�܂��A ���ꖼ�ɂ����̖�������Ƃ���A��ȉƃU���h�i�[�C�i����܂łɂ�����͕p�ɂ� �U���h�i�[�C�̉̋Ȃ��̂��Ă��܂����I�j�̐��a�n�Ƃ������Ƃ�����A���y�ɂ����� ���X�Ȃ�ʎv������������`����Ă���X�ł����B�Ƃ����̂��A���̕ϓN���Ȃ��X�Ȃ̂ɁA ���ꂾ���������I���N�O�ɏ\��N����������C���I���A�T�C�Y�͏��������̂́A �~���m�̃X�J�����⃔�F�l�c�B�A�̃t�F�j�[�`�F���ɏ���Ƃ����Ȃ����������̔����� �Ȃ̂ł��B �@����̓����F���[�g�ɂ����郂�[�c�@���g�t�F�X�e�B�o���̈�Ƃ��Ă̏㉉�ł������A �����y�A�s�A�m�A�I�y���A�u����ȂǁA�P�T�Ԃɘj�胂�[�c�@���g�̉��y�𒆐S�Ƃ����Â��� �����F���[�g�s���̊e���ōs���Ă��܂����B���t�Ƃ����O���C�^���A�ȊO�̕��������A �F�X�Ȍ��ꂪ��ь������ېF�L���ȕ��͋C�B�z�e���̒��H�ŋ��R�ׂ荇�����t�����X�l�� ���b��������A�u����̂��߂ɂ��炵�Ă������y�w�҂�������c�A�C�^���A�ꂾ���łȂ��A �v�X�̌�w���ɂ��Ȃ�܂����B �@�s���ِ푈�t�́A�����̋����{�R�ƐV���{�R�Ƃ̐푈����������i�ŁA���{�R�̉|�{���g�i����j�� �V���{�R�̍��c�����A�����Č��̂R�l�ʼn�������}�h���K�[���I�y���ł��B�Â�����A �����ē��{��ł̏㉉�Ƃ������ƂŁA���Đl�̔������S�z�ł������A����̔���Ő������� ������܂����B �@���̌����͖k�C�������w�̒˓c�N�O�搶�i�����ŏo���j�ƃC�^���A�E���[�c�@���g����Ƃ� ���\�N�ɘj�鋭���q����ɂ������������̂ł��B �@���{�ɂ����郂�[�c�@���g�����̑��l�҂ł���C�V�V�q�搶����̏Љ������肵�߁A �˓c�搶���S�O��̍��Ƀ����F���[�g�̃��[�c�@���g��������K�˂ɂȂ��Ă��炨�悻�Q�O�N�A ���[�c�@���g����Ɩ��N�̂悤�Ɍ𗬂����������钆�A��̂悤�ɔ������U���h�i�[�C����� �I�y���㉉���ł�����A�Ƃ����˓c�搶�̖���������ꂽ��ł��B �@���[�c�@���g�́s�o�X�e�B�A���ƃo�X�e�B�G���k�t���ꏏ�ɏ㉉�����̂ł����A���̒��� �o���҂̂P�l���I�y�������̗����Ƀ����F���[�g�x�O�Ō��������������ہA �u���͎v�������A�w�͂����Ă����ƕK���������̂ł���v �Ƌ��Ă����˓c�搶�̏j�������Ɏc��܂����B �@����ɂ��Ă��Q�O�N�Ƃ��������Ό����|���Ė��������ɂ��ꂽ�Ȃ�đf���炵�����Ƃł��I ���s�����Ă����������v�́A�{���ɍK���҂ł���Ǝv���܂����B �@�C�^���A�Ō�̖�̓��F�l�c�B�A�E�t�F�j�[�`�F���ł̃I�y���ӏ܁B����܂ʼn��x���ς� ���Ƃ�����h�j�[�b�e�B�́s���̖���t�ł������A�ߑ������o���~���[�W�J���̂悤�� �d���ĕ��ŁA���y���A���[�e�B�̎���̂悤�Ȍ��Ȃɒ����ɉ��t���錴�T��`�Ƃ͐^�t�� ���R�ȕ����������Ă��āA����ɂ���ĉ��y�̕\���̕��@���ω����邱�Ƃ�������������B �@�A�f�B�[�i���̃\�v���m�A�C���[�i�E�h�����E�X�J�����A�̂����Z�����Q�Ŕ�����������A ����̍���������Ă��܂����B �@���������C�^���A�ݏZ����́A�R���s���[�^�[�Ń`�P�b�g�̍w�����ł��Ȃ��������Ƃ���A �t�F�j�[�`�F���̃`�P�b�g����͍���̏�Ȃ��������߁A���߂Ē��ɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B ���F���f�B�́s�֕P�t��s���S���b�g�t���������ꂽ�`������I�y������ŁA�����̎��̍��� �ł��L���ł��B �@�P�X�X�U�N�̕s�R�ɂ��Ђɂ��S�Ă��Ă��܂��܂������A�t�F�j�[�`�F�i�s�����j�� ���ɑ��������A�����ɍČ�����܂����B���ۂɒ����t�F�j�[�`�F�ł̃I�y���͂��̖��ɒp���Ȃ� �������ȓ��e�ł����B �@�삯���̃C�^���A�؍݂ł������A�v�̃I�y���o���ƃt�F�j�[�`�F����ł̃I�y���ӏ܂Ƃ����A �l���ő勉�̃C�x���g�̂��A�ŁA�����Ă���K���i�ł����P�T�Ԃł����I
- 9��10���i�y�j�I�y���s���ِ푈�t�C�^���A����
�@���͂��̉āA��������Ă�����N���l�̃X�g�C�b�N�ȉċx�݂��߂����܂����B ���̐��N�A���s�ɍs���Ă��Ȃ��̂ŁA���s�ɂ��������ȁ`�A�Ɗ���Ă�����A �v�����������H�A�ǂ��@������Ă��܂����B �@�v�̏�������k�C�������w�E�������ꂪ��N�̎D�y�I�y���ՂŐ���㉉���� �V��I�y���s���ِ푈�t���A�C�^���A�E�����F���[�g�̃U���h�i�[�C����ōĉ� ���邱�ƂɂȂ�A�v�̏o���ɔ������̂���`���ŃC�^���A�ɍs�����Ƃ��ł��܂��B �@�I�y���s���ِ푈�t�́A�������N�Ɏn�܂������]�˖��{�R�Ɩ����V���{�R�ɂ�� �퓬�ł���A�g���ِ푈�h�i���{�Ō�̓����j��`������i�ŁA�����{�R���فE �|�{���g�ƁA�V���{�R�Q�d�E���c�����A�����Č��̂R�l�ɂ���ĉ������� �}�h���J�[���E�I�y���ł��B �@�v�͉|�{���g���ŏo���A���{��ŏ㉉����܂��B �@���ꂪ���郍���F���[�g�̓I�[�X�g���A����C�^���A�ɓ����Ă����̒��ŁA������ �Ԃ��ނ���A���v�X�R�����z���铻�̂P�A�L���ȃu�����i�[���̋߂��Ɉʒu���܂��B �Q�[�e������Ă����C�^���A�ւ̗���Ԃ�w�C�^���A�I�s�x�̒��ŁA��]�ɖ����� �u�����i�[���z���̋L�q������܂����A���̃��[�c�@���g���C�^���A�ɗ������ہA �����F���[�g�ɗ������C�^���A�ŏ��߂ẴR���T�[�g���s�������Ƃ���A���̒n�ɂ� �C�^���A�E���[�c�@���g����̖{�����ݗ�����Ă��܂��B �@����́A�����P�T�Ԃ̑؍݂ŁA�m�ÁA�f�o�A�{�Ԃ������A�A���v�X�̘[�Ƃ��� �n���̂��߁A�~���m�̗F�l�Ɉ����A�E�B���h�[�V���b�s���O�i�C�^���A�l�̃Z���X�� �z���������c�I�j������A���p�قɍs���A�ό�����c���A���s�炵�����Ƃ��肽�����Ƃ� �����ł��Ȃ��ł��낤�Ƒz�����Ă��܂��c�j�āI �@�C�^���A�Ȃ̂ŁA�ǂ��ɍs���Ă������͔��������ł��傤���A�R�̌i�F���������͂��A ���ł��~����������ꂽ��o�`��������̂ŁA���X�ɐߓx�������čs���Ă��悤�Ǝv���܂��I �@�C�^���A�ő�̌K���_�ΔȂɂ���A�厍�l�_���k���c�B�I�̏I�̐��ƃ��B�b�g���A�[���E �f�b���E�C�^���A�[�j�����w���A�I�y�����㉉���i���͗����ł����c�j�A���F�l�c�B�A�� �P�{�I�y�����ӏ܂��A�ƕ���̂悤�ȗ��ɍs���Ă��܂��I �@���̊Ԃ̂P�T�ԁA���̃N���X�͂��x�݂����������܂��B �@�h��������Ղ荷���グ�܂�����A����������K���Ă����Ă��������ˁI�I
- 9��3���i�y�j�Y��u��������v���W�F�N�g2016 in ����v
�@�ċx�݂����������߂����ł����ł��傤���H�@�R��C�ւ̃L�����v�A ���Ƒ������Ă̂����s�ȂǁA���W���[�⃔�@�J���X���y���ޕ����������A �R���N�[���i�w���R���N�[���͉ĂɏW�����Ă���I�j�A���É��y�ՃZ�~�i�[�Ȃǂ� �����n�ōs����Ċ��Z�~�i�[��e���y��w�̉Ċ��u�K�A�X�|�[�c���撣���Ă��� �l�͑������������X�A��Z���ł��ꂼ��̗L�Ӌ`�ȉĂ��߂����ꂽ���ƂƎv���܂��B �@�W���R�P���i���j�A�ȑO���̗��ł����Љ�����Ƃ�����A�����Ȋw�ȍ�����w �@�\�������ƁA�����Y�p��w���y�w���w��������v���W�F�N�g�Q�O�P�U in����x�ɁA �\���C���̐��k����j�N�����O�̃r�f�I�R����ʉ߂��A��u���Ă��܂����B �@���̊��́A�n���ɕ�炷�q���������s�S���܂Ń��b�X���ɒʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ� �n���f�B�������ł��������A���ŏI��点�Ȃ����߂̎x�����Ƃł��B�Q�O�P�T�N ���炱��܂łɁA�a�̎R�E�l���E���E�k��B���A�e�n�Ńs�A�m�A���@�C�I�����A �`�F���̃R�[�X���J�Â���Ă��܂����B �@�c�O�Ȃ��玄�͍��b�X�����ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ������̂ł����A�Y��� �� ���� �����ɂ��A�ׂ������ʓI�ȃ��b�X���͂ƂĂ��y���������ƁA�j�N����� ����܂����B �@��u���͏��w�S�N�����璆�w�Q�N���܂ł̂V�l�A�ǂ̐��k������P�����s���͂��� �f���炵�����t�����Ă��������ł��B �@�Y�勳�����璼�ڃ��b�X�������邾���łȂ��A�D�G�Ȑ��k��������u���� ���b�X���������Ղ蒮�����Ƃ��ł��A��������u���͖����B��u���ɂƂ��Ă͂Ȃ�� �K���Ȋ��ƌ����܂��傤���I �@���搶���A�q�ǂ��ɂ�������Ղ����邭���J�ɋ����Ă�������A�s�A�m��e�����Ƃ� �v�X�D���ɂȂ����I�Ƃ͖{�l�̊��z�ł��B
- 8��6���i�y�j�t�B�M���A�X�P�[�g�R�[�`�̍u��
�@�Y���ōs��ꂽ�A�t�B�M���A�X�P�[�g�R�[�`�����M�v���̍u����ɍs���Ă��܂����B �@�������̓I�����s�b�N��_���X�g��c�^���̃R�[�`�Ƃ��ėL���ł����A�����g�� �S���{�I�茠���P�O�A�e�������т������A���삳��ł��鍲���L���A���얫�A����͎}�A ����F�����ȂǁA�����̃I�����s�b�N�I�����Ă��R�[�`�ł��B �@�����A�^�ʖځA�Ƃ�����ۂ��鍲�����ł����A���b���ɂȂ���e����ۂ��̂܂܁A ����Ȃ������Ƃ��邱�ƂȂ��c�X�ƌ���Ă��������܂����B �@ �@��ۂɎc�������b�͎��̂U�ł��B ���X�P�[�g�̗͑͂��g���̂łT���Ԕ��̗��K�����̌��E�����A�����̓R�[�`�ɂȂ�P�R���� �@�X�P�[�g�C�𗚂����܂܂��������Ƃ�����B���ł��l�̂R�`�S�{���K���Ă����B���܂� �@�y���������Ƃ͈�x���Ȃ��Ƃ����̂��ŏI�̎v�����B ���L���ȑI��̊�������J��Ԃ��J��Ԃ��b���A���z����`���邱�Ƃɂ��Ă���B �������v���O�������P�N�������Ă��ł���悤�ɂȂ�Ȃ������q���������A���������� �@���߂悤�A�ƌ��ɂ������Ƃ�����B���̌�A���̎q�͂P���������K�����Ȃ��Ȃ����B �@�������A�����ɗ��K���ĊJ���A�����ɒ��ׂ�悤�ɂȂ����B�P�X�U�S�N�̓����I�����s�b�N�� �@�o�ꂷ��܂Ő��������B�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����߂Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ� �@���̎q�ɋ�����ꂽ�B �����g�������قǏd�v������Ȃ���������A���g���̕K�v���������Đ搶�ɋ����� �@�����ɍs�����B�X�P�[�g�I��͋��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ƒf��ꂽ���A������������ �@�g���[�j���O���n�߂Ă�������B�K�i���P�O�O�i�ȏ�삯���g���[�j���O�͍Ōオ �@�����オ��悤�ȏ�Ԃ��������A�Q�T�Ԗڂ����܂ő����ď�邱�Ƃ��ł���悤�� �@�Ȃ����B�������炨�肢�����Ďn�߂��̂Ŗ����Ƃ͌����Ȃ������̂����L�c�������B �@��x�ǂ�j��ƁA�����I�ɓ�����悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�m�����B�y�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A �@�������Ƃ����S��A�����Ƃ���Ăق����B ����̎����ł���悤�ɂȂ�����A����ł悢�Ǝv��Ȃ����ƁB���E��ɂȂ��Ă� �@�I���ł͂Ȃ��B����Ɛ�ɉ�����������B�J��Ԃ��ƐV�������E������������B ���P�̃N���X���x�̎��͂łQ�̃`�[���ɕ����A�Q�`�R�T�ԌP������B �@���̃`�[�������ɈႢ�Ȃ��Ɛ搶���v�����`�[���̕������Ƃ������v������B �@�ǂ�ȏꍇ�ł����̎q�͏�肭�����Ǝv���������悢�B�x�X�g��s�����āI �@���E��̑I����琬�����R�[�`�̌��t�͂P�P�Ɋܒ~������܂��B�I��琬�� ��̗��ꂪ�ł��A���N���������Ƃ��J��Ԃ��A�����͊y�ɂȂ邱�Ƃ����낤���� ����̎҂͎v���Ƃ���ł����A�����R�[�`�͌J��Ԃ��u�y�Ȃ��Ƃ͖��������v�� ��������Ă��܂����B �@�����̗��K�͎����̌��E���ďI��点��悤�ɂ��Ă���B�����̑S�͂������� ���\�����L�������Ă����A�ƍŌ�ɏq�ׂ�ꂽ���t����ۓI�ł����B �@���E��͊y����Ȃ���ł��B �@�X�|�[�c�̃R�[�`�Ƃ�����苁���҂̗l���Ɍ�����̂́A�����������������X�� �c�����ォ��d�˂Ă���ꂽ����ɈႢ����܂���B �@�M�O�������Ĉꐶ���|���ē������߂��ς��Ɗy�����B �@��ςȂ��Ƃ͓�����O�̂��ƁB �@��������Đ����������w�т܂����B �@���߂�̂͂P���łł��邱�ƁB���߂��撣�邱�ƂŁA���������Ĉꐶ�����邱�Ƃ� �ł���B�y���Đ����������ǂ��ƍl����l�͐l���̊y���݂�������Ă���Ǝ��͎v���܂��B �@�g���߂��撣�邱�Ƃ͊y����Ȃ��h �@�撣���Ă���l�̋��ʎv�����ĉ������z�b�Ƃ����C���ɂȂ�܂����B �@�ł����������Đ����邱�Ƃ͐h����������Ȃ��B�L���L���P�����ڂƊ�Ƒ̂������A ���ʂ��o�������Ȃ������̐l�Ɋ�]�Ɩ���^���邱�Ƃ��ł���I �@�f�G�Ȑ��������Ċm�F�ł����M�d�ȍu����ł����B �@
- 7��2���i�y�j���ꂱ���A�g����h�̖���
�@�\���C���������y�����E�O���s���̍ő�C�x���g�w�\���C���R���T�[�g�x���A �U���Q�U���i���j�ɍs���܂����B �@���i�́A�Q�O��̎���肸���ƌ��C�ŁA�Q�O��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����炢�����Ă���� �������Ă��鎄�ł����A���̃\���C���R���T�[�g�̏������Ԓ��Ɋւ��ẮA�S�Ă̗͂� �z������邩�Ǝv�����A�̗͂����Ղ��A�j�������A�̏d���������܂��B�i���ہA�����ڂ� �S���ς��܂���I�j �@�������𒍂�����Ŏd�グ����`�������k����A�\���C���̐搶�ɏK�������Ƃ��A �����P�l�̗͂Ō����ɏK�����{�Ԃ��}���邱�Ƃ��ł������_�I�ɑ�l�̐��k����A�M�S�� �}�}��p�p�̋��͂̉��A�ꐶ�������K�ɗ��ł������k����c���X�A�d�グ���̌`�Ԃ� �ǂ��ł���A�W���͟���A�������̉��t���I���Ă��ꂽ���k����S���ɁA�ɂ��݂Ȃ� �����������܂��B �@���\��̑I�Ȃ�����ہA�搶���́A���݂̂��̎q�̎��͂�i�A�v���O�����̔z�� �l�����܂��B���ݏK���Ă��郌�x����菭���w�L�т����Ȃ̕��������C���o��q������A �t�ɂ��܂����Ȃ�^����Ɨ�������ł��܂��q��������A�K�����Ă���e�N�j�b�N�� ���ʼn��t�ł���Ȃ�I�Ԃ��A�l�O�ʼn��t����Ƃ����@����g���āA�K�����Ă��Ȃ��e�N�j�b�N�� �撣���Ď�ɏC�߂����悤�Ǝ��݂邩�ɂ���Ă��Ȃ͕ς���Ă��܂��B �@���b�X���Őڂ��Ă���ƈ�l��l�̐��i�͒͂߂Ă��܂�����A�ǂ̒��x�̎��͂�����A ���i�͂��̂悤������A����͂��̋Ȃ��悢�ł��낤�ƁA���t����Ȃ����܂��Ă�����ł����A ����͑�R�̐搶�����A����I�Ȃ�I�сA���̎��ɂ��v�������Ȃ���J(�I)�ƁA��т� �����炵�Ă��ꂽ�̂ł����B �@�l�͐������܂��B����͂Q�̂��Ƃł�������������Ă��炢�܂����B���ɂ͐��k���� ����������]�ꍇ���������悤�ł����A�����̐搶���A���͈ȏ�Ǝv����Ȃ��ۑ�Ƃ��� �I�т܂����B �@�ܘ_�A��Ȃ�I�q�����ɂƂ��āA�����̋Ȃ͋Z�p�I�ɔ��ɍ���ŁA���\��� �P�O�����O�ɂȂ��Ă��ׂ����p�b�Z�[�W�̈Õ����܂܂Ȃ炸�A������{���{���c�A�ȏ�ԁB �P�O���O�Ɏw���v���悤�ɓ������Õ������ڂ��Ȃ��A�Ƃ����̂́A�{�l�ɂƂ��Ă��Ȃ�� �v���b�V���[�ł��B�i���ꂪ�v���b�V���[�Ɋ����Ȃ��悤���ƍ����ł��Ȃ��̂ŁA�v���b�V���[�� ������̂͑吳���I�Ȃ̂ł����c�B�j���̂悤�ȏꍇ�A���_���w�E���A��B���邽�߂� �P�O���ԃv���O������g�݂܂��B����A�q�������̐������������̂́A�X�y�V�����v���O���� �������s�̍ہA�����L�c�����e�ɂ��������ނ��ƂȂ��A���R���邱�Ƃ��Ȃ��A�Ȃ�ƂȂ� ���������ɂ��Ă���p���������ł����B �@�ߋ��A���x�ƂȂ������悤�Ȍo�������Ă������A�U�X�������蔽�R�����藎�����肵����A ���̋ǖʂ����z���A���K�ɗ�݁A���̌��ʗǂ����t���ł��āA�F�ɖJ�߂�ꂽ�o�����ނ�� �^�t�ɕς����̂ł��傤�B �@���̂悤�ɏ����Ȕނ�̐��_�I�Ȑ����ɂ͖ڂ���������̂�����܂����B���_�I�Ȗʂ����łȂ��A ����͑S���̎��͂��A�b�v�A�Ȃ̓�x���ڂɌ����ďオ�������Ƃł������������ł��܂����B �u���\�����ǂ��R���T�[�g�̌`���ōs���̂ŁA�v���̉��t�Ƃ̂悤�ɂ��q�l�Ƀx�X�g�� �@���t�����Ă��������v �u�������l�̐l�����ς��悤�ȁA�S�̂��������A�����ĉ��y�I�ȉ��t�����Ă��������v �Ƙb���ƁA�c���ł�������Ɨ������Ă���܂��B������S�Ύ��̏�����̎q��������A �Ō�̐��k�܂ŏW���͂̐�Ȃ����͓I�ȉ��t�����Ă���܂����B �@���ꂱ���A�g����h�̖����ł��I �@�S�O�b�Ԋu�̐�ڂȂ����k�����̉��t���������悻�S���ԁA�P�l�̐��k������ �R�炷���ƂȂ����͕��䑳�Œ��������܂��B�F�����ɉ��t���Ă����̂ŁA������ԂɂȂ� ���܂��A����͂���͊y�������Ԃł��B �@���k�����͑S���v���̉��y�ƂɂȂ��ł͂���܂���B���̎q�����ɖ������ł��̐����� �w��������͉̂��̂��B�g�����ƌ��߂����Ƃ͕K��������������h�Ƃ����o�����A�����ǂ�� �ɂ�����Ă��l���̗ƂɂȂ�ƐM���Ă��邩��ł��B �@�����v�������L���ĉ�����\���C���̕ی�҂̕��X�̂����͂ɂ͂������ӂ��Ă��܂��B �ǂ�Ȃɐ��k����̂��K��@���Ă��A�ی�҂̊F�������������������ċ��͂��Ă������� ����ł��B �@�R���T�[�g��R���N�[���A�����ĎO�ɃK���K���ɑ����ׂ낤�Ɓi�{���͂����Ƃ� �����Ȃ����c�j�A���ꂩ����F����ɃG�l���M�[�𒍂�������̂���A�ƌ��S�����Ă��ꂽ �f���炵���R���T�[�g�ł����B
- 6��4���i�y�j���E�G�E�G��
�@�ŋߑ��q����Z�̕������Z�ɓ��w�������߁A���w������A���w���A���ƎQ�ρA����A �ݍZ���̉��y��X�c�A�܂��Q�������o���Ȃ��̂ɖ�L�Ə��ɑ����^�ԋ@������܂����B �@�����w�����������̏��w���ӂ́A�\�Q���A�R�A����A�Z�{�Ƃَ͈����́A �����ۂ��G���̕��͋C���c��X�ł����B�i���ł��悢�Ĕz�ɃA�����͂��̕��͋C���c���Ă���c�j �@�������ȉf��ق�Â��H���A�C���`�L���ۂ���������ׂ�X�܂͏����Ă������ȃr���� ���đւ����A���Q�҂ň��Ă����������ɂ͍����̃J�t�F���������сA���Ȃ���p���� �l���ł��B�O�ς͈ȑO�ƕς��Ȃ��������̔��p�ق��A����Ȏ���̃u���b�V���A�b�v�� �h������Ă��A��������ς��f�G�ȋ�Ԃɗl�ς�肵�܂����B �@���p�ق̊��W�����͓I�ŁA���t�A�����s���p�قł̓��l�b�T���X���\������ �{�b�e�B�`�F�b���W���|����A�ȑO����ӏ܂����������w�����O���m�̗�q�x�w������ �V���l�b�^�̏ё��x���������芬�\���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�{�b�e�B�`�F�b���W��̎ቫ�W�͋�O���̐l�C�ŁA�s���p�ق̎�����Q��蔼���� �s�ł����Ƙb��ɂȂ�܂����B�i�c�O�Ȃ��炻�̍s��ɉ����̗͂͂͂������I�j �@�������m���p�قł͂U���P�Q���܂ŃJ�����@�b�W���W���J�Â���Ă��܂��B �@�������m���p�ق̌����͂V�����̋������E���A�w���E�R���r���W�G�̍�i�Q�x�� ��Ƃ��āA�h�b�n�l�n�r�i�C�R���X�j����g���E��Y�ꗗ�\�ւ̋L�ڂ��K���h�Ɗ����� �Ȃ���A����j���[�X�ɂȂ�܂����B�܂��ɍ����{�I�b��̌������ƌ����܂��B �@�����Y��̔��p�w���̍Z�����\���N�O�ɐ�������A���������������Ƃ͑S���ʂ� �X�^�C���b�V���ȍZ�ɂɐ��܂�ς��܂����B��ʂɌ��J����Ă����Y����p�ق́A �Y��R���N�V�����̏�ݓW���͂��߁A�F�X�Ȋ��W�����͓I�ł��B���p�ٓ��ɂ� �I�[�N���̃J�t�F���Y��O�b�Y�̔��̃u�[�X������A�Y��I���W�i���̃m�[�g�Ȃǂ� ������w�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Y��́A�ӊO�ɂ��J���A���ÁA��ʖƂ������A������J���炪���ߋ����B���w�� ���Ε����Ɍ������ƁA�Â��ǂ�����������Ղ�̏����̒����L�����Ă��܂��B�ؑ��� �������������������f�G�ȃJ�t�F�A�̂��炠���ʂ�����M�̐��X�ȂǂƂ��ɁA�����݉�����A ���S������A�����������ɐ��ŁA�l�X�̐��������Â��Ă��܂��B �@�Y��͐��N�O����V�������g�݂��n�߂܂����B�n���ɏZ��ł��鏬�E���w�����Y��� �����w���o�����ċ�����g�o�����b�X���h�A���Z�𑲋Ƃ��Ȃ��Ă����͂�������Y��� �i���ł���g��ы����x�h�i���̗��ł��ȑO���グ�܂����j�A����w�ł͓�����O�� �s���Ă����g��w���J���h�̊J�n�ȂǁB �@��w���J���ɂ͗l�X�ȉ��y���N�`���[���J�Â����悤�ł�����A���ꂩ��i�w�� �ڎw���w���̕������Ƒ����A���w���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B �@���܂�m���Ă��܂��A�Y���i�Y�啍�����Z�j�͌��J�̉��t������A��N��ʂ��� �Z���O�ʼn��t����Â��Ă��܂��B �@�Y��̑�w�Ձi�������Y�Ձj�A��w���J�A�Y���̌��J���t��ȂǂŁA�w���̉��t������A �͂��܂��Y��q�������ɏA�C�����㓌�ʎO�Y�ƌۓ��̃R���{���t����͂��߂Ƃ����Y���É��t�� �i�Y��Z���t�y���ŊJ�Áj��A���p�ق��ӏ܂����Ă�A�V�����ϐg�������ł̔����������H���� �J����̎U������y���݂��������̂��ꋻ�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����A���͖S���������q�e���̘^���������s�A�m�ŕ������A���̎����s�A�m���t�ƃx������ �t�B���̃����o�[�����t����Ƃ������ɂ��A�V���[�x���g�w���x��t�y���Œ����Ă��܂����B �����s�A�m�ւ̑ł����݂̒������\���C���̖����u�t�������t���Z�����搶�i�\���C���ł͖{���� �����Ă��������Ă��܂������c�j���s�����Ƃ����L����ǂ݁A�����������Ē����ɍs������ł��B �H�샊�q�e���Ƃ̑��̍��������t�͑�ϋ����[�����̂ŁA�@��������炻�̃R���T�[�g�ɂ��� �܂����̗��Ŏ��グ�悤�Ǝv���Ă��܂��B �@�I����A�t���ɐ�����Ȃ����̏�����������ċA��C�����悳�Ƃ�������I �@����A�F�l�ɂ�������Ă����������Ƃ������߂������܂��I
- 5��7���i�y�j�\���t�F�[�W������̏d�v��
�@�ŋ߃R���N�[�����s��ŁA�R���N�[���̉ۑ�Ȃ������玟�Ɏ�|���A���K�Ȃ≹�K�Ȃǂ� ��b���K��S���K��Ȃ��Ő�������q�������ƕ����܂��i�\���C���̐��k����ł͂���܂����I�j�B �F�X�ȃR���N�[���ɓ��܂��Ă���q�ł��A���������ɏK�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���b���w�� �傫���Ȃ�Ƃ�����A�R���N�[���ŏ܂��l�邱�ƂɊւ��ċߓ������Ă���悤�ł��Ȃ���A ���̎��ԓI�ȑ����͑���m��Ȃ����̂ł��B �@�������Ƃ��\���t�F�[�W������ł������܂��B�\���t�F�[�W��������̂��߂ɕK�v�� �ȖځA�ƔF�����Ă���l�������Ǝv���܂��B�m���ɊԈႢ�ł͂Ȃ��̂ł����A�\���t�F�[�W���ɂ́A ��w�̑O�ɂ���ɂ����y�I�̈���g���Ă������ȉ\������߂��Ă��܂��B������ �V�Ȏ����A�y�T����������̃\���t�F�[�W���ۑ�ɂ��Ă��鉹�傪�������߁A������Ƃ����ƁA �����E�V�Ȏ����ɍi���ă��b�X������搶�����܂��i�Ƃ������A���������������|�I�ɑ����ł��傤�j�B �ܘ_�A���������������̉��������Ƃ��A�ǂ̂悤�ȃ��Y�����������A������邱�Ƃ� �ł���̂͑�ł����A���������u���ɔc�����A�����������E���Y���ʼn̂����Ƃ͂ł��Ȃ��Ă� �����Ȃ����Ƃł��B�������A���̓����ۑ�͕K�v�ŏ����A�Ƃ�������e�ł��B �@�����y�����u���ɓǂݎ��s�A�m�E���@�C�I�����Ȃǂ̊y��Ő��m�ɒe�����Ƃ��ł��� �������t�̗͂��d�v�ł��B�y���̉����ɔ�₳��鎞�Ԃ̐ߖ�́A�]���ȗ��K���Ԃ̐ߖ�� �������A���K���e����薧�x�̔Z�����̂ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@������̔N��ɂȂ�ƁA�c��ȗʂ̋Ȗڂ���x�ɂ��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��Ȃ鎞�����܂����A �����\�͂������Ƃ������ɂłȂ��Ȃ�܂��B �@���y�̒m�����w�K����g�y�T�h�́A�Œ���A��Βm��˂Ȃ�Ȃ������ł��B����͊o���� ���܂��ςޓ��e����ł����A�̐S�Ȃ̂́A���̒m�����ǂ����y�Ɋ��p���Ă������|�|�A �Ƃ����W�J���@�ł��B �@�Ȃ̒��̓]���Ƃ��a���̕ω����A�a���w�̒m�����������킹�Ă���ƁA�����̗͂Ŋy�ȕ��͂� �ł���悤�ɂȂ�܂��B �@�y�Ȃ��������蕪�͂ł���ƁA��ȉƂ��ǂ̂悤�ȈӐ}�ō�Ȃ����̂��A�ǂ̂悤�ȉ��F�� �e���|�������߂Ă���̂����z���ł��A���t����C�ɗ��̓I�ɕς���Ă����܂��B�y����ǂ�� ���ɂ���A�Ƃ����i�K����A�����őt�@�≹�F��g�ݗ��Ăĉ��y�����A�Ƃ������x�Ŗ��͓I�� �̈�ɓ��B���Ă����܂��B �@�a���w����g�����y�ȕ��͂ƂȂ�ƁA�\���t�F�[�W���̈悩���E������������܂����A �a���w�����ł͌����Đ����ł��Ȃ����߁A�o���̔\�͂������̂ł��B �@�s�A�m��e���l�̏ꍇ�A�y���ɏ����Ă��钲���ڒ����Ēe�����Ƃ��ł�����A�����f�B������ ���ɔ��t�����邱�Ƃ��ł����肷��悤�ɂȂ�ƁA�܂��܂��Ⴄ���E���J���Ă����܂��B �@���̊y��̉����A�̂��̂��l�̐��̍����ɍ��킹�Ĉڒ��������l�ł�����A�����Ŕ��t�� �t����ꂽ��A�A���T���u������w�y�����Ȃ�܂��B �@����Ƀ\���t�F�[�W���Ƃ����Ă����̂悤�ɕ����L���̂ł��B �@�ǂ̂悤�ȕ���ł���b����ƌ����܂����A��b�炸�ςݏd�˂Ă����ƁA�̂��̂� �ł��邱�Ƃ����݂Ɍq����A�傫�ȉ\���̕������܂�Ă��܂��B �@�\���C���o�g�̏a��i�^���搶���A �u�\���C���̃\���t�F�[�W����������������K�������A�ŁA���y���ԂɐM�������悤�ɂȂ�A�@ �@�d���Ɍq�����Ă���͖̂{���ɗL��ł��B�v �ƌ����Ă��܂����B �@�i�^���搶�́A�������̗��z����̌`�ɂȂ����p�ł��B �@���邱�ƂȂ���A��b���K�ƃ\���t�F�[�W���I�����ɂ����Ă���b�͑�Ƃ������b���ł����B �@
- 4��9���i�y�j���{�W���j�A�N���V�b�N���y�R���N�[���S�����E���܁^���I
�@ �@��R�O��S���{�W���j�A�N���V�b�N���y�R���N�[���S�����y�핔�咆�w���̕��i���F������ �V���t�H�j�[�q���Y�j�ŁA�\���C���������y�������k�̈˓c���ق���i���c�旧�������w�Z�P�N�j�� �R�����܁A�V�䐐�䂳��i������{��w��������w�Z�R�N�j�����I���ʂ����܂����B �@���N�����k�������R���N�[�����ɐϋɓI�ɒ��킵�A�v�X�ǂ��o����ς�ł����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �˓c����A�V�䂳��A���߂łƂ��������܂��I
- 4��8���i���j�S���Q�X���APh.�o���x���A���}�X�^�[�N���X
�@�S���͐V�w�����}�������ƍs�����������ł����A�v�X�Ƀ}�X�^�[�N���X�i���J���b�X���j���u�t�ɂ�� �~�j�R���T�[�g���J�Â��܂��B �@�u�t�̓t�B���b�v�E�o���x���A���B�p�������R���Z�����@�g���[���C����A���݃p���E���[�c�@���g �R���Z�����@�g���[�������߁A�s�A�j�X�g�E�w���҂Ƃ��Ċ��Ă�����ł��B �@�\���C���̐��k����́A�Q�n���s�A�m�R���N�[�����w�R�E�S�N���̕��D�G�܁A��R�W��o�s�m�`�s�A�m �R���y�e�B�V�����a���n���{�I�D�G�܂���܂�����������N�i����܍��ۃA�J�f�~�[�U�N�j����u���܂��B �@�~�j�R���T�[�g�ł̓V���p���A�h�r���b�V�[�A�T�e�B�Ȃǂ̖��Ȃ����t���Ă��������܂��B �@�}�X�^�[�N���X�͌��J���b�X���`���ŁA�~�j�R���T�[�g�ӏ܂��܂߁A�����͑�l��2,000�A�w����1,000�B �@�����͂S���Q�X���i�j�j�P�S�F�O�O�i�}�X�^�[�N���X�J�n�j�ł��B�}�X�^�[�N���X�I����������� �~�j�R���T�[�g���J�Â������܂��B �@���̓\���C���������y�����Q�e�z�[���B �@�S�[���f���E�B�[�N�͂��߂̑u�₩�ȗz�C�̒��A��R�̕��ɂ��炵�Ă��������A�撣���Ă��鐶�k����� ���t�Ƒf�G�ȃt�����X���y�����y���݂���������K���ł��B �@�}�X�^�[�N���X����悵�ĉ��������������}�q����A���肪�Ƃ��������܂��I
- 4��7���i�j�A�������搶�A�V�������@�C�I�����̃N���X�n���I
�@���̋G�߂ƂȂ�܂����B�C�����オ�肷������t�ł��B �@���̂S���A�܂��V�������@�C�I�����̃N���X���X�^�[�g���܂��B�V�������@�C�I������ �搶�́A�����Y�p��w��w�@���m�ے����C�����A���y���m�̏̍��������@�C�I���j�X�g�A �A�������搶�B �@�A���搶�͊��o�g�A�����|�p��w���y�w���������y�����w�Z�i�ʏ́A�Y���j�A�Y��� �o�āA���m�ے����C������܂łP�Q�N���Y��ɒʂ����Y��̐��������̂悤�ȕ��ł��B�Y�� �o�g�̉��y���m�ƕ����ƃR�`�R�`�̍ˏ���z�����邩���m��܂��A���ۂ͂��̈�ʓI�� �C���[�W�Ƃ͊|�����ꂽ�A�Ί�͂������炩�őf�G�ȏ����ł��B �@������������p�ˋ�����邽�߉����܂Ń��@�C�I�����̃��b�X���ɒʂ��Ă����̂��� �v���f���Ă݂�ƁA�A���搶�̉Ƃ̋ߏ����Y��o�g�̃��@�C�I�����̐搶�����炵�āA������ ��������܂ł��̐搶�Ɏw�����Ă����Ƃ������ƂŁA�s��ŃL���L���d���܂ꂽ�̂ł� �Ȃ��Ƃ��낪�A���̖��邳�̗R����������܂���B �@�Y���ɓ��w���Ă���͔��m�ے��܂ł̂P�Q�N�ԁA�������t�搶����A��b�e�N�j�b�N���܂߂� ���b�X����O��I�Ɏ�ꂽ�����ł��B�����̃e�N�j�b�N�͂������A�͂�����Ƃ����ӎ��� ���Ă�N��ɂȂ��Ă���e�N�j�b�N�����グ���o���̂�����́A�����邱�Ƃ���肾�Ƃ��� ���ʓ_������܂��B���@�C�I�����̐搶�Ƃ��āA�������N���N����G�s�\�[�h�ł��B �@�A���搶�̓R���N�[�������₩�ł��B �@��S�U��E��S�V��S���{�w�����y�R���N�[�����É����w�Z�̕���P�ʁA��S�W��S���{ �w�����y�R���N�[�����É����w�Z�̕���P�ʁA���{���t�ƃR���N�[�����Z�̕��ō��ʁA �x�a�o���ۉ��y�R���N�[�����Z�̕���P�ʓ��A�����ɉɂ�����܂���B �@���@�C�I�����̃N���X�͐l�C������A��]���Ԃ�������t�ɂȂ��Ă��܂��܂�����A ���b�X����u��]�̕��͂����߂ɂ��\�����݂��������B
- 3��5���i�y�j���ɗǖ���I
���Ȑl�̉��t���ӏ܂��邱�Ƃ́A���ɂƂ��Ẳ����̖�ł��B �����Q�N���A�w�lj��t��ɂ͍s�����A��X�Ƃ������X���߂����Ă��܂����B ���w���A�~���m�ɏZ��ł������̓X�J�����A�p�����������͊X���ɓ_�݂��� �I�y�������R���T�[�g�E�z�[���ƁA�����Ɋ|����I�y����R���T�[�g�͉\�� ���蒮���Ă��܂����B �p���@���b�e�B���o�����鉉�ڂ̓`�P�b�g���肪����ŁA�P�T�ԗ�ɕ��Ԃ��A ���y�ԐȂ��K�����A�Ȃ̔N�ԃI�y���V�[�g�������Ă��邩�i��������ɂ���� ������Ȃ����Ƃ�����j�łȂ��Ɩ����A�p���@���b�e�B�̐��̐��͎c�O�Ȃ��� ���ǒ����܂���ł������A����ȊO�̐��E�̃g�b�v�̎�̃I�y����R���T�[�g�A �����Ȋy�퉉�t�҂̃��T�C�^�����X���A���{�قǍ����łȂ������Ŏv������ �������Ƃ��ł����͍̂K���ł����B �@�ǂ̉��t���R���N�g�ŁA�ǂ̂悤�ȉ��t�ɖ�肪����̂��������鎨�� �|���Ă��Ȃ��ƁA�����̉��t���q�ϓI�ɒ����Ď����̗͂ŗǂ������Ɏ����� �������Ƃ��ł��܂���B �@���ƃ��Y���Ƃ����m�ɉ��t�ł�����R���N�g�A�̂͂��͂Ȃ��i�̂̏ꍇ�� �����B������̂��[������̂ł����c�j�A���Ȑl�ɔ�ׂĎ����ɉ��� ����Ȃ��̂��l���Ȃ��璮���Ă������̂ł��B����͍��ł��K���ɂȂ��Ă��܂��B �@�����ǂ��A�͂܂��A���������A���L������Ɖ�����o����e�N�j�b�N�������A ����ɂ���ĕ\���̉\�����L����A�_�����������y���Ɍq���Ă���c�A���̂悤�� ���t������l�����݂���̂�ڂ̓�����ɂ���͎̂h���I�ł��B �@���̐l�ɏo���邱�Ƃ������ɂł��Ȃ��͂����Ȃ��A���͂����l���܂��B �@���̏ꍇ�A���ؗ͂ƌ��o���̋ؓ��R���g���[���\�͂��ꗬ�̐l�����Ɣ�ח���Ă��� �Ɣ��f���܂����B �@���͌��̒��̋�Ԃŕω����܂����A���̒��̐��Ӌ������̈ӎu�ŃR���g���[�� �ł��Ȃ��Ă͂����܂���B�X�ɕ�����B���n�̑������c�s�炿�͎R�炿�̐l�� ��ׂĕ�������Ă��܂��B �@�������A����Ă��邱�Ƃ�����������𒆐S�ɌP�����ł��܂��B���̍��ɋC�t�� ���Ƃ�����̃|�C���g�Ȃ̂ł��B �@�u���y���������Ƃ��A���̎���̃X�^�C���ɍ����Ă��Ȃ����Ďw�E���ꂽ�̂ł����v�ƁA ���k���邱�Ƃ�����܂��i�\���C���̐��k����ł͂���܂����I�j�B����� �ł��邾��������������D�ꂽ���t�Ƃɂ��l�X�Ȏ���̉��y���Ă������Ƃɂ���� �i���̉��t�ł͂Ȃ�CD�ł�DVD�ł��悢�̂ł��j�A�ȒP�ɉ����ł��܂��B��l�ɂȂ��Ă���ł� �x���Ƃ������Ƃ͂���܂���B�@ �@�����A������Ă���Ȃ���K�ƕ��s����CD�ȂǂŒ������́A���CD���āA���̋Ȃ� ���Y�����≹�̏o�����Ȃǂ̃j���A���X��̂̒��ɓ���Ă��܂��������A���K���y�ɂȂ�̂� �m���ł��B �@����l������A�ǂ��CD������ǂ��̂ł��傤���A�Ƃ���������܂��B�W���P�b�g�� ���߁A���y�G�����ŏ����W�߁A�R�c�R�c��CD���W�߂���A�ǂ������f����̂����R�[�h �iCD�j�ӏ܂̉����ł��傤���A����ł͎��Ԃ��������|���肷���܂��B��s�s�ɍs���ΐ}���ق�����A ���yCD���C�y�Ɏ�Ă��邱�Ƃ��\�ł����A�c�ɂł͂���������ɂ������܂���BYou tube�� �����ł���CD�̔�����Ă��Ȃ����t���������Ƃ��ł��܂����A�S�Ă��ǂ����t�Ƃ����킯�ł��Ȃ��A �������悭����܂���B�����悭�ǂ����t�ɏo��ɂ́A�A�h���@�C�X���K�v�Ƃ����܂��傤�B �@����ŁA�������͒����������ǂ�CD�����X�g�����A�ł������Ή�����悤�ɂ��Ă��܂��B �@�����̃��@�C�I���j�X�g��y�o���������t�h���V�[�E�f�B���C���j�́A�u���̋Ȃ͂��̐l��CD�� �����Ȃ����v�ƁA�Q�l�ɂ���ׂ����t�Ƃ�CD����Đ^���������A�Ɩ{�ɍڂ��Ă��܂��B �@�����t�������w���҂̐搶������A���y�����������A�Ƃ������Ƃ��K���܂����B�������A �P���P���K���Ă���Ƃ��ꂱ�����b�X�����Ԃ������Ԃ����Ă�����܂���B�^������Ƃ���� �^�������āA�����ʼn��y������悤�Ɉ�ĂĂ����K�v������܂��B �@�R���T�[�g�ɍs���ėǂ����t�ɏo��Ǝ������Z�b�g����܂��B�ǖ�����Ɂi���ł͂Ȃ��c�j ����@����ǂ�ǂ����Ă����������̂ł��B�@ �@
- 2��6���i�y�j�N��I���i���\
�@���N�͔N�������X�ɍ��i�̘N��ł��I �@�����Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�i�Y���j�s�A�m��U�ɂj�N�i���c�����j�� ���i���܂����I �@�n���ҁE���эG�q���\���C���������y�������n�߂��R�R�N�O�A�����s�т̒n�ƌ����� �����Q�n�����c�s�ł́A��s���̂���Ƃ͑S���قȂ鐅���ŁA�N���V�b�N���y�̋��炪 �s���Ă��܂����B�q�ǂ�����c�ʼn߂����A��������ɐi�w�������Ǝv�������ē����܂� ���b�X���ɒʂ��Ă��A�i�w�ł��鉹��ɂ͌��肪����A�Ȃ��Ȃ���]�̉���ɂ͓���Ȃ� �Ƃ����̂��R�O�N�O�̏ł����B�搶�̋Z�p�͂����łȂ��A���v���ƁA���ʂ������ƕs�� ���Ă����̂ł��傤�B �@���Q�l��̉���ɐi�w���������Ɗ���Ă������т́A���Ȃ����̒����玝���O�̍s���͂� ���̌����Ŕj���悤�Ǝ��݂܂��B �@���t��ɑ��ɂ��ʂ��A�����̎��ł��̃s�A�j�X�g�A�Ǝv�������̊y���ɖ���A��čs���A���k���� ���b�X�������肢���A��q���肪�����܂����B�m�l�̏Љ�Œ�q���肷��̂��펯�̂��̐��E�A�@���� �m��Ȃ��Ƃ͂����A��_�Ȑ荞�ݕ��ƌ����܂��B �@�������w�T�N�����炻�̐搶�ɏK���n�߂�ƁA�P���P���A���̏o���������蒼������������ �n���̃��b�X�����n�܂�܂��B�R�����ԃn�m�����g�����^�b�`�̏C�����肪��������A���F�� ���Ⴆ��قǃu���b�V���A�b�v����Ă����̂��킩��A����܂ŎĂ������b�X���Ƃ̈Ⴂ�� �S����������т́A���̎w���͂��������搶���ɑ��c�ɗ��Ă��������悤�z�����A�����̎d���̂��߂� �w�������r���̂Q�K�ƂR�K���Ă��邩�璚�x�ǂ��Ƃ���A���y������ݗ������̂ł����B �@�q���̎�����K�����������R�Ɛςݏグ�Ă��������ŁA�����Y������߂Ƃ����v����ɍ��i�ł��� �[���������y����A����c�̎q�������Ɏ��������Ƃ������т̎v���̎킪�R�R�N�O�Ɏ����ꂽ �̂ł��B �@���̌�A�����̓����Y�升�i�ҁi�s�A�m�ȂƐ��y�ȁj�A�����Ė��N��v���y��w�E���y���Z�ւ� ���i�҂𑗂�o���Đݗ��̖ړI���ʂ������A��ւƌ����铌���Y�p��w���y�w���������y�����w�Z�� �s�A�m��U�ɐ��k�𑗂�Ȃ����A�Ə��т̖��͖c���ł������̂ł����B �@���y����Ƃ���B��̍����̍��Z�ł����Y���̕�W�l���͂P�w�N�S�O���i�N�ɂ���Đ�����������j�A �Q�W��ނ̊y��ʂ̐�U��W������A���̒��Ńs�A�m��U�͖��N�P�Q�������i���܂��B��s���i�����E �_�ސ�E��ʁj���炩�Ȃ�̐l��������܂�����A����ȊO�̒n������͖��N�������x�Ƃ������Ƃ� �Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�P�T�ɂ��Ċ����`��v��������Y���̃��@�C�I������U����ւŁA��x�̓s�A�m��U�Ƒo�����Ȃ��A �P�̊w�N�Ńs�A�m�ƃ��@�C�I�����̐�U�҂��U�����߂܂��B �@���̑��Ƀ��B�I���E�`�F���E�t���[�g���A����ǂ̊y��Q�ƍ�ȁA�����č����̉��y����@�ւƂ��� ���ƂŖM�y�̒��S�E�O�����EⵁE�ڔ����̐�U�������܂��B �@���{������W�܂������s�������Y����Y���̐搶�������疈�T��������̃��b�X�������������� �����̂ł�����A�h���I�ŏ[�������R�N�ԂƂȂ邱�Ƃł��傤�B �@�܂��_�������Ⴂ�����ɗ��z�I�ȉ��y���̒��Ŏv�����������ł���͖̂{���ɑA�܂������� �ł��B �@�L���邾�����y�̗͂�L���A����ŋ��{�̂��镶���l�ƂȂ�悤�A���y�ȊO�̕��ɂ����� �~�����Ɗ���Ă��܂��B �@�Y���ɓ��邱�Ƃ��l���̖ړI�łȂ����Ƃ͎����̗��ł��B�j�N�ɂ͌b�܂ꂽ�X�^�[�g���ꂽ���Ƃ� ���o���A���Ɍ������ĕ���ł����ė~�������̂ł��B �@���w�����������Ă���搶���A�������ĉ�������X�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B �@����̑��������������n���҂��V���������ł���p��������悤�ł��B �@�����������F����A���͂��Ȃ������̔Ԃł���I���Ɍ������Ċ撣���Ă����܂��傤�I �@
- 1��9���i�y�j�����Ԃ̗��K�ƋC����
�@�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �@�F�l�A�y�����N���N�n���߂�����܂����ł��傤���H �@���̔N���N�n�́A�S���x�݂���炸���K�ɕt�������ĉ߂����܂����B �@�N���N�n�̒����x�ݒ��A�V�тɍs���Ȃ��ʼn߂����Ǝv���̊O�����Ղ���K���Ԃ� ��邱�Ƃ��ł��܂��B���̉�Ђ͂��x�݂ŁA�����I�Ȏd���̓d�b��K�₪�Ȃ��ł����A ��������Ăɂ��x�݂���̂ŁA���x�݂��邱�ƂɌ��߂������������ɂ����܂��B �@������g�������ē����₷���i�D�����A�����Ղ�̐H����①�ɂɋl�߁A�������K�ցB �@�ʂ��̗��K�̌�A���K�̌v��𗧂Ăčׂ������������������K���J�n���܂��B�Ă����� �W�������K���邱�Ƃ��ł���Ƌ����قǏK���x���t�o�B�S���t��������Œ����Ă����ł� �Ȃ��̂ŁA�r���H���̏�����������A�Ƃ̒��̑|����������A���܂��Ă��鎖���d���� �Еt������ƁA�F�X�Ȃ��Ƃ�����܂��B �@����Ă���Ɨ��K����{�l�������Ԃ̗��K����ɂł͂Ȃ�������O�Ȋ����ɂȂ��Ă��� �悤�ł��B �@��N�̃N���X�}�X�R���T�[�g��̃p�[�e�B�ŁA�v����ڎw���l�����́A�x�݂̓��ɂP�� �P�O���Ԃ�ڕW�ɗ��K���܂��傤�I�ƌĂт������Ƃ���A�N���ɒ��w������A �u�搶�Ɍ���ꂽ�̂łW���Ԕ����K���܂����B�v �u�����W���Ԃ���Ă��܂��B�v �Ƃ������������܂����B �@�R�l�̑��q�𓌑嗝�V�ɍ��i���������ꂳ��ɂ��A�~�x�݂͂P���P�T���ԕ����Ȃ���� �����Ȃ��̂������ł��B���ɁA�y��̗��K�ɂ����Ă͂P���P�O�`�P�Q���Ԃ����E�B�J�݂R�Q�N�� �\���C���������y�����ł����A�u�P�O���ԗ��K���܂��傤�v�A�ƌĂт����āA �u�͂��A����Ă��܂��I�v �Ɠ����Ă��ꂽ���k���������Ƃ͂Ȃ��A�q���������f���Ȏ���Ȃ̂��A���R���������q������ �������̂��A�F�������Ċ撣��Ƃ����C�^�����܂��Ă���̂��A������ɂ��Ă���������Ƃł��B �@�����ԗ��K�ł���ƁA�����I�ɑ�R�̋ȂɎ��g�߂�悤�ɂȂ�܂��B �@�s�A�m�⃔�@�C�I�����̋ȂȂǂ͂R�O������Ȃ�����܂����A���Ȃ����K���Ԃ��Ɣ[���� �����Ƃ���܂ōו��ɖ������������܂���B �@�P�ȂR�����炢�̗��K�ȂȂ�P�T�ԂłS�`�T�Ȏd�グ�Ă������Ƃ��ł���ł��傤�B �@�s�A�m�Ȃ�A�w�̌P���̂��߂̃��\�b�h�i�n�m���Ȃǁj�A���K�ȁi�c�F���j�[�Ȃǁj�A�o���b�N �i�o�b�n�Ȃǁj�A����ȊO�̌ÓT�A���}���h�A�ߌ���̋ȁA�Ƃ����悤�ɁA��܂��ɋ���� �S��ނ̕���̋Ȃ���s���ė��K����K�v������܂��B�ł��Ȃ��ӏ����ł���悤�ɁA�Ⴆ�A �������ƁA���Y����ς��āA���`��ς��āA�ȂǍH�v����A�搶�Ɍ���ꂽ������ȑz�ɂȂ� �悤�ɂ悭�����Ȃ���J��Ԃ����K����A�S�̓I�ȗ����͂ޗ��K������E�E�E���A���Ԃ��|����� �P�Ȃ��ƒ��J�Ɏd�グ�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����Ԃ̗��K�͊���ł�����̂ł����A���n�߂悤�I�ƌ��S���鎞�ɂ͋C�������K�v�ł��B �@�@�d���̃R�c�͋C������ �@�@���Ƀ��e��R�c�͋C������ �@�@�j�Ƀ��e��R�c�͋C������ �@�@��T�̂��Ƃ���肭�����Ȃ��̂� �@�@�C����������Ȃ����炾�@�@�@�@�@�@�@�@�֓���l �@�@ �@�@�i���̕����ǂ�ȕ����͒m��܂���E�E�E�j �@�@�����Ă��邱�ƈȊO�� �@�@�����ʼn������邩�ł� �@�@�������ɂƊ����邩�ǂ����� �@�@�ꗬ�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����� �@�@�����ꓹ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䑺��� �@�@ �@�@�i���I�f�W���l�C���ܗցE�V���N���i�C�Y�h�X�C�~���O�w�b�h�R�[�`�j �@�@�l���͟������Ő����Ă䂭�@�@�@�@�@�����J�d�G �@�@�i�������̍���c���j�@�@�@�@ �@�����J�d�G����̂��̌��t�͒j�̂�������̂��ߋ�j���̐F���ɏ��������́B���c��l�� �j�̎q�ւ̗͋������b�Z�[�W�ł��B �@����ɂ��Ă��F����A�����C���������Đ����Ă��銴�������܂��ˁB �@�����Ē����ɗ����オ����K���n�߂����k�����̔g�ɏ���āA���N�A�F���O������ �C�����ŗ��K�Ɏ��g��ʼn����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
- 12��5���i�y�j�w�R�E�m�h���x�w�̂��߁x�̌��\
�@�\���C���j���[�X�����G�b�Z�C�������łQ�O�O���ƂȂ�܂����I �@�P�X�X�X�N�T���ɃX�^�[�g���Ĉȗ��A�P�V�N�߂��Ό����o�����ƂɂȂ�܂��B �@���̎��X�ŖڂɎ~�܂��� �g�����ǂ����Ɓh���F�l�ɂ��`���������Ƃ����̂� �����n�߂����@�ł������A�l�^���s���邱�ƂȂ������邱�Ƃ��ł����̂́A���P�� �Ƃ����y�[�X�����x�ǂ���������ł��傤�B �@�g�����h�Ƃ����@���^���Ă��������������ŁA���������邱�Ƃ��ł��A������ ���Ƃ��ł��������ŁA�������Ƃ����������ɂȂ�Ȃ��Ȃ����Ƃ����̂́A�K���� ���Ƃ��Ǝ������Ă��܂��B �@�ߍ��w�R�E�m�h���x�Ƃ����e���r�h���}���b��ł��B �@�u�w�R�E�m�h���x���ăh���}�m���Ă�H�l�̂�������̂��d���Ɠ����Ȃ�A �搶���Ă�ˁB�v �@���w���̒j�̎q�����Ă���܂����B����ȊO�ɂ��F�X�ȕ�����w�R�E�m�h���x�� ���Ă̂��b���f���܂��B �@���A�ƂɃe���r�������i�{��!?�Ƌ������j�A�ǂ�����Ęb��ɂ��čs�������� �v�Ă��Ă�����A���͒T������̂ł��ˁE�E�E�A�C���^�[�l�b�g��GYAO�Ƃ����f��� �e���r�̔z�M�T�C�g�������āA�������Ă݂܂����B �@����͕a�@�̎Y�w�l�ȁB�Y�w�l�Ȉ�Ə��Y�t�A�V�����ȁiNICU�j����Y���Z���^�[�� ��t�𒆐S�Ƃ����ÃX�^�b�t����ȓo��l���ŁA�o�Y�Ɋւ��Ă̗l�X�ȓ�₪���グ ���Ă��܂��B �@����f�D�w�̏o�Y�A�P�S�˂̏��̎q�̔D�P�Əo�Y�A��ʎ��̂ɑ������D�w�̏o�Y�A ���n���̏o�Y�A�s�D�ǁA�D�P���̕��]�늳�ɂ��Ԃ����̔�����ƐS�������A���Y�@ �ł̏o�Y�A�ٔՑ��������̎�p���X�B �@������[���Ɏ�ނ����Ǝv���郊�A���e�B������A���x�̔Z���X�g�[���[�ɃO���O�� �䂫�����Ă����܂��B �@�������g�̏o�Y�̌��͂P��ŁA�o�Y�o���҂Ƌ����Č����闧��ł͂���܂��A �̂���o�Y�ɂ͔��ɋ���������A�q���������ɏh��O����o�Y�Ɋւ���{��L���Ȃ� �悭�ǂ�ł��܂����B���S�ɏo�Y���邽�߂̏������@�A�܂��A���R�ɎY�ނ��߂̏o�Y���� �ċz�@��S���ȂǁA���Y�@�̐搶�ɐ�����ʂɏo�Y�������J�݂��Ă��炢�A�������O���� �ʂ��ďo�Y�̕����������ł��i�����ʼn��l���̏o�Y���r�f�I�Ō����đՂ����̂ŁA �N������R�o�Y�����C���ł����k�l�j�B �@�̂ɔ�ׁA�o�Y�ŖS���Ȃ邨�ꂳ����Ԃ������������͖̂ڊo�܂�����ËZ�p�̔��W�� �����̂ŁA�{���ɑf���炵�����Ƃł��B��������̊��Ɍb�܂�߂��Ă��邽�߂ɁA �D�w�������A�o�Y���I�ɑ����߂��Ă���A�Ƃ����h���}�ł̎w�E������ł��܂��B �o�Y���g�Y�܂��Ă��炤�T�[�r�X�h�Ǝ~�߂Ă���A�ƌ�������悢�ł��傤���B���N�� �Ԃ������Y�ނ��߂ɁA�����ĂȂ�ׂ����R�ɏo�Y�ł���悤�ɁA���O�̎�̓I�ȕ��� ��Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B �@���̃h���}�̒��ł͐��S�O�����̐Ԃ���o�ꂵ�܂��B�o�Y�V�[���̐Ԃ��������㐔���� �V�������o�����Ă��邻���ŁA���̃��A���e�B�ɋ����̘A���ł��B�Y�܂�Ē����̐V�����͎Y�Ȃ� ����̂ŁA�Y�w�l�Ȃɂ͐V�����Ȃ̈�t���p�ɂɏo���肵�܂��B �@�l�̂�������̂��d���I�ƌ��������w���̃p�p�͂����œo��ł��B �@�h���}��ʂ��āA��Ԃ����������l�̖����~���a�@�̐搶�����̎p������ƁA����������܂��B ���w���̒j�̎q���g�l�̂�������h�̎d���̌����m��A�ւ炵���Ȃ̂͑f���炵�����Ƃ��Ȃ� �Ǝv���܂��B �@��l���T�N���͎Y�w�l�Ȉ�t�ł���Ȃ���ABaby�Ƃ����A�[�e�B�X�g�������s�A�j�X�g�ł� ����܂��B�ً}�̃x���ŌĂ��ƁA���Ƃ��{�Ԓ��ł��낤�Ɩ{�Ԃ𒆒f���ĕa�@�ɋ삯���� ���߁A���C�u�͋M�d�ŁA���̐��͓̂�ɂ܂�Ă���Ƃ����ݒ�B �@�o�Y���ɕꂪ�S���Ȃ������ߎ����{��{�݂ň炿�A�{�݂̐搶�i�搶�����W���Y�s�A�j�X�g�� ���˒q�b!!���ꂪ�{�����������肭�Ȃ�Ȃ��͂��͂Ȃ�!!�j����s�A�m���K���ăs�A�m����B���A ��t���v���s�A�j�X�g�ɂȂ����Ƃ����́A���k�����̌���S�ɉ������悤�ł��B ��l�����j���̂��߂����ɒj�̎q�������A������t�ɂȂ��ăv���s�A�j�X�g�ɂ��Ȃ�A�Ƃ��A�l�� �v�����@�C�I���j�X�g�ɂȂ�A�ƌ����Ă����̂͊������͔����ł��B �@�ȑO�w�̂��߃J���^�[�r���x�Ƃ����h���}�Ɋ�������A�s�A�m�l���������A����ɐi�w���� �l���������l�����܂����i���̎��͎�l�������̎q�������̂Ŋ������ꂽ�̂͏��q�����ł������E�E�E�j�B �@���̎h�����Ȃ�������A���̎q�����͂��̂悤�Ɋ撣���ĉ���ɂ͐i�܂Ȃ������̂�������Ȃ� �Ǝv���ƁA���܂͕K�v�Ȃ�I�Ǝv������ł��B �@�������Q�O�P�T�N�͍������c���݂̂ƂȂ�܂������A������\���C���j���[�X�͂܂��V���ȋC������ �����Ă܂���܂��B�ǂ��������҂��������I �@�F�l�A�悢�������}���������B
- 11��7���i�y�j���C�ƔM�Ӂ`�o���G�̏ꍇ
�@�ŋ߁A���C�Ƃ��M�ӂɂ��čl���邱�Ƃ�����܂��B �@�v����ڎw���ďC�s���̐l�����ɂ͂��̔R����悤�ȋC�������s���ł����A ���K���d�˂Ă����ɂ�ē����̏�M�������Ă��܂����Ƃ�����A�M���v���� �������ɗD�ꂽ�\�͂�L�������čs���ɂ͂ǂ�������悢�̂��A�������� �����l���Ă��܂��B �@����A�o���G��DVD���Q�{�w�����܂����B�P�{�̓W���j�A�̂��߂̐��E�Q�� �R���N�[���̂P�ƌ����Ă��郆�[�X�A�����J�O�����v���iYAGP�j�̏o��҂� �ǂ����h�L�������^���[�f��w�t�@�[�X�g�E�|�W�V�����x�A�����P�{�͖���p�� �I�y�����o���G�w�Z�̂P�N�Ԃ̐������B�����w�����̃G�g���[�������x�B �@YAGP�͐��E�U�����ŗ\�I���s���A���N�o��҂��T�O�O�O�l�����K�͂� �o���G�R���N�[���ŁA��ʂ̐l�����͐��E�e���̃o���G�c�ւ̓��c��o���G�w�Z�� ���w���Ȃǂ������A�o���G�_���T�[�̓o����ł��B �@�f��̒��Œǂ��̂́A�c�������^���\�͂ɗD�ꂽ�����Ŕ������A�����J�l�� �P�P�˂̒j�̎q�A���{�l�̋���M�S�ȕ�������A�w�Ƃ̓o���G�̂��ߒʐM����� ��ւ����P�Q�˂̃A�����J�l�̃n�[�t�̏��̎q�A�V�G�����I�l�̓���Őe��搶�� �ڂ̑O�ŎE�Q���ꂽ�ߋ��������A�����̂��ߍ��ʂ���A���̌�A�����J�l�̗{�q�� �Ȃ����P�S�˂̍��l�̏��̎q�A�n�������甲���o�����߂ɗ��e�̔M�����҂�w�����āA �P�g�A�����J�ŏC�Ƃ���R�����r�A�l�̂P�U�˂̒j�̎q�A�j�b�N�l�[�����g�o�[�r�[�h�� �������ƌo�ϓI�L�����A�g�̔\�́A��������Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��A�����J�l�� �P�V�˂̏��̎q�A�̂T�l�B �@�����u�����T�l�ł����A���̋ɒ[�Ȑ�����̈Ⴂ�́A�܂�Ńh���}�����Ă��� �悤�ł��B�B�ꋤ�ʂ���̂͋������̗��K�ʁB ���̉f�悪�B�e���ꂽ�̂͂Q�O�P�O�N�ŁA���̌�T�N�o�������݂̔ނ��ǐՂ��邱�Ƃ� �ł��܂��B �@���̃R���N�[���̐R��������̂́A�p���I�y�����o���G�w�Z�̍Z�����͂��߂Ƃ���A ���E��ꋉ�̃o���G�c��o���G�w�Z�̐搶�����ł��B���E������W�܂����Ⴂ�_���T�[�� �������߂�̂��Ƃ�������ɑ��āA�Z�p�A�|�p���A���y���i���Y�������j�͖ܘ_�̂��ƁA ������Ȃ͔̂M�ӂ��ƌ��𑵂��ē����Ă��܂����B �@��������̃p���I�y�����o���G�w�Z��DVD�́A���N�P�O�O�O�l����I������鍇�i�� �Q�O�l�قǂ̓��w������n�܂�܂��B���w�����ł͏_��A�g�����A���i�ɒ�߂�ꂽ ����N���A����͖̂ܘ_�̂��ƁA�ӎu�̋�����M�ӂ����o�����Ƃ���ƁA�������� ����Ă��܂����B �@���w��A�ނ�̓t�����X���Ƃɂ�闝�z�I�ȃo���G���炪���܂��B����̏�B�x�� �Ⴓ�����C�ɂȂ�̂��A�F�߂��Ȃ����߂ɃC���ɂȂ�̂��A���̎q�Ǝ������ׂ� ���C��������̂��͕�����܂��A���_�I�ɂ��������ɂȂ�A��M�������Ă����q�� ���\����̂͋����ł��B�w�N���̎����Ŗ��N���l���͗��Ƃ���ފw�ɂȂ�܂��B �@�����Đ��܂ꂽ�����\�͂Ɨ��z�I�Ȋ������ł́A�ӎu�̎���������A�Ǝv�킹�� �h�L�������^���[�ł��B �@YAGP�̂T�l�̌��݂��ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�����̂���Ƃ���ł��傤�B �@�V�G�����I�l�o�g�̍��l�̏��̎q�́A���̐������ƃR���N�[�������S�ĂŗL���ɂȂ�A �{���o�ł���i���{��������j�A���݃I�����_�����o���G�c�̒c���ɂȂ�܂����B �R�����r�A�o�g�̒j�̎q�͏��w���ƂȂ������C�����A�J�f�~�[���C�����A���݃C���O���b�V�� �i�V���i���o���G�̒c���ɁB �@���̂Q�l�͋t�����ӎu�͂����߂���Ƃ����Ă����ł��傤�B �@���{�l�ƃA�����J�l�Ƃ̃n�[�t�̏��̎q�́A���̌ピ�@���i���ۂƃ��X�N�����ۂŗD������ �R���N�[���L�����A���d�ˁA���N����o�[�~���K�����C�����o���G�̒c���ɂȂ�܂����B ��e�Ƃ̋����W���A���̏��̎q�̑O�����Ȉӎu�����������Ă���悤�ł��B �@���z�I�ȉ^���\�͂����A�����J�l�̒j�̎q�́A���E���̃o���G�w�Z����̃I�t�@�[�� �Ȃ���A�A�����J�Ń��b�X���������Ă��܂��BYOU TUBE�ȂǂŌ��邱�Ƃ��ł��� ���݂̔ނ́A�������b����ꂽ�g�̂������Ȃ���A�܂�Ȃ����ɗx���Ă���\���ۓI �ł����B�����u�����������A�听���Ăق����l�ނł��B �@�o�[�r�[�����͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�H�_��̍����g�́A�����Ŕ������e�p�A�b�܂ꂽ �o�ϊ��̔ޏ��ɂ́A�{�ԂŕK�����s����A�Ƃ������_�͂̎コ������܂����B�w�Z�� �`�A�K�[����������A�{�[�C�t�����h�ƗV��Ƃ����y���݂�����A���_�͂̎コ�A ���C�̌��@��w�͂ŕ₤���ƂȂ��A�o���G�����߂܂����B �@ �@�t���̂Q�l�̃M���M���ƋP���ځA�n�[�t�̎q�̃j�R�j�R���炵���Ί炪��ۂɎc��f��ł��B �@�̂�т�Ƃ���Ȃ�ɐ�����̂��K���Ȃ��Ƃł��傤���A�����ӎu�����������Đ����� �ނ�̂悤�Ȑ������́A�v��m��Ȃ����͂Ɉ��Ă��܂��B
- 10��3���i�y�j�����͑f�G�ȃN���X�}�X
�@�{�I�����Ă�����10�N�O�Ɋ��s���ꂽ�G�����o�Ă��܂����B �@���̒��Ɍf�ڂ���Ă��銪���G�b�Z�C��ǂ݁A10�N�O�A��� �܂𗬂����̂��v���o���܂����B �@���\�m���Ă���b�Ȃ̂ł����m�̕������������邩���m��܂���B ���w�Z�̏������t�̌o���k�ł��B �@�@���̐搶���T�N���̒S�C�����Ă������A�������s���ł��炵���Ȃ��A �@�ǂ����Ă��D���ɂȂ�Ȃ����N�������B���̔N�̒��ԋL�^�ɂ́A���N�� �@�������Ƃ�����L������悤�ɂȂ��Ă����B �@�@���鎞�A���N�̂P�N������̋L�^��ڂɂ��A�����Ă�����e�ɋ����B �@�@�P�N���A�u�N�炩�ŗF�B���D���Ől�ɂ��e�B�����悭�ł������� �@�y���݁v�A�Q�N���A�u��e���a�C�Ő��b�����Ȃ���Ȃ炸�A���X�x�� �@����v�A�R�N���A�u��e�̕a�C�������Ȃ�A���Ă��āA�����ŋ����� �@����v�A�R�N���㔼�A�u��e�����S�B��]�������߂���ł���v�A�S�N���A �@�u���e�͐�����ӗ~�������A���R�[���ˑ��ǂƂȂ�A�q���ɖ\�͂��ӂ邤�v�B �@�@�搶�̋��Ɍ������ɂ݂��������B�_���ƌ��߂��Ă������N���ˑR�[�� �@�߂��݂������Ă��鐶�g�̐l�ԂƂ��ė������ꂽ�A�Ɛ搶�͊������B �@���ی�A�ꏏ�Ɏc���ĕ����Ă����Ȃ����Ɛ����|����ƁA���N�͏��߂� �@�Ί���������B���ꂩ�疈���M�S�ɗ\�K���K�𑱂��A���N�����߂ċ����� �@������������A�搶�ɑ傫�Ȋ�т��킫�N�������B���N�͎��M�������n�� �@�Ă����B �@�@�N���X�}�X�̌ߌ�A���N�͐搶�ɏ����ȕ�݂�n�����B�����̕r�������� �@�����B�S���Ȃ������ꂳ��̕��ɈႢ�Ȃ��A�Ɛ搶�͎v�����B�������H���A �@�[���ɏ��N���K���ƁA���N�͔��ł��Ċ��搶�̋��ɖ��߁A�u�����A �@���ꂳ��̓����I�����͑f�G�ȃN���X�}�X���I�v�Ƌ��B �@�@���Z���Ǝ��A���̏��N����J�[�h���͂����B �@�@�����ɂ́A�u�����͍��Z�̑��Ǝ��ł��B�l�͂T�N���Ő搶�ɒS�����Ă������ �@�ƂĂ��K���ł����B�����ŏ��w�������Ĉ�w���ɐi�w���邱�Ƃ��ł��܂��v�� �@ �����Ă������B �@�@10�N���o�āA�܂��J�[�h���͂����B�����ɂ͐搶�Əo������Ƃւ̊��ӂ� �@���e�ɒ@���ꂽ�o�������邩�犳�҂̒ɂ݂��������҂ɂȂ��ƋL����A���� �@���߂������Ă����B �@�@�u�l�͂悭�T�N���̐搶���v���o���܂��B���̂܂ܑʖڂɂȂ��Ă��܂��l�� �@�~���ĉ��������搶��_�l�̂悤�Ɋ����܂��B��l�ɂȂ��Ĉ�҂ɂȂ����l�� �@�Ƃ��čō��̐搶�́A�T�N���̎��ɒS�C���Ă����������搶�ł��v�ƋL����Ă����B �@�@�����ĂP�N��A�������̏��ҏ͂��B���̏��ҏ�ɂ́A�u��̐Ȃɍ����ĉ������v�� �@��s�A�����Y�����Ă����B �@���S���q��̖��_�����ŃN���X�`�����ł����؏G�q�搶�����w�Z�̐搶�� ����Ă�������̎��b�ł��B �@���̘b�����߂ēǂ��A�搶�ł���ȏ�A�e�X�̐��k����̐S�𗝉����A �������ڂ��A�ǂ��Ƃ����L���Ă����Ă������邱�̂悤�Ȑ搶�ł��肽���A �Ǝv�������̂ł��B �@���̃G�s�\�[�h�͎��܁A�S�̒��Ƀt���b�V���̂悤�ɑh���Ă��āA���X�̔��Ȃ� �ޗ��ɂȂ��Ă��܂��B �@���̃G�b�Z�C�́A�����G�����w�����Ȑl���_�@�x�i�v�m�o�ŎЁj�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �@���Ɋւ�������̐l�����A�悢�����ɕς���Ă�������`�����o����c�������� �l������݂����Ǝv���Ă��܂��B
- 9��5���i�y�j�s�A�m�̂��m�Â͂g�p�̌�����ʑ�I
�@�挎���Ńh�[�p�~���̕���Ɨ��K���ʂ̑��֊W�ɂ��� ���グ�܂����B �@���X�q���̓h�[�p�~���̕���ʂ������̂ŁA���X���K���Ă� ���ʂ�����Ƃ����A���̃��|�[�g�ł�(��)�B �@�����͔]�Ȋw���V���r�V�����e���r�w�z���}�ł���!?�x�� �������Ęb��ɂȂ����A�g�s�A�m�͔]�ɂ����h�ɂ��ď����� �݂܂��傤�B �@�w�p�I�ɏؖ�����Ă������ɂ����āA�s�A�m�قǔ]�ɗǂ� �K�����͂Ȃ��A���V�����͒f�����Ă��܂��B�s�A�m���K�����ƂŁA �s�A�m���e����悤�ɂȂ�Ƃ����X�L���������g�ɕt�������ł͂Ȃ��A ���̏K�����ɂ͂Ȃ�����̗D�ꂽ���ʂ������炷�̂������ł��B �@�܂Ƃ߂Č����Ȃ�g�s�A�m�͒n����ǂ�����h�Ƃ������ƁB �ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�]�̍\�������I�ɕς�����ʂ�����A �Ƃ������Ƃł��B �@��̓I�ɂ́A�O���O�삪�\���I�ɔ��B���g�p�̒����I�Ȕ��B�� �q����i�g�p�ɂ��Ă͌�q�j�A�]���������Ȃ荶�E�̔]�� �o�����X���ǂ��Ȃ�A���]���傫���Ȃ�^���@�\��m�I�@�\�A ����I�@�\���A�b�v����A�C�n�����B���L���͂��A�b�v����̂� �w�͌���Ɍq����A�ȂǂȂǁB �@�]�̋@�\��S�̓I�Ƀ��x���A�b�v���邱�Ƃ��ł���̂ŁA �w�₾���łȂ��X�|�[�c�ɂ܂Ō��ʂ��y�ڂ��Ƃ����̂����� �{���ɋ����ł��B �@�s�A�m�̉����]�̔��B�Ɍ��ʂ������炷�̂������[���Ƃ���ł��ˁB �@�s�A�m�͗������s�����G�Ɏg���܂����A���̎g�����͍��E�� �S���قȂ�܂��B���ꂪ���ɂȂ����ɍ��x�ȍs�ׂȂ̂������ł��B ���̏�A���t�ƕ��s���Ċy�����ǂ݂�����A�Õ����ĉ��t������ ����A�����������������Ȃ�����Ă��邱�Ƃ́A���t�ŕ\���� ���̏�Ȃ�������ƂȂ̂��Ƃ������Ƃ��킩��܂��B �@�X�L���ȊO�ɔ\�́i�A�r���e�B�j�܂œ�����K�����̓s�A�m�ȊO �w�ǂȂ��Ƃ������ƂŁA����q�ׂ��g�p�̌���ɂ��ڊo�܂������ʂ� ����̂��Ƃ��B �@�h�p�͈�ʓI�ɒm�\�̓x������\���w���ł����A�g�p�͐��ݔ\�� �i�m�b����Ă�\�́j�̓x�����������w���ł��B�g�p�Ƃ́A���� �ړI�Ɍ������ēK�ɍs������\�͂ł���g�����u���I�s���́h�ƁA �����E�v�����E��������g�ɕt���ď�肭������\�͂ł��� �g�Љ�W�́h�̂��ƂŁA�g�p�̌���́A���̎�����Љ�I�����A �ǍD�ȗ����W�⌋�������A�X�ɂ͉^���\�͂��p���A����\�́A �h�p�̌���ɂ܂ł��q����̂������B �@�q���B�ɂƂ��āA�w�͂⌾��\�́A�^���@�\�����シ��ƕ����� �S�e�ނł��傤���A�g�ǍD�ȗ����W���z����h���ĂƂ��낪 ��l�ɂ͂Ȃ�Ƃ����͓I�ł���(��)�B �@���̎����ƎЉ�I�����Ƃ����_�ɂ����āA�\���C���̐搶���� �w������̗F�B�A���y�W�̒m�l�Ȃǂ����Ă���ƁA�F�y�ϓI�� ���邢�̂ŁA���̖��邳�����̎����Ɍq���錳�ɂȂ��Ă���C�� ���܂��B�g�p�x�������Ƃ����̂́g�y�ϓI�ō������邢�h�Ƃ��� ���ƂȂ̂����c�c�A�Ƃ����͎̂��̍l���ł��B �@���s�A�m���K���ƌ��ʓI�Ȃ̂��A�F����m�肽���Ƃ���ł��傤�B �@�g�p�����߂�ɂ͂T�`�W���������ʓI�ŁA�T���S�O���� ���b�X���Ō��ʂ������̂������ł��B�S�������炢�Ō��ʂ� ����n�߁A�]�̍\����ς���ɂ͂Q�N���K�v�B��͂������c�c �Ƃ����p�����ԂƂ̑��ւɂȂ邻���ł��B �@��l�ɂȂ��Ă����ʂ��]�߂�Ƃ������Ƃł�����A��l�̊F�l�� ���̎�����Љ�I�����A�ǍD�ȗ����⌋���������̂��̂ɂȂ� �\����ł���(��)�B ��k�͓e���p�Ƃ��āA�K�����̉����A�s�A�m���A���ł��K���� �]�\�������P���܂��傤�I�i�Ƃ͂����Ă����X�K���̂Ȃ��Ƃł��ˁ`�B�j �@�\���C���̑f���炵���s�A�m�̐搶���ɏK���āA�\�����L���邱�Ƃ����E�߂��܂��I �@�H����s�A�m�A�������ł����H
- 8��8���i�y�j���K�ƃh�[�p�~��
�Q�O�P�T�N�\���C���R���T�[�g�ɏo���Ȃ��������k����A��ς����l�ł����B �@���o���̕����������X�Ƃ����ǂ����t�����Ă���܂����B �@�F����̉��t����A�R���T�[�g�Ɍ����Ăǂ̂悤�ȗ��K������ׂ����A������ �{�Ԃɂ͂ǂ������S�\���ŗՂނׂ����A�Ƃ������Ƃ�[���������Ă���̂� �`����Ă��܂����B �@���y�̃v����ڎw���Ă���l�������łȂ��l���A�^���Ȗʎ����Ŏ����̍ő���� �͂����Ă���p�͔��������̂ł��B�W�����A�����̈�ԗǂ����t���I���悤 �Ƃ��邻�̈ӋC���݂��A�����Ă���l�Ɋ������ĂыN�����܂��B���N���������� ���t�ł����B �@�I����̎ʐ^�B�e�̎��A���t���I�����ʁX�����āA���N�F����̊撣��ɋ����� ���܂��̂ł����A���N���܂�}���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �@���n�[�T���ŏ��ɂł����搶���ɒ��ӂ���Ăւ���ł����l�A������Ăяo���� ���K���ꏏ�ɂ����l���A�{�Ԃ܂ŗ��K���d�ˁA�f���炵�����t�����Ă���܂������A ���C�X�C�b�`�������Ă���l�����́A��N�𗽉킷�鑧��ۂމ��t�����Ă��ꂽ �̂����������ʂł����B �@���n�[�T������肭�����Ă��܂��������ł��傤���A�{�ԂɊԈႦ�Ă��܂��A �����̏o���ɖ����ł����A�ꂢ������ĕ��䑳�Ōł܂��Ă����q�����܂����B �[�������Ȃ������l�q�ł������A�C�������ւ��A���̏o�Ԃł͌����� ���x���W���ʂ������̂͗����������Ƃł����B�\���C���R���T�[�g��� ���b�X���̎��A����̃N���X�}�X�ł͂����������s�����Ȃ��ƁA�{�l�� �N���X�}�X�R���T�[�g�̋Ȗڂ����߂Ă��C�ɂȂ��Ă���ƕ������Ƃ��ɂ� �v�킸���Ă��܂��܂����B�{�Ԃ����߂��Ȃ������̂��]�������������� �ł��傤�B �@���K�ɕt�������ė~�����Ǝ���I�ɐ\���o�Ă��āA���{�ԑO�Ɍ��Ă������q�́A ���n�[�T�����̎��M�̖��������ȉ��t�����ρA�~�X���Ȃ���A���ɐ���������S�� �����������t�����Ă���܂����B����̏�B�x�ɖ���������̂��������̂ł��傤�B ���w�ɓ����Ă����������A�Ƃ���l�Ɍ����������ŁA�B���������C�ɂȂ����̂��A ���������ʂł��B �@�g�J�ߏ��͈�ď��h���̖{���q��Ė{�̃x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă��܂��B ���_�̎w�E��������A�������肹���A�ǂ��_������J�߂Ĉ�Ă鋳����@�� �ǂ��Ƃ�����̂ł��B �@�ܘ_�A�J�߂�ׂ��_�͎����[���J�߂�悤�ɂ��Ă��܂����A���炩�ɕs�� ���Ă��邱�ƁA�܂��������ɔ�����s���ɂ��ẮA�N��ɂ����܂����A ���b�X���̒��ł�������Ǝw�E����悤�ɂ��Ă��܂��B �@�����b�X���̒��ł��傱���傱�J�߂��ē�����B���������������� �ł�����ǁA�{�ԂɌ����ďo���Ȃ��Ƃ�����w�E����A���K���A�o���Ȃ��� �������蓙�̐��X�̃n�[�h�����z������A�{�Ԃőf�G�ȉ��t���ł����B�����ق� �u�₩�Ȋ�т͂���܂���B��������͂��C���o�����邽�߂̍����Ƃ��w���� �������z�����A�������g�œ������̂�����ł��傤�B�������̗��ŏq�ׂĂ��܂� ���A���̒B�����𖡂키���Ƃ́A���y�̘g�ɗ��܂炸�l���̎��̌���Ɍq����A�� ���͎v���Ă��܂��B �@�g�撣��Ɨǂ����Ƃ�����h�Ƃ������Ƃ�����̌o���Œ͂ݎ��ƁA ���X����Ă������K�ɂ���т���������悤�ɂȂ�܂��B���K���D���� ���܂�Ȃ��A�ȂǂƂ����l�͎q���Ɍ����Č������܂ŏo��������Ƃ� ����܂���B�������A��x��т𖡂�����l�́A�g���K�͖ʓ|�L���h�� �����C���������炮���̂ł��B �@�K����������Ƃ��A���X����Ă���ꍇ�Ɗ��ł��ꍇ�̌��ʂ̈Ⴂ �ɂ��āA�]�Ȋw���V���r�V�������̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �@�u�y����ł�������͂�����ʓI�ł��B�h�[�p�~�����o����� �i��т������Ȃ���s���c�j�łȂ��Ɗ�{�I�ɂ͌��ʂ͖]�߂Ȃ�����ł��B �������A�q���͌��X�h�[�p�~���̐��l�������̂ŁA�P���Ǝv���Ď��g��A ���ł����g�����ǂ��Ǝv���܂��B�v �@�q���͌��ł�����������ǂ��E�E�E�A�̂������ł����A�B�����A��т� �m������ōs�����K�́A�����ʓI�Ƃ������Ƃł��I �@�h�[�p�~�����h�N�h�N�o����Ԃŗ��K���鎟�̃R���T�[�g�� �y���݂ɂȂ��Ă��܂�����I
- 7��4���i�y�j��@���������Ďq���̋�����I
�@�q�������̋���A���{�̏����ɂ��čl���鎞�A ���F�l�c�B�A���a���̑��S��`�������쎵������ ���w�C�̓s�̕���x���v���o�����Ƃ�����܂��B �@���쎁�́A�n���C���E�𒆐S�Ƃ��郈�[���b�p�A �I���G���g�i��Ƀg���R���Ӂj�j�������Ă������ �ł��B�����a������N���A�h���ɂ߂����R�A���� ����Ɏ������o�܂Ȃǂ��A�����m�̐����I�ȋ삯�����A �푈�̌����Ɛ헪�A�܂��o�Ϗɗ��߁A�Y�傩�� �@�ׂɕ����W�J���Ă��܂��B �@�����̒�`�������̂悤�Ɍ��肵�Ă��Ȃ����̐� �i�����ł�����ɍ�����ύX���悤�Ƃ��鍑������ �܂����c�j�A�͂����������̍��������R�Ɋg�債�� ���܂����B���쎁�̒���ɂ́A���y������Ȃ����߂� �F�X�Ȓm�b���A�Ƃ��납�����ɎU��߂��Ă��܂��B �@�l�X�Ȓm�b�̒��ł��A�w�C�̓s�̕���x�ɂ����� ���M���ׂ��́A�����ێ����鍪�{�ƂȂ�o�ϊ����� ���ِ��ł��B �@�M���������K���Ƃ��ČN�Ղ��A���̒n�ʂɊÂ� ���ƂȂ��A�Ⴂ���A��ʍ����ƈꏏ�ɑD�ɏ��f�Ղ� �s�����l�Ƃ��ē����K��������܂����B�����i���O�[���j�� �Y��ł�����œs�s���\�z�����A�����ʂ�g�C�̓s�h ���F�l�c�B�A�ɂ́A�C�Y���ȊO�̎����͂Ȃ��������� �ł��B �@���[���b�p������W�߂��i�����I���G���g�ɑD�� �^��Ŕ���A�t�ɃI���G���g�Ŏd���ꂽ�i�X�� ���[���b�p�ɉ^��Ŕ���A�Ƃ����f�ՋƂŐ��藧���Ă��� ���ł����B �@�C���̒ʂ肪�ǂ��Ȃ�悤��������Ȃ���� �������Ă��܂����y���A�������Ƃɂ���Đ������A �������~�߂�Ǝ���ł��܂��C�̒��̋��̂悤�� ��������������č����ێ����Ă���c�A����Ȉ�ۂ� �܂��B �@�������Ȃ����Ƃ����Ǝv���o���̂͂������{�B �@�킷��ΐΖ���V�F�[���K�X�A�z�����o�āA �����ɔ��邱�ƂŊO�݂��҂��鍑�ƈႢ�A���{�� �O�݂��҂��ɂ́A�����̐l�B���~�����鐻�i�� �T�[�r�X�����o���A�����Z�p���K������K�v�� ����܂��B �@�����{�̊w�Z�ŁA����ɗ��n�Ȗڂ̋�����搂��� ���܂����A�F���J������Ɠd�Ɏ���l�X�Ȑ��i�A �R���s���[�^�[���̐V�V�X�e���̑n�o�ȂǁA�l�X�� ���i��A�C�f�A�͗��ȓI�m�����y��ɂȂ��Ă��܂�����A �������ׂ�����ƌ����܂��傤�B �@�V�����V�X�e�����l���邱�Ƃ��ł��铪�]�̈琬 �i��G�c�Ȍ������ł����j�͏d�����ׂ����Ƃł��B ��z�V�O�Ȕ��z�͂r�e�����A�܂����j��ÓT��ǂ� ���ƂőM�������m��܂���B���t����g�������n�� �����ܘ_��ł��B �@���ƂȂ��L���Ȃ��̓��{�ŁA�̂�т苳����āA ���ƂȂ��A�E���A�l���݂ɐ�����\�\���ɂ������c�s�� �e��̎Y�Ƃ��h���A���̓s�s�ɔ�ׂďA�E��������A �l�X������Ȃ�ɖL���\�\�A����͗L����Ƃ�����ǁA �悭�l���Ă݂�ƂƂĂ��댯�Ȃ��ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�� �̂ł��B �@�w�a�������\���C���x�̃N���X�ŁA�O����̎q�������� �ڂ�����̂���`�������Ă���ƁA�q���̋z���́A������ �x�����ɂ�����������܂��B �@�l�X�Ȏh����^���A�D��S�̉��L���Ă�����ƁA �ǂ�ǂ�F�X�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����܂��B �@������������̂��Ă�����Ɖ̂����ɁA�������� ������Ɨǂ����A�b�������Ă�����Ƃ悭�b���悤�ɁA �{��ǂ�ł�����Ɩ{�D���ɂȂ�A�Ƃ�������ɁB ��l�Ƃ��ė�O�͂���܂���B �@�s�A�m�⃔�@�C�I������ʂ��āA���������ł��悢���� ���K����K�������Ă�����ƁA�l����j���̐����� ����܂����A���w�Z�R�N�����炢�ɂȂ�ƁA�y��̗��K�� ��������̂�������O�Ǝv���悤�ɂȂ�A����ɏ��� �ł���̂��ł��Ă��܂��B �@���y�̋Z��ςݏグ�āA���ꂱ���C�O�Ŋ���i�O�݂��҂���j ���y�ƂɂȂ铹���J���Ă������Ƃł��傤���A���X�������Ƃ� �J��Ԃ��K���Ƒ̂��ł���ƁA���̌�ǂ̂悤�ȕ���ɐi��ł� �����̗͂Ő����Ă�����悤�ɂȂ�܂��B�ςݏグ�Ă������Ƃ��A ���鎞���瑝������A�ڊo�܂����G�l���M�[�ɕω�����悤�ɂȂ� ����ł��B �@���̍������������o�������Ȃ��ꐶ���߂�����Α傢�Ɍ��\�ł����A �q���͈�ĕ��Ŏ��Ă�͂��[���ɔ����ł���悤�ɂȂ�̂ł�����A �����ɁA��@���������āA����̏[�������N���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
- 6��6���i�y�j�̂̂����͏��ɂ��������̂ł��ˁc�c
�@���������Ċ撣��̂ɂ���������\�\�A�挎�̌o�����瓾�����P�ł��B �@�d�������A�c�����������q����āA���F��S�̕�������삵�Ă������� �g�̂��ߖ��グ�A���㔼�g�ƉE�����g���P�N�Ԗ�Ⴢ������Ƃ����������A �C�^���A���w����A���������̖������M��ŊԔw���j�A�łW�����ԓ����Ȃ����� ���Ƃ����������A��w�@�O�ɓD�ꎮ�ŕ����������������I������r�[�A �������A�������A�A�����ɂ�����Ɋ|���������A�����ǂ߂��s�A�m��e�������Ƃ��Ȃ� �������Q�̏I���Ɉ����č�������ɍ��i������������J�ŗ����オ��Ȃ��Ȃ������A ����������Ɛg�̂��ߖ��グ��̂͊��x���o�����Ă���͂��Ȃ̂Ɂi���̕a������Ă� �S�R�y�����Ȃ��ł��ˁI�j�A�A���߂���ΔM����Y���̌��ʂ�A���̂��炢���v���낤�ƁA �̂̂��Ƃ͂�������Y��簐i���Ă��܂��̂͂ǂ��������̂��Ɣ��Ȃ��邱�Ƃ�����ł��B �@�K�������Ǐ�����Ղ��\�ʂɏo�Ă����̂ŁA���������E�Ǝ��o���A����ŃZ�[�u���� ���܂Ő����Ă���ꂽ�����ł�����ǁB �@�葫����Ⴢ��悤���A�̂̉����������ǂŒɂ��낤���A�撣���������ւ̌M�͂Ǝv���A �ʒi���܂ł͎d���Ȃ��Ƃ��߂����Ă����̂ł����A����͓ˑR��̍����������Ȃ��Ȃ��āA ����ɐS��V���b�N���Ă��鎩���ɋ�������܂����B�ォ��A���܂Ōq�����Ă��� �����̐��т������ʂ܂܁B���y�ƂƂ��Ă̊����𒆐S�ɐ����Ă���̂ł͂Ȃ��̂ɁA�������� ��������Ȃ��Ƃ������|�́A�z�����Ă����̂�肸���Ƃ����Ɛ[���V���b�N�ł����B �@�̂�т�ł��鎞�Ԃɍl���Ă���̂́A����̐l�B�����K���ŐS�n�悭�߂����ɂ� �ǂ�����悢���A�Ƃ������Ƃ���B�\���C���̐��k�������y�������y���w�ׁA �y���������łȂ����͂����シ��i���͎u�]�Z�ɍ��i����A�R���N�[���ɒ��킷��l�ɂ� ���܂���j�悤�A�Ί�Ɗ�]�ł����ς��̋�Ԃ������Ă��������Ƃ��A�搶������薾�邭 �ӗ~�I�Ƀ��b�X�����ł���悤�o�b�N�A�b�v�������Ƃ��A�Ƃ̒��ł́A�y������b�������ς��� �����������̂������ď����₦�Ȃ��悤�ɂ������i�Ƃ͂������t���Ăđ��q�������Ă�����X �ł͂���̂ł����c�j�Ƃ��A�����ȊO�̐l�̍K�����l���Ă��邱�Ƃɉ��̕s���������Ȃ��̂ŁA �v�X�Ɏ����̂��Ƃ�U��Ԃ邱�ƂɂȂ��Ă݂���A���т������Ȃ����Ƃւ̑r�����̑傫���� ���R�Ƃ����̂ł����B �@�̂��̂����Ƃ͎��̐l���C�Ƃ��̂��̂ŁA�N�X�F�X�ȋZ�p���l�����ςݏグ�Ă������̍�i�ł��B ���ς��̍Œ��̂P�R�̎��A�J�X�J�X�������Ń��b�X���ɒʂ��n�߁A�R�O���N�|���č��̉̂����� �l�����Ă��܂����B �@����͂P�O�����Ŏ��R�������A�܂����̏�Ԃɖ߂����̂ōK���ł������A���̂܂܉��Ȃ�������A ���ꂩ��ǂ������Ă��������A�S�̂��ǂ�����ǂ������Ă��������A�Ɛ^���ɍl���܂����B �@��y�����ɂ��Ă������_���������A���̌��ۂ��ǂ���������悢�̂��낤���ƁA�l�����������ꂽ�悤�� �P�O���Ԃł����B �@�����w���w���Ɛ����Ă���悤�ł����A���ɂ͐^���ɐl�����l���鎞������̂ł���B �@�{�l�ɂƂ��Đh���Ďd�����Ȃ����Ƃł��A�Â�������Ă���Əꂪ�Â��Ȃ�A����ɂ悢�e����^���Ȃ��A �Ƃ������Ƃ��o�����܂����B����̊F������ꏏ�ɈÂ��Ȃ��Ă��܂����̂͐\����Ȃ����Ƃł��B �@�P�K�����ĕa�@�ɍs���Ȃ���ƁA��؍k���Y���ƁA���D�A����G�q���Ƃ̑Βk��ǂƂ��A����Ȃ��Ƃ� �����Ă���܂����B �@����G�q���� �u�P�K�������̂�������a�@�ɍs���đ��������Ȃ����B�ɂ��̂͂��Ȃ������ł͂Ȃ��A�Ƒ������̐l�B�A �@�F�������悤�ɒɂ��̂ł�����v�ƁB �P�l���a�C�ŋꂵ��ł���ƁA���������Ă���l�����F�������悤�ɋꂵ�݂������Ă��܂����̂Ȃ̂ł��ˁB �@�N�ł������ł��傤����ǁA�a�C�ɂȂ����A�̂������Ȃ��A�Ƃ������R�ł��������d���͋x�߂���̂ł� ����܂���B �@���Ԃ������ċx�������A�̂̂��������ɂ��Ă����������̂ł��B����̕��X�̉������Ǝv������ ������ꂽ�T���ł����B �@ �@��������ǂ��Ȃ�S����̏Ί�ŊF��������}���ł������ł��I
- 5��2���i�y�j�����s�A�m���c�cFAZIOLI !!
�g�]�����Œ肵�Ă��镪��ŐV���n���J��|�|�B�h �@���t�ŏq�ׂ�Ƃ�����Ƃ���ȕ��Ȃ̂ł����A���͊�d�ɂ��d�Ȃ�Œ�ϔO���� ����̈̐l�A�p�I���E�t�@�c�B�I�[���������Љ�܂��傤�B �@�g�t�@�c�B�I�[���h�ƕ����āA���I�Ǝv���l�͗]���̃s�A�m�t���[�N�B �@�C�X���G���̃e���A�r�u�łQ�O�P�S�N�ɊJ�Â��ꂽ�w���[�r���V���^�C���R���N�[���x �ł́g�����h�ň���L���ɂȂ����s�A�m���[�J�[���ł��B �@�C�^���A�Ő������Ă������A����ɒu���s�A�m�������^�����邽�߃s�A�m�V���b�v�� �����^���Ƃ�����܂��B���{�ł�YAMAHA��KAWAI�����{�̊e�s�s�ɐ��V���b�v�� �W�J���Ă��āA�s�A�m�ƌ����Q�̃��[�J�[�̓Ɛ��ԁB���ł��������̃s�A�m�� �W�����Ă���s�A�m�V���b�v������܂����A�����ɒu����Ă���s�A�m�����Ђɗ��܂��� ���܂��B �@�C�^���A�̃s�A�m�V���b�v�ŋ������̂́A�P�O�O�؋߂��q�ɂ̂悤�ȓW���{�݂ɏ����� �ƒu���Ă���s�A�m�̃��[�J�[�����A�u���Ă��鐔��������Ă�������푽�l���������� �ł��B�C�^���A�ł�����C�^���A���̃s�A�m������܂������A���h�C�c���́A�����m��Ȃ� ���[�J�[�̃s�A�m�������u���Ă���܂����B �@���{�ł̂Q�僁�[�J�[�Ɛ��Ԃ����m��Ȃ������̂ŁA���E�ɂ͂���ȑ�R�̃s�A�m���[�J�[�� ����̂��ƐS������܂����B�Ԃ̃��[�J�[���e�s�������Ƃɑ��݂���悤�ȋ����ł��B �i���ɎԂ̃��[�J�[�̓C�^���A�ł����{�ɒm���Ă��鐔�Ђ����ł����E�E�E�j �@�s�A�m�͂P�U���I�ɃC�^���A�l�N���X�g�[�t�H�������������y��ł��B�s�A�m�i�㉹�j ����t�H���e�i�����j�܂ʼn��ʂ߂��邱�Ƃ��ł���y��Ƃ������ƂŁA�C�^���A�ł� �g�s�A�m�t�H���e�h�Ƃ����̂��������́B�Ȃ��A���ۂɂ��̂悤�ɌĂ�Ă��܂��B �@���̂Ƃ��Ă͒�������̂ł��傤���A�����ł͑O����������āg�s�A�m�h�ƌĂ��̂� ���ʂł��ˁB �@���̂S�O�O�N�ɋy�ԃs�A�m����̓`�������C�^���A�ɁA�P�l�̃s�A�m����҂��o�����܂����B ���ꂪ��ɏЉ���p�I���E�t�@�c�B�I�[�����ł��B �@�t�@�c�B�I�[�����́A�y�[�U�����y�@�Ńs�A�m�̊w�ʂ����A�m�[�x����҂𑽐��y�o ���Ă��鍑�����[�}�E���E�T�s�G���c�@��w�ŋ@�B�H�w�̊w�ʂ���̂��Ă��鑽�˂Ȑl�B �@�P�O�O�N�ȏ�̗��j�����V�܃��[�J�[���w�ǂ̃s�A�m�����ƊE�A�V�Q�҂����荞�ޗ]�n���A �����̋P���������v�������Ǝv��ꂽ���̋ƊE�ɁA�P�X�W�P�N�A�t�@�c�B�I�[�����͎��Ƃ� �Ƌ�[�J�[�̈������荞��ł����܂����B �u���܂ł��s�A�m���ς��Ȃ��Ȃ�Ă��������B�i�����Ȃ��Ɓv �Ƃ����v���ŁA�P���P�����N���A�ȁw�I�y���̉̐��x�̂悤�ȉ��F��Nj����s�A�m����� �n�߂܂����B �@�Ő�[�̉����H�w����g���v���̂��猩�������Ƃ͌����A�`�[�N�E�}�z�K�j�[�Ȃǂ� ���������������Ƃ̉Ƌ�[�J�[�łؘ̖g�f�ނ̌����̑��A�����R�����������܂ł� �R�N���|����ȂǁA��ԉɂ�ɂ��܂Ȃ����g�݂��d�˂���A�Ō�͎����Œe���Ďd�オ��� �`�F�b�N����Ƃ����A�H�w�m�ƉƋ�E�l�A�����ăs�A�j�X�g�Ƃ��Ẳp�m���Ïk�������̏�M�́A ����܂łɑ��݂��Ȃ������s�A�m��グ���̂ł����B �@�`���ŏq�ׂ��w���[�r���V���^�C���R���N�[���x�ŁA�t�@�C�i���X�g�U�l�̂����T�l�� STEINWAY�ł͂Ȃ�FAZIOLI��I�ԂƂ����ٗ�̎��ԂƂȂ������Ƃ��j���[�X�ɂȂ�܂����B �@FAZIOLI�͂Q�O�P�O�N����s�A�m�R���N�[���̍ō���V���p���R���N�[���ŁA�Q�O�P�P�N����� �`���C�R�t�X�L�[�R���N�[���ł��w�����s�A�m�x�Ƃ��č̗p����Ă��܂��B �@�R�S�N�Ƃ����Z���N���ŁA�����^�����s�A�m�̐���Ɏ��g�݁A�V���n���J�āA ���܂��ɐ��E�ō���ɓo��߂悤�Ƃ���l��������ɂ���Ƃ����̂́A����̊�Ղ� �v���ĂȂ�܂���B �@�m�荇���̃s�A�m�̐搶�̂����FAZIOLI���̃s�A�m������A���̉��F�ɂ��܂��ܐe����ł������ƁA �܂��A��w�̐�y�A�쌴�L�q���v���f���[�X���Ă��镟�䌧���l�s�̃z�[���ɁA��͂�FAZIOLI F308 �i���{�ɂ܂��R�䂵���Ȃ����s�����R�����z�����E�ő�̃s�A�m�ŁA�S�{�ڂ̃y�_���͉��F��܂炷���ƂȂ� ���ʂ����点��Ƃ����t�@�c�B�I�[�����̔����i�ł��I�j���ݒu����Ă��邱�Ƃł��̃s�A�m�̑��݂� �m���Ă͂����̂ł����A�S���P�R�����s�̎G���wAERA�x�Ƀt�@�c�B�I�[�����̋L�����f�ڂ���Ă��āA �o���Ȃǂ�m���R�������������̂ł����B �@�Q�O�P�R�N�̔N�Ԑ����䐔�͂P�Q�T��A���P�O��قǂ̃y�[�X�Ő��삳��Ă��镶���ʂ����s�A�m�B �@����P�l�̃C�^���A�l�̗��z�́ASTEINWAY�����ł���s�A�m�E�ɐ����������N�����A�V���Ȑ��E��� ��낤�Ƃ��Ă��܂��B �@ �@�P�l�̈ӎu�͊�����ʂ��E�E�E�B�����Ȑ������ł��B
- 4��4���i�y�j�Đ�����t�Aࣖ��B
�@�tࣖ��B������C�ɖ��J�ɂȂ�A�Ⴊ�~��ʂ܂t������Ă��܂����B �@���N�͎��������������߂ł��傤���A�~�̊ԂQ�x�M���o���܂����B ��x�ڂ̔��M���͋x�߂Ȃ������̂ŁA�M���o���܂d�������āA�܂� ������Ԃǂ�܂����B �@�̗͂̌��E�܂Ŏ��ɕt�������Ă��܂��Ƃ����悤�Ȏd���̎d���́A �N����N��Ȃ̂Ŏ~�߂Ȃ���Ǝv���Ȃ�����A�Ƃ肩����͂��߂�� �~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����i�����j�B �@���k����͖ܘ_��ł����A�|��Ă��܂��Ƒ��q�̖ʓ|������l�� ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂Łi�v�͖k�C���Ζ��I�j�撣���Č��C�ł��Ȃ���c�A �Ǝ����Ƀ��`�ł��X�ł��B �@��������đ��l�̂��q�l�����̎w�����Ă���̂ŁA�����ꖽ�𗎂Ƃ� ���Ƃ���������A�����Ǝ����̎q�͒N�������S���ӈ�ĂĂ����c�Ƃ� �v���Ă���̂ł�����ǁc�i��C�����j�B �@���͂�������ȕ��A�����Ǝ���悢�Ǝv���̂ł����A ����Ȃ��Ƃ��낪�\���C���̗ǂ��Ƃ���Ȃ̂ŁA�����Ƃ��̂܂� �����̂ł��傤�B�̂����܂ł������Ƃ��肤���X�ł��B �@���I����đ�����O��`���Ă݂�ƁA�Ԃ͖��J�A�V�͉萁���n�߁A �����̖����������܂��B �@�Q�N�O�A����̒�ɐA�����A�I�_���͂܂��t��t���Ă��܂��A������ �t���萁���Ă��Ȃ��n�E�`���J�G�f�̎}�͐Ԃ��F�Â��A�H�̐^���Ԃȗt�� �A�z�����܂��B �@����A�����I�g�R���E�]���̗͗t���T���T���ƕ����r�����A�A�Y�L�i�V�� �J�}�c�J�͐������ɗ��߉萁���̎���҂��Ă��܂��B�͂�̂悤������ �������z�ԁA�A�i�x�������킢������o���n�߂܂����B �@�Â������Ƃ���̂��ꂽ���ƂŁA�אڂ���R���،i�ƂȂ�A�R���̍��� �`�߂��g�䂪�ƂʼnԌ��h���ł���悤�ɂȂ�܂����B�������Ƃ��A ���R���g�����l�h�ƘJ���Ă���Ă���悤�ŁA�ЂƂƂ��̍K�������݂��߂Ă��܂��B �@�T�O�N�������Ă����(�܂��T�O�ł͂Ȃ�����ǁc)�A�Ƃ̎�����莄�̕��� �N���Ƃ�A�c�������猩����Ă����ߏ��̋����ƁX������n�߂܂����B �V���ȏZ�����V�����Ƃ����Ďn�߂Ă��܂��B�����ꂽ�i�ς��ς��̂� �����߂�������ǁA�g�����Ȃ�n�߂��t�ɁA�g���J���ƐV�z�H���̒Ɖ��� ��������̂͂Ȃ�Ƃ������Ȃ��u�₩�ȋC���ł��B �@���{�ɂ͍Đ�����g�t�h�Ƃ����G�߂�����̂��ǂ��ł��ˁB���R���烊�Y���� �^�����銴�������܂��B �@�����̌܍s���Ɋ�Â��l��������A�l���ɂ��S�̊�������A�ƁA����ǂ� �G�b�Z�C�ɏ����Ă���܂����B �@�S�̊��Ƃ́A�t�A��āA���H�A���~�i���͌��Ă̌��A���l�g���낤�Ɓh�̍��j�B �@���ʂ͂R�O���炢�܂ł��t�A�T�O�܂ł���āc�ƕ����Ă���悤�ł����A �l�������~����n�܂��Ĕ��H�ŏI���Ƃ���l����������悤�ŁA�O�����͏C�Ƃ̓~�A �����Œ~�������_�͂ƋZ���A�₪�ĉ萁���̗͂ƂȂ�A��ւ̉Ԃ��炩���A�[������ ����̏H�Ől�����I����c�A���ꂼ���z�̐������ƌ����܂��ˁB �@���̎��X�̗̑͂���ɋt��킸�ɓw�͂𑱂��A���R�̃��Y���ɓY���Đ����邱�Ƃ� �ł�����悢�l���𑗂�邱�Ƃł��傤�B �@�l���̎l�G�Ƃ͕ʂɁA���N�J��Ԃ����l�G�Ƃ��琁B���̏z�̂��A�ŁA �ǂꂾ���p���[��^���Ă�����Ă��邩�v��m��܂���B �@�V�w�����n�܂�A�\���C�����V�������Ԋ����X�^�[�g���܂����B �@�V�����y���y�̃��b�X�����n�߂����I�Ǝv���Ă���������ɂƂ��ẮA �܂��Ɏn�܂�̋G�ߓ����ł��B �@ �@�\���C�������҂̂W�O���́A���k����⌳���k��������̂��Љ�ɂ����X �i�Q�O����HP���䗗�ɂȂ��ē������ꂽ���I�j�B�\���C���̎w���@��ǂ��Ɗ����� ������A�m�l�����Љ��������̂́A�w���҂Ƃ��ĉ����ւ炵�����Ƃł��B �@�F�l�����M�������Ă��Љ�Ă���������w���Ƒ̐������ꂩ����ێ����A �X�ɗǂ������ƂȂ�悤�A�w�͂��Ă��������Ǝv���܂��B �@�V�w���A�V���ȋC�����Ń��b�X�����X�^�[�g�����܂��傤�I�@�@�@�@�@�@�@
- 3��7���i�y�j�������t�̃j���[�X�^�u���呲�v�͕���ɂȂ�
�@�������t���܂������Ă��܂����B���i�̃j���[�X�����X�͂��܂��B ��N�H���獇�i�҂����o�ł��B �@���������A�\���C���̐��k�ʼn���ɐi�w�����^�j�q�A���q���� �g�s�A�m��U�j�q�P���h�̌���ɃG���g���[���A�������i���܂����B �����O�Ƀ\���C���Ƀ��b�X���ɗ��Ă����̂ł����A�_���r�b�V������ �w�̍����D�N�́A�S�O�{�ȏ�̔{���������˔j�i�ނ̎ԍ��� ���̕ӂ������̂ł����Ƒ��������m��܂���c�j�A�ꐶ�s�A�m�� �e���Ă�������Ղ���Ƃ������Ƃ��b�܂ꂽ�E�ƂɏA�����ƂɂȂ� �܂����B�{�l�͂��̗L����������Ă��邩�ǂ����^��ł����A �^���Ɍ����Ɏ��g��ł����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �@�P�I�N�^�[�u���͂��Ȃ������Ȏ�ŁA��������s�A�m�n��R�[�X�� ���i�����̂͌I���M仔T����B�Жڂ��Ύ��ŗ��ڂň�x�Ɍ��邱�Ƃ� �ł��Ȃ��Ƃ����n���f�B���������z���Ă̍��i�ł��B �@�{���Ɏ肪�������āA���̏㍜���ł��w���J���Ȃ����߁A�I�N�^�[�u�� �o���o���o�Ă���Ȃ͖����A�o�b�n��[�c�@���g�A�V���p���́A���� �p�b�Z�[�W�̋Ȃ���L���ɉ��y�I�ɒe�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���i�� ������܂����B���ȋ��Ȃ͐�ɂ��Ȃ��A�Ƃ�����ȂȂƂ��낪������ �̂ł����A�ł��Ȃ��Ǝv������ł������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ɏ]���A��Ȃ� �C�����������A���Ȃ��Ƃɂ����߂�悤�ɂȂ�܂����B �@���̌o���͔ޏ������ꂩ��̐l�����Ă䂭�̂ɉ����̕ɂȂ� ���Ƃł��傤�B �@�ꏏ�Ɋ撣���Ă�����]�L�������������w�A�����Ȃɓ�Ȃ����i�I �Q�l�Ƃ��A�����s�A�m�̉��t�����łȂ���Ȃ�A�����W�Ȃǂ��ł��镝�L�� �s�A�j�X�g�ɂȂ肽���A�Ƃ��������ӎu�������Ă������߃s�A�m�n��R�[�X�� ���܂����B�s�A�m�Ȃ̘g���z�����l�X�Ȍo����ς݁A���y�ƂƂ��� �H�����Ă����Ăق����Ǝv���܂��B �@�\���C���u�t�̏a��i�^���搶���A���t�����A�����Y�p��w��w�@ ���m����ے��i�s�A�m��U�j�ɍ��i���܂����B �@��w�@���A�E�܂ł̍��|���A�ƔF�����Ă���l�������悤�ł����A �����Y��̑�w�@�͓�ւł��B���m����ے��s�A�m��U�́A��N���i�Җ����A ���N�U�����A�Q���̍��i�ł����B�s�A�m���t�Ƌ��ɁA�����O�����q���Z���� ���̓��]�ŁA���Ė����s�A�m���t�̈�̌��������A�㐢�Ɏc��_�������̂��� ���炢�����Ǝv���Ă��܂��B �@����A���y�̗F�Ђ��o�ł����w�u���呲�v�͕���ɂȂ�x�Ƃ����{�� �w�����܂����B���x�m��s�Ől���S���������A�E�̃X�y�V�����X�g�� �����쉹��̏A�E�ۂ̍u�t�ɂȂ�A�����쉹��𑲋Ƃ���(����)�l��ΏۂɁA ��ʊ�ƂɏA�E�����Ă�����т����V���ł��B �@�@�w����o�ϊw���𑲋Ƃ����S�Ă̐l���i�@�����ɍ��i��������F��v�m�� �A�i���X�g�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA����𑲋Ƃ����l�S�Ă����t�Ƃ≹�y���@�A ���y���t�ɂȂ�Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����A�ƒ�N���Ă��܂��B �@��ʊ�ƂɏA�E����ۂ̉��呲�́g����h�A����́A���b�X���Ő搶�Ƃ� �ڐG����ʂ̊w���Ƃ͒i�Ⴂ�ɑ������߁A�N���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V������ �Ȃ�Ă��邱�ƁA���Ԍ���E�g�����Ȃ݁E��V���@�����܂�Ă��邱�ƁA �����邱�ƂɊ���Ă���̂ł߂��Ȃ����_�͂������Ă��邱�ƁA������������ �y�������Ă���l�ɑ���������A�s���┭�z�ɂЂ�߂��������Ă��邱�ƁA �������ł��B���̂��߈�ʊ�Ƃ̏A�E�ɂ͓K�C���Əq�ׂĂ��܂��B �@�g���t�Ƃ�w�Z�̐搶�ɂȂ�̂͏��߂�����߂܂��傤�h�A�Ƃ����b�̗���� �Ȃ��Ȃ������[���a�V�ł��B �@���y�̎d���ɏA���Ȃ����呲�҂������ƌ������A���y�̐��E�ŏ��҂� �Ȃ邽�߂̔錍�������Ă��܂��B���ȃ}�l�W�����g���ł��A���t�ȊO�� �X�L���̍����l�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ������ł��B���t�ȊO�ɉ������l�ƈႤ ���̂������Ă��邱�Ƃ�ɂł���l�ɂȂ邱�Ƃ��̐S�Ȃ̂������ł��B �@�������͂��̏����g(�H)��ڎw���Đ����Ă����̂ŁA���߂��瑲�Ƃ����� ��ʊ�ƂɁc�Ƃ�������E�߂�̂͗]��Ɉ����߂���C�����܂����A ���������l���������l���ʂ̐��E�������Ă��āA�V���n���J���A �Ƃ������Ƃł��傤���B �@�O�q�����l�̑��ɂ��A����o�ϑ�w�������Z���ʉȌ|�p�R�[�X(���y)�� �Ԑ��A�����쉹��̃T�N�\�t�H�[���Ȃɓc���ʕc�����i���܂����B ���邢�����Ɍ������Đ��i���d�˂Ă����܂��傤�I
- 2��7���i�y�j�撣��ΕK���ł���悤�ɂȂ�I
�@�y�킪��肭�e����悤�ɂȂ�Ȃ��A���̐��т��オ��Ȃ��A �d���̐��ʂ��o�Ȃ��A�����ɂ͍˔\��������Ȃ����낤���A �����v�������Ƃ�����l�͂��܂��B �@�y���V���o�j�A��w�S���w�����A���W�F���E���[�E�_�b�N���[�X���́A ���N�ɘj�錤���̒��ŁA�����҂����ʂ��Ď�����\�͂������܂����B �@���m�́A�Q�V�̎��Ɍo�c�R���T���f�B���O�̎d�����璆�w���t�ɓ]�E ���܂����B���w���t�Ƃ��ċΖ����钆�Ő��k�̂h�p�̐��l�Ǝ��ۂ̐��т� ��v���Ȃ����Ƃɒ��ڂ��܂����B �@���̌��w�@�ŐS���w���U�A�l�X�Ȋ��̒��œ���ۑ�ɒ��킷�� ��l��q���B���������n�߂܂����B �@�@�A�����J�̌R������w�Z�s�E�G�X�g�E�|�C���g�E�~���^���[�E�A�J�f�~�[�t �A�ߍ��Ȍ���œ������t�@�B��ʊ�Ƃ̃Z�[���X�S���� �C�s�i�V���i���E�X�y�����O�E�r�[�t�̐��k�����A���̂S�̃J�e�S���[�� ������l�������g�P�Ԃ̐����҂ƁA���̗��R�h�Ƃ������ʂ̃e�[�}�Ŋώ@ ���܂����B �@���������҂������Ă������ʓ_�A����́A�m�\�̍����A�O���̗ǂ��A �g�̔\�͂̍����A�Ƃ�����V�I�Ȃ��̂ł��A�w���A�Ƒ��̏����A�Ƃ����� �����V�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��A�����ɑ����M�A�����ړI��B�����邽�߁A �g�����I�p���I�w�́h���ł��邱�ƁA���ꂪ�B��̋��ʓ_�������̂ł��B �@���m�͖���ڕW�Ɍ������Ė��������R�c�R�c�Ƃ���𐔔N�Ԃɘj�薲���� �Ȃ��Ċ撣�葱���邱�Ƃ��A����ڕW�������̂��̂Ƃ���A�Əq�ׂĂ��܂��B �@�u���Ȃǂŕی�҂�搶���ɂ��̘b������ƁA �u�����I�p���I�ɓw�͂��邱�Ƃ��������A�Ƃ������Ƃ͂킩�邪�A �@�����I�ɔM�S�ɕ����Ɏ��g�ގq���Ɉ�Ă�̂ɂ͂ǂ�������悢���H�v �u�ǂ�����Ύq�������̃��`�x�[�V���������������邱�Ƃ��ł���̂��H�v �Ǝ������Ƃ����܂��B���m���A �u����ɂ��Ă͐���������܂���B�v �Ɠ�����Ɖ��͏��ɕ�܂�邻���ł����A���̌�A�X�^���t�H�[�h��w �L�������E�h�D�G�b�N���m�����Ă���w�O���[�X�}�C���h�E�Z�b�g�x�Ƃ��� �l���������p���A�q���B�ɁA�]�ƒm�\�̔��B�ɂ��ė\�ߊw�K��������A �m�\�͐��܂���ł͂Ȃ��A���킵�����邱�ƁA�w�͂��邱�Ƃɂ���� ���ł��L�����Ƃ��\�ł���A�Ƌ����Ă�����������������ƁA �q�������͓��ɑ��Ď��s�����ꂸ����i��Œ��킷��悤�ɂȂ�A�Ƃ��� �������ʂ�������邻���ł��B �@�撣��ΕK���ł���悤�ɂȂ�Ƃ��炩���ߒm�点�Ă����ƁA�撣�郂�`�x�[�V������ ���܂�A������ێ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�����ɒ��킷��O�ɁA�g�����I�p���I�ɓw�͂��邱�ƂŐ�����h�� �������Ă���q�Ƃ����łȂ��q�ł́A�w�͂���ߒ����A�����Č��ʂ� ����Ă���̂��Ƃ�����A���猻��ɂ���l�ɂ͐���q�������ɘb���� �����Ăق����l�����ł��B �@���N�A���y����̐��E�Ő����Ă���ƁA���ʂ̔\�͂Ȃ̂Ɂg�����I�p���I�ȓw�́h�� ���������ʁA�_�̈�I�Ǝv����悤�ȃ��x���ɂ܂œ��B�����������Ă��܂������A ���������ɂ͂������ʂ̎q�����Ǝv���Ă����q���A���̐l�B�Ƃ͔�ׂ悤���Ȃ��ق� ��B���Ă��܂����Ƃ�����������Ă��Ă��܂��B�ł����炱�̔��m�̌����Ă��邱�Ƃ� �S�������Đ������̂ł��B �@�K�^�Ȃ��ƂɎ��͂��̂悤�ȍl��������������e�Ɉ�Ă��܂����B���y�� �˔\������������ł͂Ȃ��������ɁA��͐��y���u�������̂ł������A �u�w�͂�����������ɂȂ�v�Ɩ����̂悤�Ɍ����Ă��ꂽ���A�ŁA���̌��t�� ��������M���A�w�͂𑱂��邱�Ƃ����͂ł���l�ԂɂȂ�܂����B�{���͊y�V�I�� �`�������|�����Ȑ��i�Ȃ̂ŁA�����Ȃ����̂���̌��t�̂��A�ł��B �@�ꂪ�S���Ȃ�������A���̌��t����Ɏ��̎����Ō�葱���Ă���Ă��āA���� �s�����Ȃ������Ă�����b�ɂȂ��Ă��܂��B �@�L�������E�h�D�G�b�N���m�̌����̂悤�ɁA�E�C�Â����Ȃ����Ă�ꂽ�q�� �����łȂ��q�̌��ʂ����炩�Ɉ���Ă���̂��Ƃ�����A�搶���e������ɂ���l������ �E�C��^���錾�t����ɓ��������Ă�����ׂ��ł��B �@�F����̖���ڕW�̒B���ɏ����ł���^�ł���悤�A���͗E�C��^���錾�t�� ���������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
- 1��10���i�y�j �����������̎g����
�@�N���̑I���ň��{�����̑��������肵�A�l�X�Ȗ@�Ă�R�c�E���肳��� ���܂����A�����ł����łɂȂ锽�ʁA���^�ŗP�\�̊��Ԃ������ꂽ�肷��悤 �ł��B�\���C���Ɋ֘A������e�ɂ��ăs�b�N�A�b�v���Ă݂܂��傤�B �@�Z��擾�̂��߂̐e����q���ւ̑��^�ŖƏ��i����L��j�̂ق��A�q�⑷�ւ� �����Ɋւ��A1,500���~�ȉ����ꊇ���ċ�s�����ɐU�荞�݁A�����Ɏg���� ���邱�Ƃ��ؖ������̎���������A���^�ł��Ə������悤�ł��B �@���N�P�O�O���~�ȉ��̑��^�ł��Ə��ɂȂ��Ă����Ǝv���܂����A����ɔ�ׂ�� �啪�������������܂��B �@�c���ꐢ��̒��߂Ă��邾���Ŏg���Ȃ��������A�������|����q�⑷����� ���邱�ƂŁA���̒��ɂ��������Ƃ�������ł��B �@��㕨�������A�H�ו��ɂ�������������o�����ꂽ�N��̕��X�ł����A���̌�A �o�ς������ɐ������A�L���ȑސE��̐l���𑗂��Ă�����������Ǝv���܂��B �i�ܘ_�A���Ԃő�����Ă���悤�ɘV��҂̐����ی쐢�т������Ă���悤�ł����c�j �N��オ��A�����͂��邯��ǁA�����g�����ƈӗ~�������́c�Ƃ��������悭�����܂��B �@��ʂ̍��Ɨ\�Z���X�O���~�̓��{�̍����̑����~�z�́A�P�S�O�O���~�ł��B �@����͂P�T�N�ԍ����^�c���邱�Ƃ��ł��鋐��Ȋz�ł��B���̂������s��ɉ�炸�A �}�l�[�Q�[���̎����ɂȂ邾����������A������s�ɗ��߂Ă��邾���ł͌o�ς����� �܂���B �@�Ⴂ���オ���o�����̂��w������Ȃǂ��Ďs��ɂ������Ȃ��̂ł���A ����̐���̂悤�ɁA�w�����Ȃ�������Ȃ����̂������A�q���̋���ɂ������� �|����Ⴂ����ɂ������Ƃ����̂͗ǂ����@���Ǝv���܂��B �@�S���Ȃ�����A���̐��������ł�����Ă��Ďx�������Ƃ����������A���̉ېŊz�� �ꂵ�肷������R���Ă��Ă��܂��B�S���Ȃ�����A���߂Ă�����������ŋ������Ȃ�A ���~���W�����W�����Ďq�E���̋���̂��߂ɐ�Ɏg���������������̎g�����ł͂Ȃ� �ł��傤���B�܂��Ă�A�R������(�H)�����ł����łɂȂ�܂��B�₳�ꂽ�l�������ꂵ�܂Ȃ� ���߂ɂ��g���ߕ��h�ł͂Ȃ��g�g�����h���l����K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����A���l�������������ŋ������ƁA�^����������Ă���̂������B������ �����������Œʂ��Ă����������l�̕��Ǝq���̐��k����Ƃł́A���g�ݕ��ɈႢ�� ����Ɗ�����͎̂������ł͂Ȃ��ł��傤�B �@�Ⴂ�����炨��������������J���Đ��ݏo���Ă����������Ƃ������Ƃ� �q���B�ɂ悭�����������A���ӂ̋C�����������Ƃ���������ŁA����Ȏ������g���� ����������邱�Ƃ��ł�����A�o������Ԑ����������̎g�����ƌ����܂��傤�B �@����ɂ������|����Ƃ����̂́A���̑�ɂ��q���鐶���������̎g�����ł��B���� �������ł��Ă��܂��܂����A������͏����邱�ƂȂ��A�L���ȋ��{�Ƃ��Ď������ �`���Ă䂯����̂ł�����B
- 1��3���i�y�j�V�䐐�䂳��Ȗ،����y�R���N�[������
�^�ߓ��L�q�搶���|�p�Տܥ�D�G���!!! �V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��I �N���N�n�A������肨�x�݂ɂȂ�܂����ł��傤���H �@�K��悭�A�V�䐐�䂳��i������咆������w�Z�Q�j����N�P�Q���A�Ȗ،����y�R���N�[���̖{�I�� �Q�ʂɓ��܂����j���[�X����A�V�N�̃\���C���j���[�X�̓X�^�[�g�ł��I �@�`����͏��w�P�N���̎��Ƀ\���C���Ń��@�C�I�����̃��b�X�����n�߂܂����B ����܂ŕʂ̂Ƃ���ŏK���Ă����悤�ŁA�e�����ɓƓ��̕Ȃ�����A��������� �̂ɐ��N��v���܂����B �@�\���C���Ń��b�X�����n�߂ĉ��N���o�������A���@�C�I������{�i�I�ɏK������ �Ƃ����C�������萶���A���b�X�����Ԃ𑝂₵�āA���i�搶�Ɛ^���Ɏ��g�ݎn�� �܂����B �@�`����͔N�̋߂����@�C�I�����̂��F�B�ƒ��ǂ������Ȃ���A�����x�I�ɏ�B���A �P�Q���̃N���X�}�X�R���T�[�g�ł��o�b�n�̖����t�p���e�B�[�^�������ɒe���Ă��� �܂����B �@�Q�ʂɓ��܂�������̎ʐ^���Ƀ��[���ő����Ă��ꂽ�̂ł����A�Q�ʂ� �g���t�B�[�Ə���������s�������Ȋ炪�����ɂ͎ʂ��Ă��āA�Q�ʂ��������Ƃ� �������Ȃ����䂳��̏����C�Ȑ��i�������ɉf���o����Ă��܂����I�g�����������h �Ƃ������i�͐��܂���̂��Ƃ������̂ŁA�S����������ł��I���̉������v����ƂɁA ���Ȃ�X�e�b�v�ɔ�Ă����Ă���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B �@���N�̓w�͂̐��ʂ������Ŕ��\�ł���̂��y���݂ł��I �@�\���C���̍u�t�߂�ꂽ��A���ݍ�������y�����ł���������s�A�m�� �ߓ��L�q�搶���������|�p�ՏܗD�G�܂���܂���܂����B �@�ߓ��搶�͎t�ł��鍂�ǖF�}�搶����́A�ו��܂ōs���͂����k���ȃ��b�X���� �����搶�ł����A�������ւ̗v���x������Ȃ������A���̃v���O���~���O�̃Z���X�ƁA ���t�̊����x�̍����͔䌨������̂Ȃ��Ƃ����������x���̂��̂ŁA�ȑO���玄�͗\�z ���Ă����̂ł����A���̂��ь|�p�Տ܂������A��܂��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@���{���̏H�ɍÂ��ꂽ���t��̒��ŁA��܂Ɏ����ō��̉��t�ɗ^������܂ł��I �@�ߓ��搶�̎��t��͂P�P���S���ɍs���܂��B���C�t���[�N�Ƃ���Ă��� �o�b�n��i�̏W�听�Ƃ������郊�T�C�^���ł��B �@���N���ǂ����Ƃ���t���肻���ȍK��̂悢�X�^�[�g�ł��B��R�̓w�͂��ł��� �K���Ȉ�N�ƂȂ�܂��悤�ɁB
- 12��6���i�y�j�����Y�傪�u��ы����w�v�Ɓu�����p�ˋ���v
�����Y�傪�A���Z�Q�N�C��������̑�w�ւ̔�ы����w�ƁA�n���̏��w�S�N�`�U�N���� �Ώۂ��Y�勳�������ڏo�����w�����邱�Ƃ\���A�g�Y�傪�����p�ˋ���ɒ���h�� �b��ɂȂ��Ă��܂��B �����Q�O�N�A���y�����E���y�ƁE���y�ӏ܉Ƃ�y�o���邽�߂ɐݗ����ꂽ�������y�w�Z ���瑱���A�ێ�I�ȑ̐��Ɋv�V�̕��ł��B �O���̉��y�@�≹�y��w�����鎞�A�����ɔN����Ƃ����ǂ������͂�����܂��B �Ⴆ�A�p���������y�@�s�A�m�Ȃɓ��w���邽�߂ɂ͓��{�̊w�Z���X�g���[�g�ɐi�w ���Ă����Ƃ��Ă��A��w�S�N�̏H�����w�̃��~�b�g�ɂȂ�܂��B �ȑO�͔N�����������Ⴍ�A�p�������R���Z�����@�g���[���ւ̗��w�́A���{�� ��w�𑲋Ƃ��Ă���ł͕s�\�ł����B���݂͓��{�̑�w�̍Ō�̐������A�����`�p���Ԃ� ����������Η��w�\�ł����A��ы��Ői�w���Ă�����A���̋�J���Ȃ����Ƃ��v���ƁA ����͕֗��ȃV�X�e�����ȁH�Ƃ����C�����܂��B��ы��������A�Ƃ����D�z�������M�ɂȂ���A ���t�Ɍ�����������c�A�̂������b�g�ł��傤���H Facebook�Ȃǂł́A�Y�呲�Ɛ����F�X�q�ׂĂ��܂��B�P�N��邱�Ƃ��̑�ȉ��y�Ƃ� �a�������邱�Ƃɂ͌q����Ȃ��A�Ƃ����ӌ����w�ǂł������A�i�ޓ����l�X�L��A������ �`���C�X�ł���悤�ɂȂ�͈̂������Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ����̂����̍l���ł��B �g�Y�傪�����p�ˋ���ɒ���h����ŏ��̕��@�́A�n���i�܂��͕����ƎD�y�j�̏��w�S�N�� ����U�N���ɁA�Y�勳�����o�����Ē��ڎw������Ƃ������́B�n���ɋ����������^�юw������ �Ƃ����̂́A�������傪���N�s���Ă������ł����A���悢���Y�储�O�����A�Ƃ��������ł��B ���i�搶�������g�̃u���O�ŏq�ׂĂ���ʂ�A�s�A�m�E���@�C�I�����Ɋւ��Č����A ���w�S�N�`�U�N���ł͑����p�ˋ���Ƃ����ɂ͒x������N��ł��B�ܘ_����܂łɉ��y�� �����p�ˋ�����Ă����q�������W�߂Ẵ��b�X���ɂȂ�̂ł��傤���A�g��������h�� ���ł���ɂ́A�����ƔN��̉��̎q������Ώۂɂ��Ăق����C�����܂��B���w�S�N�`�U�N���ł� �g�����d�グ����h�Ƃ����̂����m�ł��傤�B �����A�V���������N�����A�Ƃ����_�ŁA������Y��̔��\�͑傢�ɕ]���������̂ł��B ����܂ŗD�G�Ȋw�����W�܂�ɔC���Ă�����w���A���烀�[�u�����g���N�����n�߂܂����B �@���{�͎������w�ǖ������ł��B�e����̗D�G�Ȑl�ނ����̗ƂɂȂ�܂��B�O�݂��҂����Ƃ� �ł���V�����V�X�e����肪�ł���l�ށA���E�̐l�X�����߂鐻�i���J������G���W�j�A�A ���I�ȐE�l�⑼�̍��ɂ͑��݂��Ȃ����x�ȋZ�p�����e����̃X�y�V�����X�g�A���E�� �K�v�Ƃ���A�[�`�X�g����āA���藧�ĂĂ����˂Ȃ�܂���B �@�����Y��̃��[�u�����g���A���{���琢�E�̉��y�E��Ȋ����鑽���̉��y�Ƃ��o�������� �����͂ɂȂ邱�Ƃ�]��ł��܂��B �@�ߍ��A���������Baby�\���C�������ĂĂ����q�������A���w�Z���w�N�ɂȂ�A������ �~�ߎ��Ȃ̂��A�Ƒ��k���邱�Ƃ������Ȃ�܂����B �@�s�A�j�X�g�ɂȂ肽���A�Ƃ����@�C�I���j�X�g�ɂȂ肽���Ƃ����q�ɂ͊W����܂��A ���{�̈�Ƃ��Ď�I�ɏK���Ă����q�́A�w�Z�̕��╔������ςɂȂ邾�낤�ƁA���w�Z ���w�������ƍl���Ă���ی�҂̕�������������悤�ł��B �@����A���q�z�[���ɍs�����܁A���q�z�[�����s�̏����q�Ɉ�̉�����܂����̂� ���Љ�܂��傤�B �@�~�����w�����ۃR���N�[���ŗD�������̂���ɍ��ۓI�Ɋ���t�����X�l�s�A�j�X�g�A �A���k�E�P�t�F���b�N����̃C���^�r���[�L���Ɍf�ڂ���Ă��܂����B�P�t�F���b�N����� �Q�l�̒j�̎q�̂��ꂳ��ł�����A���̎q�����Ɩ����Ă���A���̓��e��������ƃ��j�[�N�ł��B �@����́A�u�ɂ��₩�ŏ�M�I�ȃs�A�m�̐搶�ɏK�������A�ŁA�����ɂ͉��y���n�b�s�[�Ȃ��̂� �Ƃ����ӎ������t��������A�N�炩�Ȑ搶�Ɏt�����ĉ����P�y����K�����Ɓv�u�����̌Z��� ���Ă����o������A���܂�ɑ����y����~�߂Ă��܂��Ƒ�l�ɂȂ��Č�����邱�Ƃ�m���Ă���̂ŁA �P�S�ɂȂ����玩���̈ӎu�ő����邩�~�߂邩�I�����Ă��悢�v�Ƃ������̂ł����B �@�u���̂��Ȃ����ȒP�ɏK���ł��邱�Ƃ͂R�O�̂��Ȃ��ł͔��ɓ���Ȃ邩�A���邢�� �s�\�ɂȂ�v�Ƃ������Ƃ�`�������Ǝv���A��e�Ƃ��āu��l�ɂȂ�����A���̎������ɂł� ���������Ă����A�ƌ���Ȃ��łق����Ɗ�����̂ł��v�Əq�ׂĂ��܂��B�܂��A�u�l�ԂƂ��� �S�Ɠ��]����āA�z���͂����߂邽�߂Ɋw�ƂƉ��y�̃o�����X�͑�A���w����p�Ɖ��y�̌q����� �w�Ԃ��Ƃ��d�v�v�Ƃ�����Ă��܂��B �@�ؓ���ʂ��Ċo����Z�p�́A���w���オ�厖�ł��B�Ǖ��̗͂͌P�����~�߂Ă������܂��A ���t�̔\�͂͑̂̐����Ƌ��ɏ����Ă����܂��B �@�u�̃s�A�m����Ă��́A���e���Ȃ�����ǁE�E�E�v�ɂȂ�Ȃ����߂ɁA�P�S�Ƃ����������� ���Ȃ����f�^�����ȔN��ł͂Ȃ������ł��B �@�P�Q���A���Z���ȉ��̐��k����̓N���X�}�X�R���T�[�g�̏����A���͎d�グ�̎����� �����Ă��܂��B���������O�ɂ��A���S�̑̐��Ŗ{�ԂɗՂ݂܂��傤�B �@�F�l�ǂ����ǂ����N�����}�����������܂��B
- 11��8���i�y�j�������j���[�X�u�Q�n�������̗p�����v�u�I�[�f�B�V�����^�R���N�[���v
�@�������j���[�X����э���ł��܂����B �@�c��������\���C���Ń��b�X���𑱂��Ă������k���Q�n�������̗p������ ���i�����j���[�X�ł��B �@����܂ŗl�X�ȍ�������z���Ă����̂ł������A�����ŋɓx�ɋْ����āA �v���悤�Ȍ��ʂ��o���Ȃ����_���������A�Q�n��w����w�����y��U�ɓ��w �����̂������̊Ԃ̂悤�Ɏv���o����܂��B �@�����N�ɁA�\���C���J�ݓ�������̔ߊ肾���������Y��s�A�m�ȂɁA �a��i�^������i���݂͓����Y���w�@�ݐЁA�\���C���u�t�j�����i���A �Q�l�����č��i�̕ɗ������A�����a�C�×{�����������̕�i�O�В��j���A �u�i�^������̍��i���x����̍��i�̕����������v�ƁA���U�����Ƃ� �ł��Ȃ����A�͂����茾�����̂ɏł����L��������܂��B��̖��_�̂��߂� �⑫����Ȃ�A������x����̎����Ǝ��������Ɍ����Ă̒����͑�� �������̂ł��B �@���̌�A�撣�艮�̂x����́A���Z�E���w�E���w�Z�̉��y�Ǝi���̖Ƌ��� ����Ė����ɑ�w�𑲋Ƃ�����A���ʎx������̖Ƌ����擾���邽�߁A�Q��� ��U�Ȃ��C�����A���̌�A�Վ������Ƃ��ďA�E���܂��B �@���݂̋����̗p�����͂Q�������`���ŁA��勳�Ȃ̕M�L����������P�������A ���_���Ɛ��x�ɘj��ʐڂ�����Q�������ɕ�����܂��B�R�c�R�c�ƕ����� �x����͂P�������ɂ͍��i����̂ł����A�オ�艮����̂��ߗՋ@���ς� �����˂Ȃ�Ȃ��ʐڂ���ϋ��ł����B �@�ߋ��̖ʐڂŏo�肳�ꂽ���W���݂Ă݂�ƁA�ߍ��b��ƂȂ��Ă��� �����X�^�[�y�A�����g�i�������������Ă���e�j�ւ̑Ή��Ɋւ��鎿�₪ ���|�I�ɑ����̂�������܂��B�܂��A�ԓx�������������Ƃ��Ȃ������E ���k�����̎w���@�Ȃǂ�₤���e����R����܂��B���̂悤�Ȏ��₪���� �Ƃ������Ƃ́A���ꂪ�������������ɒ��ʂ��A�����E���f���Ă��� �Ƃ������Ƃ��z���ł��܂��B�N���[�������̒B�l�������ł����������������A �Ƃ�����Ԃł��傤���B �@�ǂ�����Ύq���B���e�X�̋��Ȃɋ��������悤�ɂȂ邩�A�Ƃ��A���Ȃ� �K���ɐ��ʂ���������w�����@�́H�Ƃ������w�͌���Ɋւ��邱�Ƃ�A ���݂��h���F�ߍ����A���Ԉӎ������߂�N���X�ɂ��邽�߂ɂ́H�Ƃ��� �悤�ȁA���\���I�ȃN���X�^�c�Ɋւ��鎿��������̗������ɂ��Ă䂯�A ���h�q�I�Ȍ��݂̋��猻��ł͂Ȃ��A�w���@�ɐS���ӂ��A�����v������ ����搶���������Ă䂭�̂ł͂Ȃ����ƍl����͎̂������ł��傤���H �@�x����́A�����������������A�Ƃ������ނ̒��X���~�̖ⓚ�͕s����ł����A �\���C���̒����ɘj�錵�������b�X���ɑς������̉䖝�����͕��ł͂���܂��A �ǂ�Ȏ��ł������j�R�j�R�ƏΊ���₳���A���l�̐S��a�܂��Ă��܂��D������ �ޏ��̃`���[���|�C���g�ł��B �@�܂��x����́A�q���B�������ł��y�Ɋo������悤�ɁA���Ȃ��D���ɂȂ�悤�ɂƁA �V�������ނ�n�삵���肷�邱�Ƃ��}���܂��A�����������ł������悤�ɁA �ł���悤�ɂȂ�܂Ŏq���B�ɕt��������h������������܂��B �@����҂Ƃ��āA�ォ���݊|���邱�Ƃ��ł��鐫�i�����łȂ��A���C������A ����ɒn���Ɏ��g�߂�D���������ޏ��̂悤�Ȏ��������ݏグ��̗p������ ���̍L�����]�݂܂��B �@�������j���[�X�͑����܂��B �@���@�C�I�����́w����A���i�L�O�� �ẴI�[�f�B�V�����x�ɕۈ牀�N���� �� ��������A���U�̈˓c���ق����i���܂����B �@���V�A�o�g�ŁA�����쉹�y��w���ɂ����ă��@�C�I��������ɐs�͂���A �����̓��{�l���@�C�I���j�X�g����Ă�ꂽ�A�ő��`���̐l�ɂȂ��Ă��� ����A���i�搶�̖剺���Ƃ��̑���q�̕������ɂ��^�c����Ă��� �I�[�f�B�V�����ł��B���w���̍��i�҂����͓����Y�啍�����Z�ɐi�w���� �l���������郌�x���̍����I�[�f�B�V�����ł�����A���̍��i�͉��l�̍��� ���̂ł��B �@���i�҂ɂ��t�̓��ʑI�����t��A���N�Q�O�P�T�N�R���R�P���A �����I�����s�b�N�L�O ���N�����Z���^�[�E�J���`���[�� ���z�[���� �J�Â���܂��B �@�܂����@�C�I�����̐V�䐐�䂳��i������啍�����Q�N�j���Ȗ،����y �R���N�[���ŋ��܂���܂��܂����B �@���@�C�I�����̃N���X������܂ł̒~�ς��悤�₭�\�ɏo�n�߂܂����B �����ȒB����ςݏd�ˁA�傫�ȒB���Ɍq���Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �@�P�O�N�O�A���̗��Łg�����A�a��i�^������͑f���炵���s�A�j�X�g�ɁA �x����͑f���炵�������ɂȂ�Ɗm�M���Ă��܂��h�Ə����܂����B�a�삳��� �V�����J���Ɩ����̂悤�ɃR���T�[�g�̍L�����ڂ��Ă���s�A�j�X�g�ɐ������A �x����͓w�̖͂��A�����̖���B�����邱�Ƃ��ł��܂����B���Ԃ��|���ς� �グ�Ă������Ƃ��`�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�܂���o�������Ă��炢�܂����B ���S������i�ЂƂ����j�ł��B
- 10��4���i�y�j���y���K���Ɛl�����ς��
�@���N�ɓ���Facebook���n�߂������ŁA���m�̕��X�Ƃ̋����������Ək�܂�܂����B �@���̐���̒m�l�����̒��ŁA���y�ƂƂ��Ă���l������Face book�������������A �̗̂F�l����������Ƃ��Ȃ�̕p�x�Ńq�b�g���Ă��܂��B������ł����Ȃ�����A���� ��荇��Ȃ������F�l�A�m�l�����̓����v�l�܂ł�����Ɏ��悤�ɂ킩��̂͋��� �ł��B �@�Љ�I�ȃg�s�b�N�X��v�z����тт��L���Ȃǂ��A�F�l�����̋���������Ƃ��� �u�V�F�A�v����Ă��܂����A���y�W�҂炵���A�ߋ��Ɏ����������������N�̉��t�Ƃ� �r�f�I�i���͉��ł�����ł���I�j�⒍�ڂ̃R���T�[�g�A�y��̏���特�y����� �ւ��錤���ȂǁA���y�ɓ��������L���������̂悤�ɑ����Ă���̂͋����[���Ƃ��� �ł��B �@���̒����璍�ڂ̋L�����P���Љ�܂��傤�B �@�肵�āw�V�܂łɉ��y���n�߂�Ɛl�����ς����Ė{���H�x�iNAVER�܂Ƃ߁j �@���s�A�j�X�g�ƃs�A�m���S�҂Ŕ�r�����ꍇ�A�^���̊w�K��A�͂�^�C�~���O�� �@�@���߂Ɋւ���Ă���]���ʁi���]�j�̑̐ς��s�A�j�X�g�̕����T���傫���B �@�@�y�o�T�w�s�A�j�X�g�̔]���Ȋw����x�z �@���]���̑傫���͂V�܂łɃs�A�m�̌P�����n�߂��l�̕�������ȍ~�Ɏn�߂��l �@�@�����傫���B �@�@�y�o�T�w�s�A�j�X�g�̂��߂̔]�Ɛg�̂̋��ȏ��x��P�T�� ���K�̐����w (2)��������̌��ʁz �@�s�A�m�𑁊��Ɏn�߂���A�P���𑱂���ƁA��������Ȃ������l�ɔ�ׂĔ]���傫���Ȃ� �Ƃ����������ʂł��B �@���U�Ύ����R�̃O���[�v�ɕ����A���ꂼ��s�A�m�A���y�A�����̃��b�X���� �@�@�P�N�Ԏ������B���b�X�����Ȃ������q���Ɖ����̃��b�X������ �@�@�q���ɔ�ׂāA�s�A�m�Ɛ��y�̃��b�X�������q�������̕����h�p�e�X�g�� �@�@���т̌��オ�����������B�y�o�T�w�s�A�j�X�g�̔]���Ȋw����x�z �@���y��̉��t�Ɖ^���_�o�͖��W�Ǝv��ꂪ�������A���������ɉ��y���n�߂�l �@�@�قǁA�킸���ȗ��K���Ԃŏ��߂Ẳ^���𐳊m�ɏK���ł����B���̂悤�Ȕ]�� �@�@������͌v����s�\�͂ɗD�ꂽ�l���Ƃ���A�^���_�o���ǂ��̂����̂��߂炵���B �@�@�y�o�T�F�V�ΑO����y����K���Ă���q�͓����^���_�o���ǂ��Ȃ�Ɣ����@�J�i�_��w�����z �@ �@�y���y�𑁊��Ɏn�߂�ƁA�h�p���オ��^���\�͂����シ��Ƃ����������ʂł��B �@�����̌����ɑ��ẮA���_���オ���Ă��܂��B �@����������������y����K���邭�炢�ƒ���I�ɂ��b�܂�Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŁA �@�@���̌��ʐ��т��ǂ��i�ɂ����Ȃ��j�B �@���������g������������e���q���ɂ�������������{�����߁A�q���̂h�p������ �@�@�Ȃ萬�т��ǂ��Ȃ�B �@�����y���K���q���͎����̑����ƒ�ň���Ă���B �@�O���ł��ƁA�e�̊w����n�x�̍��ɂ��w�K���̍��ق͓��{�ȏ�ł��傤����A ���̂悤�Ȕ��_�ɂ���������̂����肻���ł��B �@�������A���ۂ��̂P�Q�N�ԁA���c���̑������y��������H���Ă��āA�ƒ���� �Ⴂ�����Ő������͂ł��Ȃ��Ƃ������錋�ʂ��o�Ă��܂��B �@�Ⴆ�A�����Z��łP�l�����������y������s�����ꍇ�A���̌Z��Ɣ�ו��� ���т��^���̐��т��D�ꂽ�A��p�Ȏq�ɐ�������̂����g�����Ă��Ă��܂��B�����e �Ƃ��^�������Ȃ��ƒ�ŁA�S�_�����є����꒵�т��悭�ł����ł��I�Ƃ����o�� �����܂��B �@������A�����ɉ��y��������q�������A���ł��ł���f�G�Ȏq���ɐ������� ���Ă���̂����ی��Ă��Ă���̂ŁA�����̌����͎��̂P�Q�N�Ԃ̗��t���ł͂Ȃ��� �Ǝv���قǂł��B �@ �@���y���K���Ƃ������Ƃ́A��ړI�ł��鉹�y�Z�p�K���╛�Y���I�Ȑ��т�^���_�o�� �����}�邱�Ƃ����łȂ��͖̂ܘ_�ł��B �@�܂��́A���y�̊y������m���Ă��炤���Ƃ����Ȃ̂͌����܂ł�����܂���B �@����͑�������Ɍ��炸�A���y���K���Ă���S�Ă̐l�ւ̊肢�ł�����܂��B �@�������̐l�X���|�p�Ɋւ��Љ�ɂ͉��b������B �@���y�����镽�a�Ȑ��̒��������悤�A�[���������b�X���𑱂��閈���ł��B
- 9��6���i�y�j�����N���D�G�܁^�t�̉֎q�ɏH�֎q�̖���
�@��������N����R�W��PTNA�E�s�A�m�R���y�e�B�V�����A�\������a���A �����{��ʂP�n����ɂ����ėD�G�܁i���܂��j����܂��܂����B �@�����N�͖��N���̗��ɓo�ꂵ�Ă���R���N�[�����܂̏�A����ł����A ���N�͏��߂Ă�PTNA����A������܂����������ċA���Ă��܂����B���� �R���N�[���́A�S���{�w�����y�R���N�[���i�����V����Áj�ƕ��сA ���{�ōł����Ђ���R���N�[���̂P�ł��B�n��\�I�A�n��{�I��ʉ߂��� �S���{�I�ł́A���{�̃g�b�v���x���̉��t�����Ƃ��ł��܂��B���{�l �s�A�j�X�g�����E�̃R���N�[���ŏ�ʓ��܂��Ă��錻��݂Ă��A����� ���E���x���Ƃ�����ł��傤�B �@�������敪���ꂽ���{���̊e�n�悩��{�I�ɏオ���Ă���̂ŁA �n������̖{�I�o��҂��A�I���I���H�Ǝv�����Ȃ����t������l�� ���܂����A��s������オ���Ă����l�������l�̃��x���́A���A�� �ꌾ�ɂ��܂��B �@�����N�͌���n���ʌ��ł̒n��{�I�ŁA�S�`�U�ʂɒl����D�G�� �i���܂��j�����������܂����B�{�l�͌��ɂ����Ďd�����Ȃ��l�q �ł�������A����G���g���[����ۂɂ́A�g�{�I�o��h�ł͂Ȃ��A �S���{�I�̏�ʓ��܂̃��x���܂ŗ͂����ėՂ�łق����Ǝv���Ă��܂��B �@��������Ȃ������̂����l���A���̃G�l���M�[�����ݏo����Ă䂭�A �Ƃ����_�ŁA�g���ɂ����h�Ƃ����C�����͑�ł��ˁB �@����܂ŁA�R���N�[���o�ꖈ�ɓ��܂��J��Ԃ��A�������܂����̂ɂ� �S��炸�g���ɂ������Ă���h�����N�A�Ȃ�Ƃ������������w�S�N���ł��B ���N�Ɍ����ĉv�X�̐������y���݂ɂ��Ă��܂��B �@�������̂ō�N�̂R�O���N�L�O�R���T�[�g����P�N���߂��悤�Ƃ��Ă��܂��B �@���DVD���ς�@�����A���������^�悵���̂�����A��R�̕��ɒ����� �������������ƁA�ӂƎv�������A�v���O�����Ō�̓��{�̉̃��h���[��You Tube�� UP���Ă݂܂����B �@�\���C����HP�g�b�v�y�[�W�ɂ��\��t���܂����̂ŁA�\���C����HP���������������� �������Ƃ��ł��܂��B �@����Ƃ͕ʂɁA�g�Ԃ͍炭�h�����������o�[�W���������܂����B�s�A�m�W��A�e�� �g���x���^���S�h�A���@�C�I�����E���B�I���̓�d�t�g�p�b�T�J���A�h������UP���悤�� �v���Ă��܂��B �@���N�͉J�������A���ڂɋG�߂��i�݂����ł��B�~�J�̍��ɁA�H�ɑ����͂��̉Ⴊ ��L�����������ƂƁA�J�̍~�������N�ɂȂ��l�����������ƂŁA�H�������Ɨ\���� ���Ă��܂������A���~���߂��������肩�璩�ӂ̋C����������A��������H�͗l�ł��B �^������߂��Ă������ł��Ȃ�������Ȃ����������Q�`�R�N�̉ĂƂ͐����l�q�� �Ⴂ�܂��B �@�P�X�X�S�N�̗�Ă������N�A���Ă��s��ő呛�������܂����B���ފ݂܂ł̒g������ �\�����č�t�������ł��傤����A���̂P�����̗������ɂ͂��č��̕��X��A ���������������X���p�S���K�v�����m��܂���B �@��{�������A�t�ɐH�ׂ��֎q�ɏH�֎q�̖������������߁A�A��������̈�����āA �B�∾��A����悤�w�������Ƃ���A���̎w���ɏ]�����_�Ɓi���S���j�����������c�ꂽ�A �Ƃ����b������܂��B �@��{�����͔_�Ɛ���̐��ƂŁA�������̂�����Ă��錻�݂̏�肸���ƁA�_�Ƃ� �ւ�邱�ƁA�Ⴆ�ΓV���V�ϒn�قȂǂɕq���������ł��傤���A����ł��l���݊O��� �����̊��o�͉s�������̂ł��傤�B �@���̂悤�Șb��ǂ�ł������炾�Ǝv���܂����A���H�̖K�ꂪ�����Ƃ����\�z���������� ���ƂɁA��l�����Ă��܂��B���܂�ǂ��\�z�ł͂���܂���ł������A���̗\�z���A���� �l�̖��ɗ��ĂA����ɉz�������Ƃ͂Ȃ���ł��B�������������R�Ɋւ�錻�ہA�� �q���ɔc�������ǂ�ł䂭�͂́i�@�������A�Ƃ����̂��j�A����ɂ����Ă��K�v���� �v���̂ł��i����?!�j�B �@���{�͑����m�̒��ɐh�����ĕ����オ���Ă��铇���ł��B�ЊQ�ɂł��邾�����킸 �������т邽�߂ɂ��A�q�����͎��킸�ɂ����������̂ł��B �@�قǂقǂ̋C���̒ቺ���F�鍡�H�̓��X�ł��B
- 8��2���i�y�j�Ǔ��}�G�X�g���E�x���S���c�B
�@�}���A��J���X�A�}���I��f������i�R�A���i�[�^��e�o���f�B�Ȃǂ� �X�^�[�̎�̑䓪�ɂ��A�Q�O���I���Ղ̓I�y���̉�������ł����B ���[���b�p�ł̒����푈���I�������a�����߂������ƁA�^���Z�p�� ����ɂ��I�y���S�Ȃ��^������A����ȊO�ł����t���y���߂�悤�� �Ȃ������Ƃ��I�y���M�ɔ��Ԃ��|����v���������̂ł��傤�B�j���[���[�N�� ���g���|���^���̌��ꂪ�A���[���b�p�̉̎���W�߁A�W�q���ʂ������炷 �h��Ȑ�`��ł����̂��t�������ƌ�����ł��傤�B �@�e�Ɋp�A�X�^�[�I�y���̎�̈ꋓ�����͏�Ƀ}�X�R�~�̊S���ŁA ���i�R����ƃO���[�X�E�P���[�̌����̂悤�ɁA�}���A�E�J���X�� �e�o���f�B�̃��C�o���W�A�J���X�ƑD�����I�i�V�X�Ƃ̉ؗ�ȗ��� �s���Ȃǂ��A���Ԃ��Ȃ����̉ʂĂ̓��{�ɂ܂ł��͂��Ă������ł����B �@�Q�O���I���߂́A�܂��v�b�`�[�j�A�}�X�J�[�j�ȂǁA���݂ł������ ���p�[�g���[�ɂȂ��Ă���I�y����������l�C�I�y����ȉƂ������Ă��� ����ŁA���̌���`�b�N�Ȋ����I�X�g�[���[�Ɗ����I�ȉ��y�����ւ��� ������̐l�X�̐S�𖣗����Ă��܂����B �@�C�^���A�l�w���҃Z���t�B�����A�ߋ��̂��̂ƂȂ��Ă������b�V�[�j�A �h�j�[�b�e�B�A�x�b���[�j�Ȃǂ̃I�y�����A�}���A�E�J���X�Ƃ�����ނ� ���đ��X�Ƒh�点�Ă������̂͗L���Șb�ł��B �@�����̃v���}�h���i�I�y���́A�ׂ����p�b�Z�[�W�̃X�P�[����A���y�W�I�A �R�_�σz�̒������Ȃǂ��p�o���A����Z�I�Ƃ��̊���\�o���v������܂��B ���̓���Z�@���Ȃ��������ĉ̂����@���g�x���J���g���@�h�Ƃ����A ���̎���̍�i�͑��̂��ăx���J���g�I�y���ƌĂ�Ă��܂��B�x���J���g�́A ���̌�̎���A���F���f�B�̃I�y���ł��i�Ƃ����܂����A�{���I�ɂ͂��̌�� �C�^���A�I�y�����ĂɕK�v�Ƃ���Ă���̂ł��E�E�E�A���ƂȂ��Ă͑S���Ⴄ �̂���������郏�[�O�i�[���A�x���J���g��]�ƋL�^�Ɏc���Ă��܂��j ��Ɍp������A���F���Y������̏d�������o���悤�Ȕ����Ƌ�ʂ��ĔF�� ����Ă��܂��B �@���̃x���J���g�̐^�̌p���҂Ƃ��āA��Ƀ��F���f�B�𒆐S�ɂV�O��܂� ���E�̞w����Ŋ����e�m�[���̃J�����E�x���S���c�B�����A�V���Q�T�� �~���m�ŖS���Ȃ�܂����B�P�R���ɂX�O���}��������̂��Ƃł����B �@�Ⴂ���́A�J���X��e�o���f�B���Ƌ������A�~���m�E�X�J�����ƃ��g�� �|���^���̌���𒆐S�Ɋ���A�m�g�j�����ق����u�C�^���A�̌��c�v�ł� ���������e�m�[���̎�ł����B �@�P�X�W�U�N�A�U�R�̃x���S���c�B�������{�Ń��T�C�^�����s�����ۂɂ́A �z�����B�b�c�̂悤�ȑ�|����ȑO��`�͂���܂���ł������A�U�O�� �߂��Ă����̂ɂ��ւ�炸�A�x���J���g���@�̗]��̑f���炵���ɁA���{�� ���y�E���I�̑��������l�ȑ呛���ɂȂ�܂����B �@�Q�O�O�P�N�A�V�V�ł̗������T�C�^���͂��͂�`���ɂȂ��Ă��܂��B �@�N����d�˂Ă������ʼn̂����Ƃ��ł���x���J���g�̗D�ꂽ�����@�� �K�������ƁA�x���S���c�B���̂��Ƃɐ��E������Ⴂ�̎肪�����܂����B ���{�ł̃��T�C�^�����Ċ����������ƂƁA�x���S���c�B���Ɋw��ŋA������ ��y�̋������߂�����A�P�X�X�P�N����X�Q�N�ɂ����āA�������̉��ŕ� ���邽�߃C�^���A�ɗ��w���܂����B �@���F���f�B�䂩��̒n�u�b�Z�[�g�ŁA�x���S���c�B���̃z�e���Ɋʋl�߂ɂȂ��� ���N�Ԏ�u����A�J�f�~�A�E���F���f�B�A�[�i�ƁA�V�G�i�s�̓`������A�J�f�~�A�E �L�W�A�i�i�L�W�A�i���y�@�j�ł̂Q�R�[�X�̒��ŁA���͂Q�`�R���ɂP�x�̊����� ���̃��b�X�����A���̌�X�J������g���|���^���Ŏ���������邱�ƂɂȂ� �̎肽���̉̂��A���J���b�X�������Ŗ��������K�^�Ɍb�܂ꂽ��A����萢�I�� �e�m�[���A�J�����E�x���S���c�B�̐��ɂǂ��Ղ�Z����܂����B �@����ɂ���āA���ɋC��t���Đ����o�����A�Ƃ��������ɂ��Ă̕��� �ܘ_�ł����A�S����̎�u���̉̂��A�ǂ����A������������������ �g���h���o���オ��܂����B �@���I�̃e�m�[���̐����͋��낵���n���Ō����ł����B���������o�c���� �z�e���t�̃��X�g�����Ŕ����������͖̂��������オ��܂����i�ł�����A ���ɗ��h�ȑ̂��I�j�A�u�b�Z�[�g�ɓ����!!�n���ȗm���𒅗p�A ���E������W�܂���������ɂ͌������������A���f�̍ȃA�f�[���v�l�� ���r�܂��������ꏏ�A���̓V�����[�𗁂тȂ���w���̖���x�̃l�����[�m�� ��߁u�����������������E�E�v���������ݐ��̗l�q��T��A�h����������� ���b�X�������鐶���B�C�^���A�j�ɂ��肪���Ȍy��������������A���̎q�� �D����������Ƃ����z�C�Ȋ����ł͂Ȃ��i�ܘ_�C�^���A�l�Ȃ̂Ō����ĉA�C �ł͂Ȃ����E�E�E�j�A���i�Ŋ�ŁA�̋C���̕��e�̂悤�ł����B �@�ł�����A�l�C���o�ėV�щ߂��A���������ē��݊O�����̃e�m�[���� �悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��A�V�O��܂Ō��C�ʼn̂�������ꂽ�̂ł��傤�B �@�W�F�[���Y�E�����@�C�����烁�g���|���^���ւ̃I�t�@�[�̓d�b������ �|�����Ă�����A�m�l�����i�L���l�������ς��I�j�ɒ��a�R�T�p������ �p�����U���`�[�Y�̂P/�S!!���N���X�}�X�v���[���g�ɉ��\�����������肷�� �l�q�́A���A�x���S���c�B�Ƃ��������ł�������ǁc�c�B�i�A�����J�l���A ���̗ʂ̃p�����U���`�[�Y�����āA�ǂ�����̂��낤���ƁA�S�z�ł������c�c�B�j �@�}�G�X�g���ɂ�����邸���ƑO���玝���Ă����w�X�J�����̖��̎肽���x �Ƃ����{�ɁA�n�_�̃p�����U���`�[�Y�E�l�̉Ƃɐ��܂�A�n�����̒��ʼn̂� �������A�o���g���̎�Ƃ��Đ����A���̌㎩�͂ŕ����e�m�[���ɓ]������ �ƋL����Ă��܂��B �@�w�͂ƌ��������ȊǗ��Ő��E�̕�ƂȂ�A���@�C�I�����̖���X�g���f�B�o���ɂ� ���̖���������A�x���J���g�I�y���̈ꎞ���z�����}�G�X�g�� �J������x���S���c�B�B ���̉h���̐��U���̂��A�ӔN�͂𒍂�����i�̎w���̐��ʂ����E���ɍL����A�p������� �䂭���Ƃ���킸�ɂ����܂���B �@
- 7��5���i�y�j2014�\���C���R���T�[�g�cBaby Soleil�̐��ʌ���
�@�U���Q�Q�� (��)�A�\���C���R���T�[�g�i���\��j�y�у\���C���u�t �R���T�[�g���J�Â������܂����B �@���N���̗��Ɋ��z���������Ă��������Ă��܂����A���N�������� �ނ��ы���(!?)�A�f���炵�����e�̉��t��ƂȂ�܂����B �@���N�̏o���҂̒��œ��ɐi�������������̂́A�c�������B�o������ �U�l�̗c���̖w�ǂ��a�������\���C������̐��k����ł����A ��b�͂̒蒅�����݂ƂȂ�A�܂��e�䂳��̈ӎ��̍������Ƃ��v���� �Ȃ��āA���ꂼ��ɉ��y���̂���قƂ���o�Ă��鎩���I�ȉ��t�� �������Ă���܂����B������ꂽ���Ƃ𐳊m�ɍČ����邾���ł͂Ȃ��A �����������������̂��A���̎q�̊������ĕ\�����Ă��鉉�t�́A �����Ă��Ė{���ɐS�n���悢���̂ł��B �@�c���Ɍ��炸���ݍݐЂ��Ă��鐶�k�����́A�Q��̃��n�[�T�� �i������̐l�͂R��j���o������ƁA�~�X�i�����ԈႦ����A�]�ԉӏ��� ��������A�Õ���Y�ꂽ��j�͍�������܂��B�ȑO�́A�S�������̒i�K �܂ł����Ă����̂����J�������̂ł����A�ߍ��́A�e���Ȃ������Ō� �܂Ŏc��A���P���K�v���Ƃ����q�͖w�ǖ����Ȃ�܂����B �@����͉��̂Ȃ̂��ƍl����̂ł����A���炭�A���݂̒��w�������� �Ԃ���������X�^�[�g�����a�������\���C���̐��ʂȂ̂ł͂Ȃ����� �v���Ă��܂��B�ނ�ɂ̓\���t�F�[�W���̊�b�͂����蕈�ǂ݂ɋ�J ���Ȃ����Ƃ�����ł��傤�B�O���[�v���b�X���ł�����A���T���Ԃ� �O�ʼn��t���I����̂��A���t���ꂷ��v���̈�Ƃ��l�����܂��B ���Ԃƈꏏ�Ƀ��b�X�����钆�ŁA�F�����ǂ��ɂȂ�A�ǂ��Ӗ��� ���C�o���W�������Ă���̂�����S�ɔ��Ԃ��|���Ă���Ƃ����܂��傤�B �@���̒��ԓ��u�̊W�́A�a�������\���C���o�g�҂łȂ��q�������ɂ� �e����^���Ă��āA���n�[�T����R���T�[�g�A�����ă��b�X�����Ԃ� �O�シ��܁X�ɁA�����w�N���炢�̎q�����̉��t���A�G�ꍇ���A ���݂��Ɏh�����Ă���l�q�������܂��B �@�ꏏ�̃N���X�Ń��b�X�������Ă��Ȃ��Ă��A�����������������Ă���q�� ����w�N�ł́A���̎q�ɉe�����A����̎q�������ǂ�ǂ���ɂȂ��� ���邱�Ƃ�������������܂��B���F�B�̊W���đ�Ȃ̂ł��ˁB �@�\���C���̎q�����������\��ʼn��y�I�ȉ��t���ł���悤�ɂȂ����� ����q�ׂ܂������A������A��͂�a�������\���C�����e�����Ă���̂ł� �Ȃ��ł��傤���i��O���X�I�j�B �@���͉��y�̊�{�́g�́h�A�ł���Ǝv���Ă��܂��B�ł�����A�Ԃ��������A ���T���T�a�������\���C���̃��b�X���̒��ő�R�̉̂��Ă�����Ă��� �̂ł����A�킭��A�������ɂȂ�ƁA����l�̂����̒��ɂ��鎞���璮���� ���邱�ƂɂȂ�A�܂��������̂ɒ������t�������ł��i�j�B�����̒����� �����Ă���q�́A�̂��̂��n�߂����_����A�S���A�̂��Ă��鉹�������m�� �̂ł���I���b�X���̒��ŃV���[�x���g�̃A���F�E�}���A���̂��Ă��������ɁA �O�Ȃ̂Ɍ��̉��i���̂悤�Ȑ��Ŏ��̉̂Ƌ�����悤�ɂ��Đ����o���� ���ꂽ�q�����āA�ً����đ�Ȃ̂��ƁA�v�������̂ł��B�i���̎q�͊��S�� ���̐��̋����ɋ����Ă���Ă��܂����B������������Ə�����ȑ̐��ɂȂ��āI �{���Ɍ��̉��i���̂悤�ŁA�������́g�{�\�h���݂�悤�ł����B�j �@��R�̉̂��Ĉ�����q�������A�s�A�m�ł����@�C�I�����ł����R�� �j���A���X�̂��鉹�y��t�ŁA�̐S�����Ղ�ɉ��t���Ă���l�q���݂�ƁA �꒩��[�ɂ͂䂩�Ȃ��A�ςݏd�˂̑���A���̑�����v�킸�ɂ� �����܂���B �@�y��̉��t�����ł͂���܂���B�������q�����̉̂̉��t�ł��A���̐ςݏd�˂� ���ʂ��݂��Ă��܂��B���悪�L���A���ʂ�����A�̐S����̂��y�������ɉ̂��� ����鏬�w���̐��k�����B���������y�X�Əo���A�̂����Ƃ̓���������Ƃ� ���������܂���B���ɂ͎��̓��e�\���A����̍L���A���ʂƂR���q�������̏��� �����̂��q�l�̗܂�U�������t������܂����B��l�����������Ⴄ�̂ł����� �{���ɑ債�����̂ł��I �@����̓`�F���N���X�J�u�R�N�ڂɂ��ď��߂Ẵ`�F�����t������܂����B �����B�����A����̉��i���G�s�\�[�h�̐Ԃ�����w�Z�P�N���ɂȂ��� �p�ł��B���h�ɂS�̃o���G�[�V�������W�J����w���炫��ڂ��ϑt�ȁx���A �Ԃ�Ȃ��|�g���Œe���Ă���܂����B �@���w���A���Z���́A�ꏏ�Ɋ撣�铯���w�N�̒��ԂɌb�܂�A�����������Ă��� �^���Œ��B����܂Ŕ|���Ă���������\���Ɍq������悤�A�v�X���K�ɗ��� �����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B �@�����x�̍������y�I�ȉ��t�͒����Ă���l�ɃG�l���M�[��^���܂��B�F����� ���t��S�Ē����āA��ꂪ������f�G�Ȉ���ƂȂ�܂����B �@�o�����ꂽ���k����A�ی�҂̊F�l�A�����ɗ��ĉ����������q�l���A�U���Ԃɂ� �y�Ԓ����ԃR���T�[�g�ɂ��t���������������L��������܂����I �@�R���T�[�g���I������T�A�܂��U�������o���Ă��Ȃ��̂ɁA���̃N���X�}�X �R���T�[�g�Ɍ����ĉ̂��Ȃ̗\������C�ɐ錾�����q�����܂��B�X�ɁA�����܂ł̊ԁA �S�l���N���X�}�X�̋Ȃ����߂Ă��܂����̂ł���������ł��ˁB����̉ẴR���T�[�g�� ��肭�ł��āA����̕��X����J�߂Ă��������A�v�X���C�ɂȂ��Ă���ʁX�B ���̖ڕW�Ɍ������Ėڂ��P�����Ă��邻�̗l�q����́A�g�B�������l�́A�O������ ���ݑ�����h���Ƃ��m���ɑ̌����Ă���̂��݂ĂƂ�܂��B �@��D���ȉ��y�̗͂��A���ꂩ����悢�`�ŐL���Ă����Ăق������̂ł��B �@
- 6��7���i�y�j��e�̓����E��e�̖���
�@�w����̕�e�ɂȂ�Ƃ��ǂޖ{�x�Ƃ����^�C�g���̖{�̍L���� �ڂɂ��܂����B �@��R�̂��q�������ĂȂ���A��X�������������萷�肵�Ă��� �����������{�Ȃ̂ł����i�܂��ǂ�ł��Ȃ��I�j�A���̃^�C�g�������āA ���������I���������{���K�v�Ȃ̂�I�Ɨ��������������v�������܂����B �@���y�����Ŏd�������Ă���ƁA�q�����ǂ̂悤�Ɉ�Ă���ǂ����Ƃ��A ���y�Ői�w�������ق����ǂ����ǂ������A�E�c�E�c�Ɩ����Ȃ���q��Ă� ���Ă�����ɑ����o��܂��B�ܘ_�A�S���������Ȃ��Ƃ����l�͂��Ȃ��� �v���܂����A�قȂ鉿�l�ς̊Ԃ�f�r���F�X�Ȃ��Ƃ������Ō��߂�ꂸ �h�ꓮ���Ă���l��ڂɂ���ƁA�q�������O�ɁA��������Ƃ������l�ς� ����A�����������g�̃A�C�f���e�B�e�B�̊m����ڎw���ׂ����Ǝv���ĂȂ�܂���B �@�e�̉��l�ς��p�����Ă�������A�e�q�Ԃ̉��l�ς̑��ق͍��قǂȂ����� �ł��傤�B�e�͎�������Ă�ꂽ�悤�Ɏq������Ă�Ηǂ���������ł��B �E�Ƃ⌋�����܂߁A���ɂ����Ă��I�����������ɂ��錻��ł́A�e�q�Ԃ� ���l�ς̐��荇�킹������ɂȂ�����A��������Ă�ꂽ���Ɖƒ�O�� ���Ƃ̈Ⴂ�ɔY�ނ悤�ɂȂ����肵�܂����B �@�������A������Ƃ����āA��O�̂悤�Ɍ���ꂽ���l�ς̒��Ő�������� �K���A�ȂǂƂ�������͂���܂���B�E�Ƃ������������������R�ɑI�ׂ� �f���炵����������Ȃ�āA���ꂱ���o�J���Ă��邩��ł��B �@����ł͂ǂ�����悢���@�@�@ �B �@���l�ȉ��l�ς����̐��ɑ��݂���̂��Ƃ������Ƃ�m�邽�߂ɁA�{��ǂ� ���Ƃ����E�߂��܂��B���ɁA�Ⴂ���͏�����ǂ�ŗ~�����Ǝv���܂��B �����ɂ́A��҂��o���������Ƃ�l�������ƁA����̐l����u�����蒲�ׂ��� �������Ƃ��A�o��l����ʂ��ĕ`����Ă��܂��B���⎞��A�o��l���̔N��� ����ɘj��A���ʂɐ����Ă��Ă͐�Όo���ł��Ȃ��l�X�Ȑl�Ԗ͗l���������� ���Ƃ��ł���̂ł��B�ǂ̂悤�ɍl���A�ǂ̂悤�ɍs������ƁA�ǂ̂悤�� ���ʂ������炷�̂���l�X�ȃp�^�[���ŋ����Ă���܂��B �@��������͍�����悤�ɂȂ�����A�N�w����`�L��ǂނ̂��ǂ��ł��傤�B �L���Ȓ����Ђ��[����ǂ�ł����ƁA�����A���ꂾ�I�Ǝ����̋C������ �q�b�g����{�ɕK���o�����܂��B �@���h����l���̓`�L��ǂ�Ő^�������Đ����Ă݂�̂��P�̕��@�ł��B �@���ł́A�N�w���Ȃǂ��Ղ������t�ŏ���������Ă�����̂������A�������E �l�����̎w�j�ɂȂ�{�ɏo�����₷���Ȃ��Ă��܂��B �@������̂��ʓ|�������I�Ƃ��v���Ȃ�A�r�W�l�X�{��How to�{����� �Ƃ��Ă݂�̂��ǂ��ł��傤�B�Y�o���I�m�肽�����Ƃ��^�C�g���ɂȂ��� �����肵�āA������Ղ�����ł��B �@�����ƈقȂ鉿�l�ςɏo���킵����A�����ɕs�������������ɁA�ǂ������ �蔲������悢�����g�{�h�������Ă���܂��B �@�{��ǂވȏ�ɕK�v���Ǝv�����ƁA����́A���ꂳ��ɂȂ�O�ɁA��e�̖��� �ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃł��B �@���A�����͋�����錠���A�j���Ɠ����ɓ����錠�����l�����܂����B ����͑�ϑf���炵�����Ƃł����A�������l�Ԃ́A��e����Y�܂�A��̓��� ��������Ƃ���������O�̂��Ƃ��A���������ɓ`���Y��Ă��܂��Ă���C������ �Ȃ�܂���B����͌����Ēj�������Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�f���炵�������̓����� �Ƃ������Ƃ��B�V�������������Ɠ����Ɂg��e�̖����h������Ăق����� �l���܂��B�q���̐g�̂���Ă邱�ƁA�Љ���������l�ԂɂȂ�悤����� ���邱�Ƃ́A��e�̖�ڂł��B�ܘ_���e�����̕��X�̋��͂���ł����A �܂���e����������Ƃ��̖������ӎ����ӔC�������Ƃ��̐S�ł��B ���ꂳ��ɂȂ��Ă��炻�̐ӔC�̏d���ɂ��̂̂��l���������Ƃ���݂Ă��A ���̓��{�̋���́A���ꂳ��ɂȂ�l�ɑ��ė₽���A�Ɗ����Ă��܂��B ���̂Ȃ�A�q������l�O�ɂȂ�܂łǂ���̂��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A �ǂ������S�\���ň�Ă�ׂ������Y�ޑO�ɂ������苳����V�X�e�����Ȃ� �̂ł�����B �@���_�I�Ȗ�������Ă���q�́A���_�I�ɕs����ȕ�e�Ɉ�Ă��Ă��� �����𑽂����Ă��܂����B �@�[���Ȉ���A�����i����j�A�����Ċ��e���i�����S�j�A���̂R�𒌂ɁA �m�łƂ������l�ς������Ďq��Ă���c���̐S�\���ƕ��@��`����w�Z�� �ق������̂ł��B �@���l�ȉ��l�ς����݂��錻��̓��{�A�S�Ă̎q���������̎����Ă��� �f�����[���ɔ����ł��A�[�������ꐶ�𑗂��悤�ɁA��e����̕K�v���� �����Ă��܂��B �@
- 5��3���i�y�j�����̕t�����ԂƉ��K�����߂��̂͒N�H
�@�u�������Ăǂ����Ă����������ԂɂȂ��Ă���̂ł����H�v �@Baby�\���C���̃N���X�ŁA�������������{�[�h���f���ēǂݏグ�Ă�����A ����l���玿����܂����B �@�\�Ȍ���ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɂ���������悤�������ă��b�X���ɗՂ�� ���܂����A�ƂĂ��f�p�Ȏ���Ȃ̂ɉ��y���_�̍���܂Őu�˂�ꂽ�悤�ȋC�� ���āA�ǂ������ėǂ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B �@��n�̒����K�Ȃ�A�e���Ԃ̑S���Ɣ����ɂ��K���I�ȉ����̘A�Ȃ�� �s�A�m�̔��������������̂�����ׂĂ����ƁA��P�̂��̂̓t�@�A��Q�� �t�@�ƃh�A��R�̓t�@�E�h�E�\�Ƃ����悤�ɁA���������Ă����܂��B ���ꂪ�ǂ����ĂȂ̂��ƍl���邱�ƂȂ��A���̂܂܊o���Ă������Ƃ��ĔF���B �����̏��Ԃ�����A�h���~�t�@�\���V�h�̉�����A�e���̍���(�s�b�`)������E�E�E�B ���̋N����m��Ȃ����Ƃɓ��h���Ă��܂����̂ł����B �@�ЂƂ܂��h��ɂ��Ă�����āA�w�j���[�E�O���[�����y���T�x����������o���� ���ׂĂ݂邱�ƂɁB �@���ׂĂ݂Ă܂��ӊO�������̂́A���̍����A������s�b�`�����߂�ꂽ�̂� �P�X�R�X�N�Ɗ����ŋ߂̂��Ƃ������Ƃ������ƁB�C�M���XBBC�����ƕč��X�~�\�j�A����� ��Ăɂ�荑�ۉ�c�Ō���B���R�́A�����̂��߂ɘ^�������e�[�v��ڑ�����ہA ���̃s�b�`���K�v���������炾�����ł��B���̎��_�ŏ��߂Đ��E������肵�� �Ƃ������Ƃ́A����ȑO�A�s�b�`�͈�肵�Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B �@�Ⴆ�A�s���ϗ��N�����B�A�ȏW�t�Ƃ����A���̌��{�s�̂悤�ȍ�i����Ȃ��� �o�b�n�̎���A�y���n�悲�ƂɃs�b�`���قȂ��Ă����Ƃ������Ƃł���������ł��B �P�_�P�_���肾�����y�퐻��̋Z�p���A�s�b�`�̈���܂ł͎���Ȃ������悤�ł��B �F�X�ȁg�h�h�́u���ϗ��v�����݂����Ƃ���Ȃ�A�o�b�n�͍��̂悤�Ȑ�Ή����� �����Ă��Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�g�{���h�͂����m�ł����H�P�̉���炷�����ŁA�P�I�N�^�[�u��̉��A ���̊��S�T�x��̉��A����ɂ��̊��S�S�x��̉��E�E�E�Ƃ����悤�ɁA��̉��� �����{�̐U�������������A��̉��̒��Ɋ܂܂�Ă��āA�����{���ƌĂԂ̂ł��B ���̔{����ɂȂ�A�h���~�t�@�\���V�h�̉��K���o�����ƌ����Ă��܂��B �@���̉��K�ɖ��̂�t���A�S�����i�T�����͂��̌�a���I�j�ւ̋L���@���m�������̂��A �P�P���I�C�^���A�̏C���m�O�B�[�h�E�_���b�c�H�B���̐l���L���ȁg�h���~�t�@�\���V�h�h�� ���݂̐e�ŁA���̏o�T�́A���e����̃O���S���E�X���́w����Ґ����n�l�̒a���x�̒��� ���n�l�]�̑��Ԃ̉̎��ł��B Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Ioannes. �u���̂����ׂ��A���������ȂłāA���̖��Ȃ�킴�� ����������悤�ɁA���̂����ꂠ��O�̍߂��̂����� ���܂��A�����n�l��B�v�i�a��j (�����̂Ƃ��낪���ꂼ��ut,re,mi,fa,sol,la�c�ƂȂ��Ă��āAsi�͂����ƌ�̎���� �Ō��S��I��g�ݍ��킹�č��ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�t�����X�ł͍��ł�Ut�� �g�h�h��\�������Ƃ��Ă��̂܂g���Ă��܂��B) �@ �@���ۂ��̋Ȃ́AUt�̓h�̉��ARe�̓��̉��AMi�̓~�̉��ŏ�����Ă��āA���R�Ȃ̂��A ���Ȃ̂��A���Ɠǂݕ�����v���Ă���̂ł��I �@����q�ׂ��u���ϗ��v�A����͂P�I�N�^�[�u�ς��ĂP�Q�̉��ɕ��������̂ŁA �{���ō\�����ꂽ������ɂ����������̒��a�͖]�߂Ȃ����̂́A�S�Ă̒��ɓ����悤�� �]���ł���Ƃ��������b�g�����邽�߁A���R�ȓ]����D��������o�b�n�̖��삪���܂�܂����B �@�s�A�m�̔������h���~�c�̉��K�ō\������Ă��邱�Ƃ���������ł����A����̃s�A�m�� �h���~�t�@�\���V�h���{�̉��K�Ƃ��ĕ��ϗ��Œ������ꂽ�y��ŁA�h���~�c�Ɖ����Ԋu�� ���ɕۂƂ��Ƃ���ƁA���S�T�x��̒��ɏオ�邲�ƂɂP����̒����������邱�Ƃ� �Ȃ�܂��i�����悤�Ɋ��S�S�x��̉�����n�܂钲�ł́�̒������P�������Ă����j�B �@����́A���e�����I�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���y�̐��ƂɂƂ��Ă��A�s�b�`�̗��j�� �h���~�̖��̂̋N���A���K�̋N���Ȃǂ͐��Ɂg�g���r�A�I�h�ł����A���F�B�Ƃ̘b��Ɏg���� �݂��肷��ƁA���\��������A�����ł��邩���m��܂���(��)�B �@���[����ŏh�肪�����I�����I �@���������A����Ȃ��Ƃł��Ȃ��ƋM�d�ȁw�j���[�E�O���[���x�̉��y���T���R������Ȃ��̂ŁA �u�H�v�Ȃ��Ƃ��������牽�ł������ɗ��ĉ������I �@
- 4��5���i�y�j�����t�̍]�X���q
�@���������Ă�����������A�s�A�m�����t�̍]�X�_����Ƃ�����肨�b���� ���Ԃ������Ƃ��ł��܂����B �@�]�X����́A(��)���{�s�A�m�����t������A�\���C���J�ݎ�����s�A�m�� �����e�i���X��R���T�[�g���̒��������肢���Ă�����ł��B �@�������������Œm�荇�����̂����o���Ă��Ȃ����炢�̂́A���ꂱ���R�O�N���� ���t�������ɂȂ�܂��B �@�]�X����́A���������łȂ��A�Â��s�A�m�̏C������e�i���X�̃X�y�V�����X�g�ŁA �����쉹�y��w�Ⓦ���Y�p��w�����̖������ɗA�����ꂽ�s�A�m�̏C�������s���Ă��܂��B ����܂ł̋Ɛт����߂Ďf���ƁA�������Ȃ̂��Ȃ��A�Ƌ����̂ł����A���̈̑傳�ɂ��� �������N���Ȃ����A�g�߂ȑ��݂ł��B �@�s�A�m�����t�́A�s�A�j�X�g�Ƃ̊W���[���E�ƂȂ̂͂ǂȂ��ł��z���ł��܂��ˁB �c�B�v���A���E�J�c�@���X���͂��߂Ƃ���s�A�j�X�g�E���t�Ƃ����̃��n�[�T���̏�i�� ���K���@�ȂǁA����̂��b�̒��Ŋy�����f�����Ƃ��ł��܂����B �@�c�B�v���A���E�J�c�@���X�́A���n�[�T�����Ԓ��X�e�[�W��̃s�A�m�̊W�i���ʑ�� �������I�j�������ƕ߂��܂ܗ��K���A�{�Ԃ����J����Ƃ����s�v�c�ȏK�������� �s�A�j�X�g�Ƃ������b��i����͈��̃W���N�X�Ȃ̂ł��傤�ˁj�A�J�[�`�X���y�@ ���@�C�I�����ȋ����̃A�[�����E���[�U���h�ƁA�s�A�j�X�g�̃u���[�e���̃��T�C�^���ł́A ���ꂼ�ꂪ�{�Ԃ܂ł̎��ԁA�{�Ԃɏ悹��Ȃ͒e�����ɏI�n��т��ăX�P�[���E�A���y�W�I�Ȃ� �w�̗��K�������s���̂ŁA���̖{�Ԃ̋Ȃ���K���Ȃ��̂ł����A�Ɛu�˂�ƁA���ꂳ���ł���� �|�����̂͂Ȃ�����A�Ɠ������G�s�\�[�h�ȂǁA�y����K���Ă���l��������������h���� �邾�낤�ȁA�Ǝv�����b������ł��B�i���݂ɂ��̂Q�l�A���킹�Ēe�����̂� �{�Ԃ����������̂������I�j �@�J�c�@���X�̃��T�C�^���ł́A�R���T�[�g�̋x�e���ԂɓˑR�X�e�[�W�Ɍ���A ����̕ϑt�Ȃ����X�ƒe���������Ƃ��E�E�E�B���t���I������܂ł����ƃX�e�[�W�e�� �T���Ă��钲���t�����炱���̑̌��G�s�\�[�h�ł��ˁB�i���ɂ������q������ܘ_ ��������ł�����ǂ��c�B�j �@�����t�̐��w�Z�ɒʂ킸�s�A�m�����Z�\���ƌ���P���ɍ��i�������q����ƁA �e�q���Q�l�œ��{�����щ���Ċ���Ă��܂��B���̌���P����e�q�Ŏ擾 ���Ă�����́A���{���A�]�X����e�q�ȊO���ɂ͂���������Ȃ��̂������ł��B �@�]�X����́A�m�g�j�́w�j�̗����x�Ƃ����ԑg�ɏo�����ꂽ���Ƃ�����܂��B �����ӂ̌O���������I���ꂽ�����ŁA�ԑg���́w�����̐S�ō��\�[�Z�[�W�E �x�[�R���x�B �@�s�A�m�����łȂ��A���A�����Ƃ�����Ƃɂ��đ���ɘj��D��S�����A ���N�̂悤�ȕ��ł��B �@�]�X����́A�x�`�l�`�g�`�o�ł��特�y�]�_�Ƃ̌���������Ƃ̋������o�ł���� ���܂��B�s�A�m�̖{��s�A�m�ɂ܂��G�s�\�[�h���܂Ƃ߂��w�m���Ă���悤�� �m��Ȃ��s�s�A�m��������G�w���T�t�x�B �@���̒��Ƀs�A�m�̔����ƍ����̔z�u�̗��j�������Ă������̂ł����A���A���x ����ɂ��Ē��ׂĂ����Ƃ��낾�����̂ŁA��ϗL��ǂ܂��Ă��������܂����B �@���̃G�b�Z�C�ɏ������Ă����������邽�ߍ]�X����ɘA����������Ƃ���A �߂����{�����t����É��x���ɍu���ɍs���̂ł���A�Ƙb����Ă��܂����B �@�����Ɛ��X�̃G�s�\�[�h�ŊF����̋������O�b�Ƒ~�����Ă邱�Ƃł��傤�B �F����ɔ��������F���y����ł����������߁A�\���C���̃s�A�m�́A���ꂩ��� �]�X����e�q�ɂ��C���ł��i�j�B �@
- 3��1���i�y�j���т͍ō��̃R�~���j�P�[�V�����c�[��
�@�ȑO�A�����ɂ��ď��������Ƃ�����܂����A���̂��Ƃɍ����ɃR�����g�� �����������Ƃ�����܂��B�F����H�ׂ邱�Ƃɐ����S��������Ȃ̂��ȁA�� ������@��������̍��ł��B �@�������ɘR�ꂸ�A�����H�ׂ邱�Ƃ���D���B�N���N�������������X�ɏo�|���� �����Ȃ��̂ŁA�����ō���ĐH�ׂ���X�ł��B�F�X�b�܂�Ȃ����Ƃ������� ���̐l���ł����i�z���g�`�H�j�A�H�ׂ邱�Ƃ����͔��Ɍb�܂ꂽ�O�������߂��� �Ă��܂����B �@���Z�A��w����́A���x�o�u���^�Œ��ŁA��̗F�l�̂���l���A���c�ɋ�� ���J���̃V�F�t�����������ă��X�g�������J�Ƃ����̂�ǂ����ƂɁA�X�̃}�_�� ��������̗F�l�ɗU���A���T���܂��Ȃ�������Ղ��ɒʂ��Ă��܂����B�܂��Ȃ� �Ƃ����Ă����J���d���݂̗����ł���������������Ƃƌ������炠��܂���B �@���a�T�X�N�A��w���w�̂��j���ɁA�����b�ɂȂ����搶�ƌ�ꏏ�ɋ�����J���� �f�������A�����H�ׂĂ�����̂Ɠ������������̂ɂ͐S����������̂ł��B �@���ƂQ�l�ŏZ��ł����A�p�[�g�ɁA���܂��܃C���h��g�ق̏��L��������l�� �ꏏ�ɕ�炵�Ă��āA�ޏ��ɗU���R���ɏグ���C���h���������y���ɂȂ��Ă��� ����������܂����B����l���������ȕ��ŁA����Ă���Ƃ���������ĉ������āA �����Ղ�{�i�C���h�������K���Ă��܂��܂����B���ł��������{�ŐF�X�C���h�J���[ �̃��V�s���Љ��Ă��܂����A�����͒������A���{�̃J���[�̍����Ƃ͑S�R�Ⴄ ���@�ɍD��S�̉�ɂȂ������̂ł����B���������������A���߂ɂȂ������A�{���� �c�C�Ă����������Ǝv���܂��B �@���ؗ����͑�w�@�̓������ɏK�������Ƃ�����܂��B�|��̑�w�@���̒����l ���w���Ƃ��ė��������R�l�̂����̂P�l���A�����Œ����t�̖Ƌ��������A �Z���`�����[�n�C�A�b�g�̒��̖��X�A�Ő��{�ł��A���o�C�g�����Ă����l�ŁA �炩���鐅�L�q��A�e���Ɠ����u�ߕ��ȂǁA�ȒP�œ��{�̂��̂Ƃ͑S�� �Ⴄ���́A������Ȃ��Ĕ����������ؗ������R�����܂����B �@�C�^���A�����́A���w���A�������̃C�^���A�l�Ƌ������������Ă������A �l�X�Ȓ������p�X�^�\�[�X�Ɠ������������܂����B�ޏ��̂Ƃ���ɂ̓��C�h ���ʂ��Ă��Ă��āA�T�ɂQ�x�A�|���Ɛ���A�A�C�����|�������Ă���� ���܂����B���C�h�����鎞�ɂ́A���������̕����̑|�������邱�ƂɂȂ��� ���āA�ޏ��ƃ��C�h����̂��������āA���̖����� �A����̎d���A�A�C������ �������A�x�b�h���C�L���O�̕��@��{�i�I�ɏK�����܂����B���������� ���[���b�p�I��w�C�Ƃ������Ă��������ł��I �@���N�̑�e�m�[���A�J�����E�x���S���c�B�̃N���X�ɒʂ��Ă������ԁA���k�S���� �ނ̌o�c����u�b�Z�[�g�̃z�e���ɍ��h����̂ł����A���̃z�e���̃��X�g������ �V�F�t�ɃX�[�v��p�X�^�\�[�X�������܂����B �@�p������͑�w�̐�y�ƌ�y�ƂR�l�ŕ������V�F�A���Ă��āA�̎�ł���ޏ������� ������肾�������Ƃ�����A�ޗnj��o�g�̎q�Ɋ��̂����̐F�X�A�Ⴆ�ΐ花���卪�A �Ђ����̎ϕt���A�����A�͂��܂��������̔����X�G�ςȂǂ��K������A�F�X�ȗ����{���� �����Č����邱�Ƃ����ӂȎq�Ə��������������肵�āA������R�̗�����n���A���₩�� �[�H�O���̓��X���߂����܂����B�̎�͗����D���Ȑl�������̂ł��B �@���{�ł͈�ʓI�ł͂Ȃ�����ł̃p�[�e�B�ł����A���[���b�p�ł͐e�������ԓ��� �p�[�e�B���ǂ����Ŗ��T�J����Ă��āA�����ʼn��l�̂������𖡂킦����i�ǂ��̉Ƃ� ���X�g������肸���Ǝ|���I�j�A�V�����o�����������A�ō��̎��Ԃ��߂������Ƃ� �ł��܂��B �@���{�ł��K���ɂȂ�Ηǂ��̂ɂƎv�����Ƃ̈�ł��B �@ �@���т͑̂���邾���łȂ��ō��̃R�~���j�P�[�V�����c�[���ł��B�Ȃ�ׂ������̕��� ���ꏏ�ɂ��т����������K���������������̂ł��ˁB���̂悤�ȋ@����}���ɍ���Ă��� �����Ǝv���A�����A�����������������т���邼�I�Ƙr�܂��肷�鎄�Ȃ̂ł����B�@
- 2��8���i�y�j����搶�̃}�����o��i�^���c����ŗD�G��
�@��ȁE�\���t�F�[�W���̍u�t�ł������k���搶�̃}�����o�̂��߂̍�i �s�O�t�ȂƃA���O��Op.19�t���A���N�J�Â�����R�P����{�ǑŊy��R���N�[���E �}�����o�����Q���\�I�̉ۑ�ȂɑI�o����܂����B �@���{�ǑŊy��R���N�[���́A�ǑŊy��̃R���N�[���Ƃ��ė��j�ƌ��Ђ��� �d�v�ȃR���N�[���ł��B���̍�i�͌���搶���}�����r�X�g�i�}�����o�t�ҁj ���X�M�F����ϑ�����A�P�X�X�W�`�P�X�X�X�N�ɍ�Ȃ��ꂽ�ȂŁA �}�����o�Ƃ����y��ŕ\���ł���ō���x�̋Z�p��g�ݍ���ł���̂������ł��B ����܂łɂ����j�o�[�T����x���M�[��}�����o���ۃR���N�[���i2007�N��2013�N�j�A ���E�}�����o��R���N�[���i�V���g�D�b�g�K���g�j�i2012�N�j�ȂǁA���E�� �}�����o��R���N�[���Ő��x�ɘj��ۑ�ȂƂ��Ď��グ���Ă��܂����B �@�Y�X�Ƃ����L�����N�^�[�̌���k���搶�͍�N�̂R������\���C���̍�ȁE �\���t�F�[�W���̍u�t�Ƃ��Ē��C����܂����B�����|��̏C�m�ے����C�����ꂽ�� �n�Ă��A�~�Y�[����w��w�@�Ŕ��m�����擾�A�ȗ��P�T�N�ɘj��A�����J�Ŋ��� ����܂����B�|��݊w���̈���܁i�w���R�N�����̎�Ȃ̐l���Ⴆ��j����� ������Ȃ����̎�ܗ��̂����ȉƂł��B �@����Ȃ��Ƃ�\���グ��Ƒ�ώ���Ȃ̂ł����A�X�����o���Ƃ��̌����Ȑl���A �����~�X�}�b�`�ł��ˁB���ꂾ���̌o���������Ă�����A�J���X�}��ȉƂƂ��� �}�X�R�~�Ŏ��グ���A���ŕ����ĕ����Ă��Ă����������������Ȃ��̂ɁA �搶�{�l�́A�W�X�Ƃ������q��������A�D�������݁A���Â��ɘb�������t���� �悤�ȕ��ł��B �@�u�Z���X����f�G�ȍ�i����Ȃ�����ł���B�v�Ƃ͌���搶�̍�i���� ���Ƃ�������X����̊��z�ł����A�c�O�Ȃ��炱��܂Œ������Ă��������@� ����܂���ł����B �@����搶�͎�̊O�A���k�����������Ă��āA���J�ɒ��J�ɉ���܂� �����ĉ����鋳�����ɁA�l�C�͍��܂����B�������ɃA�����J�Œ��N��炵�� ���炵�����������Ēm���͖L�x�Řb�p�͖ʔ����A���y�ȊO�ɂ��l�X�Șb���� ���ĉ������Ă���l�q�ł��B �@�s�O�t�ȂƃA���O��Op.19�t�͏��X�M�F���̃}�C�X�y�[�X�Ō�������Ƃ����� �������Ƃ��ł��܂��B���X�M�F����CD�wMarimbist�x�ɂ͑S�Ȃ����^����Ă��� �悤�ł��B�����̂�����͒����Ă݂Ă��������B �@���N���̗��ɓo�ꂷ���A�̉��c�^�킳��i����܍��ۃA�J�f�~�[�������Q�N�j���A ���N�̃W���j�A�s�A�m�R���N�[�� �k�֓�A�u���b�NB�ے��ŁA�Z���o���e�X��� �s�������Ռ��t�A�h�r���b�V�[��ȁs�q���̗̕��t����s�O���h�D�X �A�h �p���i�b�X�� ���m�t��e���A�O��̍ŗD�G�܂���܂��܂����B �@�^�킳��͂���܍��ۃA�J�f�~�[�������̃o�g�~���g�����ɏ������A�V�[�Y�� �Ƃ��Ȃ�Ɩ��T���ɏo��A�}���\�������i�[�̂����l�ƒ��������������������� ����X�|�[�c���q�ł�����܂��B���̐��т��ǂ��悤�ŁA�F�X�Ȃ��Ƃɍ˔\�� �����Ă���l�ł��B �@�s�A�m������Ă��邩�琬�т��U���Ȃ��E�E�E�Ƃ����l������悤�ł����A �\���C���̐��k���������Ă���ƁA�R���N�[���ȂǂŊ撣���Ă��鎞�ɂ� �w�Z�̐��т���Ⴕ�Č��シ��q�������A�撣���Ă��鎞�͉��ł��撣��� ���܂��̂��ȁA�Ɗ��S���Ă��܂��܂��B �@����͐e�q�s�A�m�A�e����ł�����l�̗R�I�q����Ƌ��ɘA�e���A�ŗD�G�܂� ��܂��܂����B �@�Q����Baby�\���C���N���X�ɓ������A����l�ƈꏏ�ɖ{���ɐS���特�y�� �y����ŁA�L�ѐL�тƃs�A�m�Ɛ��y�Ɏ��g��ł���^�킳��B���̌���Ȃ� �\����T�ɋ��鎄�������ꏏ�Ɍ��Ă�����̂͊y���݂Ȃ��Ƃł��B �@������������萬�����A��ւ̉Ԃ��炩���邱�Ƃ�����Ă��܂��B
- 1��11���i�y�j�x�X�g�Z���[�Ɋw�ԉ��y�̃��b�X���@
�@�F�l�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���U���炸���Ɨǂ��V�����A �K��̗ǂ���N�̃X�^�[�g�ł��B�n���V�ɋ삯�オ���Ă䂭�悤�ȁA�ǂ���N�� ���������̂ł��ˁB �@����̔N���N�n�́A���x�݂��[�����������Ă������x�ނ��Ƃ��ł��܂����B ��D���Ȓ��Q�V���ł�����A���q�̃X�L�[�ɕt����������i���N�͘A��Ă����� ���Ă��邾���ł����I�j�A�������������������A�T�����炻�̂܂܂��������z���� ������������A�ǂ݂��������{���܂Ƃ߂ēǂ�c�A���˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�A ��肽���������Ƃ��܂Ƃ߂Ăł����M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B �@���_�I�[�d�͉��Ƃ����Ă��Ǐ��ł����B�S�O�O�����Z�[���X�̕S�c���B�� �w�i���̂O�x�A�������S�c���̍�N��P�O��{����܂���܂����P�V�O�����˔j�� �w�C���Ƃ�ꂽ�j ��E���x�A�r�㏲���̐V���w�w�ё�����́x�̌v�R��B �@���Ԃ������ēǂޒ��̂��Ƃ͂Ȃ������Ƃ������z������x�X�g�Z���[���������A �S�c���̒���͑����̋��P���܂ޓǂ݂������̂�����̂ł����B���{�̐l���� �R�O���̂P�ȏ�̍��������ꂽ�w�i���̂O�x�Ɓw�C���Ƃ�ꂽ�j ��E���x�� �N���ɓǂ߂����Ƃ͎��ɗL�Ӌ`�ł����B �@�i�n�ɑ��Y�̒��N�ɘj��x�X�g�Z���[�w��̏�̉_�x�́A���I�푈�̓��{�� �C�R�E���R�̍��ƃ��V�A�Ƃ̍U�h��������ł��B���E�C�o���̍��ƍs�R�� �P�P�Ȗ��ɏ������ƂŁA�v��ƌ��f�A�����Ď��̉^(�c�L)�̑��������� ���Ă��܂��B �@�_�c�̌Ö{���X�Ńg���b�N��t�A�P��ɂ��Q�O�O�O���~���̌Ï����w���� �������ƌ�����i�n�ɑ��Y���B���j����O��I�ɋ���A���̃G�b�Z���X�� ���W���������̂����̖c��ȍ�i�Q��������ł��B �@�i�n���̒���Ɍނ���Ǝv����͍�w�i���̂O�x�́A�e�Ɋp�A����_�ɕ肪���� ��̑��ł̓��{��R�i���ɓ��U���j�̍U�h���A�����̏W�ƃC���^�r���[�ɂ��A �ǂ̍�킪�N�̎w���ōs���A�N�̌��f��s���ɂ���Ăǂ̂悤�Ȍ��ʂɎ����������A �������ڂ��A�`���Ă��܂��B�i�~�b�h�E�F�C�C�킵����A�K�_���J�i���킵����A ����̊C�E���̍s��������E�E�E�B�j �@���̕��a�ȓ��{�ł́A���̖{�̒��ɏ����Ă��邱�Ƃ�푈�Ɍ��т��ċ��P�� ���ׂ����Ƃ͂���܂��A�����ɍ��i���O�����ƌv��j����Ȃ��̂ł��邩���A �d���⋳��ɒu�������čl���邱�Ƃ͏[���\�ł��傤�B �@�w�C���Ƃ�ꂽ�j ��E���x�́A�o�����Y�𗧂��グ���Ƃɔ��W�������o�����O�� �l����`���Ȃ���A�����푈�̍U�h������{�̐����E�O���E�����̑Ԑ���A���E�� �Ζ��ƊE�̍\����`���Ă��܂��B���O������w�o�ł͂�����̂́A��O���̖��� �����菤����X�^�[�g���A�����ɐl�ނ����炵�A�H�v���d�ˁA�����ɂ��������� ���Ƃ��g�債�Ă��������A��ɐl�̂��ߓ��{�l�̂��߂Ƃ����g���`�h��Y�ꂸ�A �����Ɏ������~��ǂ�Ȃ��������������l���ł����������`����Ă��܂��B����� �P�̃��f���ɂȂ鐶�����ł��B �@�w�w�ё�����́x���A�����l�ɓ`���邱�Ƃ̈Ӗ��ƕ��@�������Ă�����i�ł��B �r�㎁�́g���{�h�Ƃ����������ňꊇ��ɂ��Ă��܂����A���������N�������߂ɂ� ���N�O����̒~�ς�����Ɛ����Ă��܂��B��w������A�@���A���j�A�o�ϓ��̒m�� ������B�������̌o������A���̃X�e�b�v�i�ށi�r�㎁�̏ꍇ�͓]�E�j�ۂɑ�� �������̂��A�����O����~�ς��Ă��������̋��{�������Ƃ�����ł��B �@�Ⴆ��������y�̃��b�X���ɒu�������Ă݂�ƁA�V�����Ȃ�搶���炢�������� ���������鎞�A�\���t�F�[�W���͂��������特��莩�̂Ɏ��Ԃ�����邱�Ƃ� ����܂���B�O����b�c�Ȃǂ��Ă���Ȃ�������A�ȑz���牉�t�X�^�C���܂� ���R�Ɏ����̒�����N���オ���Ă���ł��傤�B���̎���ɂ��Ă̖{��ǂ� �f������Ă�����A���̒��ł͋ȂƋ��ɕ��ꂪ�o���オ���Ă���͂��ł��B��w�� �ł�������{�ɏЉ��Ă��Ȃ����̋Ȃ��ȉƂɂ��ẴG�s�\�[�h������ł��܂��B �ł�����A�e�N�j�b�N�I�Ɏ���Ȃ��Ƃ��낾���Ɏ��Ԃ��|���ė��K����Ηǂ��Ƃ��� ���ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A������l���̑S�Ă̎����ɂ����Ă���ł��ˁB �@�Ƃ�����ŁA�����̖{����̃��b�Z�[�W��O���ɁA���̈�N���߂����Ă��������� �v���Ă��܂��B �@���N���X�~�����肢�������܂��B
- 12��7���i�y�j���얃������̎v���o
�@����A��w����̓��������S���Ȃ�܂����B ���w���̔N��A�P�W����R�P�܂łƕ��L���N��w�̊w�N�̒��A�ޏ��Ƃ͓����ŁA ���̌�P�N�����x��Đi�w������w�@�̃I�y���Ȃ��ꏏ�A��w�@�C����ɗ��w�����ꏊ�� ���Ԃ��d�Ȃ��āA���ɗ��w���ƂĂ������ǂ������F�l�ł����B �@�ޏ��̖��O�͐��얃������Ƃ����A��Ϗ��ȃ��]�\�v���m�̎�ł����B�ŏ��ɔޏ��� �̂����̂́A���Z�R�N���̎��ŁA�m�g�j�e�l���W�I����w���{�w�����y�R���N�[�� ���Z���̕��S�����x�̘^�������R����Ă����̂����̂ł����B����Ȃɐ��n���� �����ƕ\���͂̐l�������Ȃ̂��A�Ɯ��R�Ƃ����̂������Ă��܂��B���̍��悭������ �s���Ă��������̃v���̎肽���̉��t����肾�Ǝv���܂����B �@��w�ɓ��w���Ă݂�ƁA�\�z�ʂ�A���̉̐��̎�͓������ŁA���ۂ̂��̐l�́A�ڂ� �ς�����Ƃ������̗ǂ����������̂���l�ł����B �@��w�̗��K�����畷�����Ă���ƂĂ��P�W�̏��̎q�Ƃ͎v���Ȃ������x�̍����̐��ɁA ���ꂩ��K�����Ȃ�������Ȃ������̋�̓I�ȖڕW������v���ł����B �@���w����A�ޏ��͂������ɏ�肩�����̂ɁA�����Ɋւ��Ĕ����×~�ł����B�ޏ��� ���܂ŏK���Ă����搶�̂��ꂼ��̋������ɂ�艽���ǂ̂悤�ɏK���ł������A�܂��A �t�ɂǂ̂悤�ȂƂ��낪������Ȃ��������ȂǁA��̓I�ȗ�������Ȃ��炻�̌o���� ����Ă���܂����B���ƂȂ����͋C�◬��ʼn̂��̂ł͂Ȃ��A�����̃e�N�j�b�N�� �������g�̑̂Ŋm�F�����t�ɂł���l�������̂ŁA���y���t�Ƃ��Ă��D�G�������͂��ł��B �@���삳��́A�T�O�ΖڑO�Ő��y���n�߃v���̃\�v���m�̎�ɂȂ����r�c����q����� �搶�ł�����܂����B �@�܂��A���l�̒����J���`���[�Z���^�[�̐l�C�u�t�Ƃ��āA�����̐��k�������Ă� ���܂����B �@�̎�Ƃ��ẮA�����̃I�y���ɏo��������A�ӔN�i�Ƃ����ɂ͎Ⴗ����I�I�j�́A ���L�u�����ẪR���T�[�g�̋����҂Ƃ��Ċ��A�w���E��������Ɓx�ɂ� �o�����Ă��܂����B �@��m��Ȃ��߂���������Q�����ʖ�ł������A�ӊO�ɂ�����l���Ί�ŁA �u�����́A��肽�����Ƃ�S�Ă��s�����ĖS���Ȃ����̂ŁA�߂��܂Ȃ��ł��������B�v �Ƌ����̂ł��B �u�̂����ŕ�����Ȃ��Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ������A����܂Ŏv�������̂��Ă�����ꂽ�B �@�l�ɂ��b�܂�{���ɍK���Ȑl���������B�v �ƌ��A�S���Ȃ鐔���O�ɘ^���������������Ă���܂����B �@�l�͂����S���Ȃ���̂ł��B�������ł��������̂��Ƃ��������Đl���̏I���� �}����A����̂Ȃ��������͑f�G���A�Ǝv���܂����B �@��킭�A�����̐l���ɐS���疞�����A����̕��X�Ɋ��ӂ̌��t���q�ׁA�ޏ��̂悤�� �l���̖�����������̂ł��B �@�l���ɂ͏I��肪���邩�炱���A�ڕW�������Č����ɐ�������̂��ƁA�������� ������ꂽ�C�����܂��B �@���O�̘^���You tube�ɍڂ��Ă��炦��悤�A����l�ɂ��肢�����܂����BUp���ꂽ��A ���삳��̑f���炵���̐����ĉ������B �@���N���킸���ƂȂ�܂����B���N���f���炵���ɂȂ�܂��悤�A�F�l�̂����N�Ƃ��K���� ����Ă��܂��B
- 11��2���i�y�j��Q�V�� �Q�n���s�A�m�R���N�[��
�@10��20��(��)�A�O���s�̃e���T�z�[���ɉ����đ�27��Q�n���s�A�m�R���N�[���i��ѐV���Ў�Áj�� �J�Â���A�W���̗\�I��ʉ߂��{�I�ɃG���g���[���Ă����\���C���̐��k����Q�����Q���Ƃ��D�G�܂� ��܂��܂����B �@���w�R�E�S�N���̕��ɏo�ꂵ����������N(����܍��ۃA�J�f�~�[�R�N)�́A�P�N���̎��A ���w�P��Q�N���̕��ɏo�ꂵ����܂����(�P��Q�N���̕��ł͍ō���)�B�Q��ڂ̒���̍���́A �{�ԂŏW���������t���ł��A�D�G�܂�Ղ��܂����B �@���w���̕��ɏo�ꂵ������Е��N(���c�����P�N)�́A���w�R��S�N���̕��œ��I�A�Q��ڂ� ����ŗD�G�܂�Ղ��܂����B �@����̒��w���̕��̖{�I�ۑ�Ȃ̓u���[���X�́s���v�\�f�B��Q�ԁt�ł������A������� �u���[���X�A�Ɠ��̉��[�����F���o���̂ɑ啪�ꗶ���܂����B����̃R���N�[���ɒ��킵�� ���ƂŁA���w����ɁA�Ƃ�����ƃX���[���Ă��܂��\���������u���[���X�ɂ��������� �g�ނ��Ƃ��ł������Ƃ͗L�Ӌ`�Ȍo���������Ǝv���܂��B�w�����������Ƃ����y�I�ɉ��t���� �Ƃ����A�ʏ�R���N�[���ŋ��߂���ϓ_�����łȂ��A���̕����O��I�ɗv�������u���[���X�� �G��邱�Ƃ́A�����ɘj���ăs�A�m�ɌW����Ă����q���B�ɂƂ��āA�M�d�ȋZ�p�K���̃`�����X�� �Ȃ�܂����B�s�A�m�����łȂ����ɂƂ��Ă��u���[���X�������ǂ����������ɂȂ�܂����B �@�����q�ǂ��̍��A�h�C�c�̋Ȃ͓��{�ł����E�ł��嗬�s���Ă��āA�t�B�b�V���[�E�f�B�X�J�E�� �y�[�^�[�E�V�����C���[�A�V�����@���c�R�b�v�t�A���m���B�b�c�A�A�������N�A���{�ł������� �d�������ɂ��h�C�c���[�g�i�̋ȁj�̃R���T�[�g���ڔ������ł����B����Ƀe���r���f����܂� �����A�w���y�̗F�x����e���r���f�ʼn��������O�̉̎�̃��[�g�𓌋��܂ł悭�����ɍs���܂����B �@�̂͂��Ȃ̂Ɂc���m���B�b�c��A�������N�A�V���o���c�R�b�v�t�́A�`���[�~���O�ŁA�ό����݂� ���t�Ɛ��̃��[�c�@���g��V���[�x���g�A�V���[�}���͉����Ă���̂ɁA�u���[���X�����L���� �c�Ȃ��̂ł�!! �����ł��h�C�c���[�g���̂������Ƃ͖ܘ_����������ǁA����������Ńu���[���X�� ���p�[�g���[�ɂȂ邱�Ƃ�����܂���ł����B���y�j�I�ɂ͏d�v�Ȑl���ł��邵�A�s�A�m�ȁE�̋� �Ȃnj��肵�����삾������Ȃ����l�Ƃ�����ł͂Ȃ��̂ɁA�nj��y�Ȃ��s�A�m�Ȃ����G�ꂸ�ɍ��܂� ���Ă��܂��Ă��܂����B �@����̉ۑ�ȃ��v�\�f�B��Q�Ԃ̊y�ȕ��͂����݂܂����B�r�ӐW��Y���̃u���[���X��i�� �������ǂނƁA���̍�i�̊y�ȕ��͂̂���肪�����Ă���̂ł����A�����Ă��邱�Ƃ𗝉� ���邱�Ƃ͂ł��Ă��a���������x���̎��̘a���͂ł͕��͓͂��ꃀ���ŁA����搶�̗͂����� ���Ă�����ƕ��͂��đՂ��܂����c�������Ƃɏd�����ē]�����Ă��邽�߁i���`�I�����j�A ���͕͂��G�ɂȂ�A�Q�̒����̘a���i�s���d�Ȃ��Ă�����������������A�����͌ÓT�h�� �悤�ł��āA��͂������}���h�̍�i�Ȃ̂͂������Ⴄ�̂ˁA�ƍ��_���������肵���̂ł����B �@���`�I�a���̐i�s�₻�̌��ʍ��������a���ɂ������܂������A��͂��ɏq�ׂ��悤�� �g�u���[���X�̉��h�ɂ͍Ō�܂ŋ߂Â����Ƃ͓�������Ǝv���܂��B �@88���A�V�I�N�^�[�u�ȏ゠�錮�Ղ́A��ԉ��̂P�I�N�^�[�u�������Ɍ���邻�̒ቹ���A �t�H���e�ŏ[���ɋ������ĉ��t����ɂ́A����Ȃ�̑̂̑傫���Ƙr��w�̑������K�v�ł��B ���w���������ȑ̂ł��̉����o���ɂ́A���͂���[���ቹ�̃C���[�W����������Ǝ����āA �E�͂��ł�����Řr���悹�Ă����e�N�j�b�N���K�{�A�Ƃ̓s�A�m�̐搶����J��Ԃ�����ꂽ �A�h���@�C�X�ł����B�������Ȃ���A�܂����̒ቹ�̃C���[�W�����̂��Ȃ��Ȃ�������� �悤�ł��B �@�s�A�m�́A������ȉƂ̍��ЂȂǃ��p�[�g���[������ɘj���Ă��āA��i�����s���ɂ���A ���̂�����������y��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����߂Ēm�����@��ƂȂ�܂����B �@�����܂��������N�E����N��(�ܘ_�A�撣���Ă���F����S���I�I)�A���ꂩ��l�X�ȋȂ� ���킵�A��B���Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B ��܁A���߂łƂ��������܂���!!
- 10��5���i�y�j�|�p�̏H��DVD
���{���c�f������^�̑䕗��p�ɂɋN���������ŁA�V�n�n���̂悤�� ��r��̂X�����߂��A��N���߂����₷���H�炵���̊�������P�O���� �Ȃ�܂����B �@�傫�ȍs������i�����A�����������ł��邩�Ǝv������A�������ɘj���� ���܂��Ă����d�����h�b�Ɖ�������A�q�������̃R���N�[���̎d�グ��������A �}�Ɍ��܂����v�̓]�̂��ߖk�C���ɍs���Ă�����ŁA�h�^�o�^�̂X�����߂����܂����B �P�O�O�������̎��Ԃ������Q�O��́A�w�Z�ɍs���ĕ��Ɨ��K�������Ă���悩��������� �����̂Ȃ̂���A�ƃZ���`�����^���ɂȂ�ɂ͗]��ɂ��킵�Ȃ��A����ł��Ă��̂��킵�Ȃ��� �y���݂Ȃ�����X�𑗂��Ă��܂��B �@����ɂ��Ă��A�Ǐ���f���DVD���ς�]�T���炢�͗~�����B�{������ɍs���� �{��I��ł���Ɩ����ăt���t�����邵�A�܂��Ă͖{��ǂݎn�߂���DVD��ON�ɂ���� �m���̂܂ܒ����}���Ă��܂����肵�āi�����Q�Ă��܂��Ƃ����Ӗ��j�A�s���Ǎ����@������ ���S�Ƀ}�X�^�[���Ă���Ƌ����Č����錻�݂̏ł��i���������Ƃł��ˁj�B �@���ԂƑ̗͂����鎞�ɂ悭�ς�̂́A���q�ɕt�����킳��邱�Ƃ����� �w�n���[�E�|�b�^�[�x�V���[�Y�Ȃǂ̃t�@���^�W�[��w�V���[���b�N�E�z�[���Y�x�Ȃǂ� �T�X�y���X�~�X�e���[�ł����A�w�O�O�V�x��w�~�b�V�����E�C���|�b�V�u���x�Ȃǂ̃A�N�V�����A �����l���Ă��Ȃ��Ƃ��ς�̂Ɉ�Ԃ悢�̂��R���f�B�ŁA�w�����[�Ɏ�������x�� �w�V�R�ӂ�����x�͂��܂�ɂ�����Ȃ��ăz���g�ɉ����ł���B �ߍ����Ă��Ȃ��l�ɂ͂����߂ł��B �@�w���݂ɓǂޕ���x�w���E�~�[���u���x�Ȃǂ̏����f���h���}�ɗ܂�����A�w�t���K�[���x�Ȃǂ� �����T�N�Z�X�E�X�g�[���[����D���ł��B��w�̕��ɁA�t�����X�f��E�C�^���A�f������܂��B �t�����X�f��͌��������̂܂܉f��ɂ����悤�ȓ��e�������A�n���E�b�h�f��̂悤�Ɋ��P�����E �n�b�s�[�G���h�Ƃ�����ɂ����Ȃ��āA�u����ŏI���H�v�Ƃ������z�ɂȂ��Ă��܂���i�� �����̂ł����E�E�E�B �@�C�^���A�f��w���C�t�E�C�Y�E�r���[�e�B�t���x�w�،C�̖x�͋��ɃW�[���Ƃ�����̂�����A ����ςĂق�����i�ł��B�E���x���g�E�G�[�R����́w�K�N�̖��O�x��A�_���E�u���E������� �w�_���B���`�E�R�[�h�x���A�G��⎖�ۂ�ǂ݉����Ă����Ƃ����L���_��C�R�m���W�[�w�� �T�X�y���X�f��ł����A�{�Əƍ����Ȃ���ς邱�Ƃ��ł����A���e�����[���̂Ŗʔ����ł��ˁB �@���j��̉��y�Ƃ���l���̉f��͕K���ς�悤�ɂ��Ă��܂��B����l������Ă��Ď���w�i�� �悭������L�v�ł��B���̓����̊y��̉��ł�������A�����ł�������A���������A����̂� �ǂ��ł��ˁB�^�C�g���͖Y��Ă��܂��܂������A�̊ς��f��̒��ɍ�ȉƃh�r���b�V�[���o�Ă��āA �̎�ƃA���T���u���������ʂ�����܂����B�A�b�v���C�g�s�A�m�̏�ɕ��ʂ��Ƃ炷���E�\�N�̓��A ���E�\�N�ȏ�̖��邳���Ȃ��Â���̒��ŋ����h�r���b�V�[�̉̋Ȃ́A���̘a���̃C���[�W����������A �]�N�]�N����悤�ȃp���̃T�����̕��͋C�i�����܂Ŋ�������悤�ȗՏꊴ�j�̒��ŁA �{���̋P��������Ă��܂����B �@���ڂɊς��Ƃ��͊��������̂ɁA���x���ς�ƌ����̈ӊO���ɋ�������Ă����������������Ƃ� �C�Â����ꂽ��A�t�ɉ���ςĂ�����Ɋς��Ƃ��̊������h��f�������܂��B�w�T�E���h��I�u� �~���[�W�b�N�x�w���[�}�̋x���x�͉f��̒�Ԃł����A�S�҂ɘj���Ċ����I�ȏ�A��ʂ��Ƃɂ� ���ǂ��떞�ڂł��B �@���N�́A�t�́w���t�@�G���W�x��������A��D���ȃ}���G�b���E�f���B�[�A�̗����������s���� ��X�Ƃ��Ă����̂ŁA�|�p�̏H�Ƃ������Ƃ�����A�G����ÓT�|�\�i�s�v�c�ƎO�����Ⓑ�S���� ��ꂪ������c�j���I�y�����f����Ϗ܂��邼�`�A�Ƒ������Ă��܂��B �@�|�p�͎���s���̂��ܘ_�悵�A����NJӏ܂���̂���̊O�ǂ����̂ł��B�F�X�Ȍ|�p�ɐG��� �[�������H�����߂����������B
- 9��7���i�y�j�\���C���R�O���N�L�O�R���T�[�g�听��!!
�@�\���C���������y�����R�O���N�L�O�R���T�[�g�������I�����܂����B ���C��������蕿�̎���������Ɣ����k�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�v���O�����ɂ��������悤�ɁA��ɐ��k�����Ƃ̃��b�X���ɖ������A �ΊO�I�Ȋ�����w�ǂ����A���Ԃɕs�`�����������ȓ���𑗂��Ă���̂ŁA �����������̎��ɂ��q�l�����U��������@�������炸�A�{���̂Ƃ��� �r���ɕ��Ă��܂��Ă����̂ł����B�@ �@�W�O�W�Ȃ̉�ꂪ�P�O�O�Ȃɖ����Ȃ�������ǂ����悤�I�K���K���̉��� �g�L�O�R���T�[�g�h�Ɩ��ł��ĊJ�Â��Ă����t����l�����̃��`�x�[�V������ �オ��Ȃ����낤���c�c�B�@�@ �@���ۂP�����O�܂ł���ȏ�Ԃ������̂ŁA�����̐S�z�̎�͏����܂���ł����B �@���̃G�b�Z�C���n�߂����ɑ�H�̓����ł���c�����j���̘b�������� ���Ƃ�����܂��B �u�ꐶ�H����E�l�Z�Ȃ�ĂȂ���ł���B���͂P�O��Ŋo�������Ƃ� �@�Q�O���H�����B�Q�O��Ɋo�������ƂłR�O��ɏ��[�q����{���Ȃ���A �@�S�O��T�O��܂ŐH������������B�R�O��������Ɖ߂�������́A �@���߂���Ȃ����ȁB�N�����ɂ�邱�Ƃ��l�����Ȃ��ƁA�T�O��ɂȂ����� �@�|���R�c�����B�v �@���͂��̌��t������̃R���T�[�g�̍��E�̖��ɂ��Ă��܂����B���̂R�O�� �S�O����|���Ė����Ă����Z�ƁA�����Ă��̔N���ɒz���Ă������k�̊F����Ƃ� �M���W���m���Ȃ��̂ł������Ȃ�A���̃R���T�[�g�͂����Ɛ�������ƁA ���������C�����������Ă����̂ł��B �@���̓����͂���Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B �u�^�ʖڂɃR�c�R�c�Ƃ���Ă����҂������A�w����͂���˂��x�A �@�w�����ň꒚�q���Ă݂�x�ƁA�m�V�̐��n�����Ƃ��ł����ł��B �@���ꂾ������t���������A���Ƃ͓V�̐��ɔC���Ă݂悤���A�Ƃ��� �@�S���ɂȂ�̂�������Ă����ł���B�v �@�܂��ɂ���ȐS���ł����B �@�����܂łǂ��Ȃ邩������܂���ł������A���V�C�ɂ��b�܂�A�F�l�̂����͂� �吨�̕��ɒ����Ă����������Ƃ��ł��܂����B �@�I����A��R�̃A���P�[�g�����������܂����B���ꂼ��̕������ꂼ��̊ϓ_���� ���������Ȃ₻�̓��e�A���͉��P���������悢�Ǝv���_�Ȃǂ��L�����ĉ������܂������A �S�̓I�Ȋ��z�����łȂ��A�P�Q�ȑS�Ăɂ��āA�ǂȂ��������z�������ĉ������Ă��� �̂ɂ͋����܂����B �@�i��ɂ��āu������Ȃ��_�W�����͂���Ȃ��v�A�u�������������v�Ƃ����l�� �����(���)�A�Ȃ̉�����������̂ʼn���������Ȃ��Ă��y���ނ��Ƃ��ł����A�Ə����� ������������܂����B �@������̍��G���`�N���Ǝw�E���ꂽ��A�l�X�Ȋy���̂Ƃ��̑g�ݍ��킹�A �܂����Ȃ̌`���i�^���S�A�����c�Ȃǁj�����ʂŋȏ����ǂ��A�O���Ȃ������� �����ĉ��������������܂��B���������������̂́A�A���T���u���̑��������Ă��āA �S���̘a�ƈ��Ɖ��y�ɑ����M���`����Ă����A�Ə����Ă��������Ƃł��B ����������ɂ��Ă���A���y�ɑ���g�v���h�������Ă����������̂���Ԋ��������Ƃł����B �@������ɂ���A��|����ȍÂ��ŗ����ɓO����l�����Ȃ��Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ���ςȂ��ƂȂ̂� �Ƃ������Ƃ��w�@��ł�����܂����B �@����͂T�N��ɂȂ邩�P�O�N�ォ�E�E�E�A�\���C���̐��k�̒�����A���S�ɂȂ��Ă���Ă���� ���t�Ƃ��ǂ�ǂ����Ă����Ǝv���̂ŁA���̐l�����ɕ���͔C���A���͗����ɓO��ł���悤�ɁA �w���ɗ͂����Ă��������Ǝv���܂��B �@����I�ɓ����悤�ȃR���T�[�g���J�Â��Ăق����Ƌ��ĉ�����������܂����B�L����Ƃł��B �R���T�[�g�ɂ��Ă��O�����ɐi��ł�������Ǝv���Ă��܂��B
- 8��10���i�y�j�Q�n���s�A�m�R���N�[�����ԕ^�\���C���R�O���N�̋���
�@�s�R�O���N�L�O�R���T�[�g�t�̏����ōQ���������߂��������A�W��������� ���܂����B �P�O�N�U��̑�|����ȃR���T�[�g�Ƃ������Ƃ������āA����������щ���� �������Ă��܂��B �Ă͎q�������̃R���N�[���̋G�߂ł�����A���̎w���ł����͂𒍂������ł��B �W�����{�ɍs��ꂽ�Q�n���s�A�m�R���N�[���̗\�I�ł́A�G���g���[���� �\���C���̐��k�Q�l�����ɗ\�I��ʉ߁A�{�I�o�ꂪ���܂�܂����B �@���w���R�E�S�N�̕��ɃG���g���[������������N�͂V�X���̒�����P�T���A ���w���̕��ɃG���g���[��������Е��N�͂R�X���̒�����P�Q���̓��I�҂̒��ɓ���A 10��20���i���j �O���e���T�z�[���ł̖{�I�ɏo�ꂵ�܂��B�ċx�ݒ������K�ɐ����o���A �����ȏ��������A�[���̒��𐮂��ė͂��o���Ă��ė~�����Ǝv���Ă��܂��B �@����A�R�O���N�̏����ɗ]�O���Ȃ��P�Q���̏o���҂����́A����̃v���O������ �A���T���u�����������Ƃ���A���Ԃ�����Ă͏W�܂��č��킹�̗��K�����Ă��܂��B �@����A���M���ׂ����ڂ̓s�A�m�̂S��ƂW��̃A���T���u���ł��B���i�\���Œe�� ���Ƃ����|�I�ɑ����s�A�j�X�g�����́A���̍������������y���݂ł��B���݂��Ɉӌ��� �o�������Ȃ���A���X���~�̂��Ƃ�̒��A��̉��y�ɗ���グ�Ă����Ă���l�q�B ���݂����Ԃ������Ȃ�������a�ݏo���āA����߂��̂��鉹��a���o���ė~������ ����Ă��܂��B �@���y�l�d�t�̓A���T���u���̊�{�ł����A�`���C�R�t�X�L�[�̌��y�Z���i�[�f�� �t�@�����������Ƃ���A�A���T���u���̃v����������w�^���Ɏ��g��ł��܂��B ���i��ΐ搶�̂Pst���@�C�I����������S�l�̑t�҂́A�Qnd�̐X�F�I������o�b�N��A�b�v ���Ȃ�����K�ɗ]�O������܂���B�����ƃX�e�L�ȃ����c���t�ł��邱�Ƃł��傤�B �@���y�l�d�t�ƃs�A�m�Ɖ̂̋������M�������d�����������o���A�S�n�悢��������� �グ�Ă��܂��B �@���t�Ҏ��g���y����ł��܂��Ă��鉉�t��́A���q�l�ɂ͋��S�n��������������� �ł����A���K�ł͔��������̏d�Ȃ��S�䂭�܂Ŋy���܂��Ă��������Ă��܂��B �@�V�����ɂ悤�₭�o���オ���Ă����s���{�̉̃��h���[�t�́A����k���搶���R������ �|���ĕҋȂ����͍삾�������āA��������d�Ȃ荇���������������ʔ�������i�� �d�オ��܂����B��������t���ċ�����Ă䂭�͎̂������̗͗ʂł����A�ҋȂ� �����Ȃ��悤�ɁA���G�Șa�����Z���X�悭���t���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �@�v���A�w���͂���D�G�ȍu�t�c�ɏ����`�Ŏn�܂�A���c�̎q�������ɁA ���b�X���̒��Řr�O���オ���Ă������Ƃ��������Ăق����Ɗ�������̎�����A �R�O�N�̍Ό������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@����̂R�O���N�L�O�R���T�[�g�ɂ͏o�����܂��A���X���̃G�b�Z�C�ł� �Љ�Ă���悤�ɁA�吨�̑f���炵���\���C���̑��Ɛ��������A���{���A���E���� ���Ă��܂��B�R�O�N�̊ԂɈ�������Ɛ��������ꓰ�ɉ��R���T�[�g���A ��悵�Ă��������Ǝv���Ă��܂��B �@���X�������Ƃ��J��Ԃ����Œ~�ς��ꂽ�G�l���M�[�́A�v���������傫�����̂� �Ȃ��Ă��܂����B���ꂩ����A�O�������ĕ���ł����������̂ł��B
- 7��7���i���j�A�C�h���a���I
�@��T�̌|�\�j���[�X�������ɂȂ�A������A�ƋC�t�����l�������ł��傤���E�E�E�H �ȑO���̗��ł����`���������Ƃ�����A���w�R�N���̂��̐_�{���I����A���ƁA �s�����p�t�H�[�}���X�h�[���t�Ƃ����A�C�h���O���[�v�Ńf�r���[���܂����I�I �@�ȑO�����q���������Ă����O���[�v�̍Đ����Ƃ������ƂŁA�f�r���[�L�҉���� �|�\�j���[�X�Ɏ��グ����ȂǁA���ڂ𗁂тĂ��܂��B �@�\���C���ł̃s�A�m�ƃ\���t�F�[�W���̃��b�X�����A���w�Z�̊nj��y���ł� ���@�C�I������������Ƃ��Ȃ��Ă����A�S�R�o����肶��Ȃ��L�����N�^�[�� ���I����A�A�C�h���O���[�v�ʼn̂��ėx���Ă���Ȃ�āA������ƐM�����Ȃ� ���������Ă��܂��B �@�R�����瓌���ŕ�炵�n�߂邱�ƂɂȂ�\���C���𑲋Ƃ������I�����ł����A ���w���ɂȂ��Ă���Q�N�Ԏ��_�J���搶�̃��H�C�X�g���[�j���O���b�X���� �t�������̂ł��傤�A�̂����ɂȂ�A�����ƃO���[�v�̒��ł��̂����[�h���� ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂�(�����܂Ŏ��̊�]�I�ϑ��ł����E�E�E�j�B �@�V�Ȃ̏����Ȃǂ̃\���t�F�[�W���͂�����̂ŁA���y�Œ��Ԃ����������Ă����� ���ꂽ��ǂ��ł��ˁB�ł������̂�т肵�Ă���l�Ȃ̂ŁA�������狰�炭 �A�s�[�����Ȃ��ł��傤����ǁE�E�E�B �@�p�t�H�[�}���X�W�c�Ƃ������ƂŁA�a�J�́s�b�a�f�j�V�u�Q�L!!�t�Ƃ�������ŁA ��ɕ���ɗ����p�t�H�[�}���X�����Ă��邻���ł��B �@�ςɂ������������́A����a�J�ɍs���ĉ������Ă����ĉ������B �@�N���b�V�b�N��������Ȃ��I�\���C�����������l���܂������o���܂����B �@�ǂ̕���ɂ����Ă��A�\���C���Ŕ|�����g�g�R�g����鐸�_�h�������āA�h������ �撣���Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
- 7��6���i�y�j�\���C���R���T�[�g�i���� ���\��j
�@ �@�U���Q�R���̃\���C���R���T�[�g�ł́A�o�����ꂽ���k�̊F���A �W���x�̍����A��ϑf���炵�����t�����Ă���܂����B �@�w�ǂ̐��k���A�~�X�̂Ȃ����y�I�ȉ��t�ŁA�ْ����̂���R���T�[�g�� �����Ɋ�^���Ă���܂����B �@���k�����̔��\��Ȃ̂ɁA�h���\��h�Ƃ������̂��g��Ȃ��Ȃ��� ���N�ɂȂ�܂��B�����x�̍����R���T�[�g�̂悤�Ȏd�オ���ڎw���Ƃ��� �v�������߂āh�\���C���R���T�[�g�h�Ɩ��ł��āA���̈Ӑ}���F����ɓ`���A �w�����Ă��܂����B �@�R�`�S�̗c�������l�܂ŁA�N���u�]����i�H�ɊW�Ȃ��A���ꂼ��� ���x���ōō��̗͂�����悤���߂Ă��܂����B �@�u���Ȃ��B�̉��t�����߂ɂ킴�킴���Ԃ������ė��Ă������������q�l�́A �l���ς��ς��悤�ȉ��t������̂�v�A�u�������Ⴈ���ƍl���Ă����l���A ���Ȃ��̉��t�����玀�ʂ̂����炵���Ȃ����A�]��ɑf���炵���Đl���� ��]���������A���Ă�����悤�ȉ��t������́v�Ƃ��A�u���q�l�́A�Ԉ���� ���t���m�F���邽�߂ɗ�����Ȃ��̂�����A�����~�X�������Ă������Ȃ����� �悤�Ɍq���Ă����̂�v���A�R�E�S�Ύ��ɉ����������Ȃ����A�Ǝv����悤�� �v�������Ă��A��������Ɨ���������ŁA�p�t�H�[�}���X�����Ă����̂ł��B �@���̂悤�Ȏw���𑱂��Ă��邤���ɁA���������ł͂Ȃ��d�グ�����K���ɂȂ�A ����قǃL�c���v���Ǝv���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��傤���A������������O�̂悤�ɁA ����̃��n�[�T�����d�ˁA�^���Ŗ��x�̔Z���{�Ԃ��}���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B �@�ܘ_�A���Ŏx���Ă��������Ă��邲�Ƒ��̉��������ẮA���̊����x�ł��B �����Ȃ���A�����͂��������Ă��邲�Ƒ��̊F�l�Ɋ��ӂ������܂��B �@�R���T�[�g�̍Ō�ɃA�i�E���X�����Ă����������悤�ɁA���ꂩ��R���N�[���� �Ղސl�́A���̉��t���ŏ�Ƃ����A�R���T�[�g�̔��ȓ_�܂��C�X�ɐS�ɟ��݂�悤�� �ǂ����t���ł���悤�A��w�̒b�B�����҂��Ă��܂��B �@
- 6��8���i�y�j�\���C���R�O���N!!!
�s�\���C�� �R�O���N�L�O�R���T�[�g�t�̃`���V�ƃ|�X�^�[�� �o���オ���Ă��܂����B �P�N�O�����悵�Ă����̂ɁA�̂�т肵�Ă�����A�`���V�� �|�X�^�[������オ���Ă����̂��R���T�[�g�R�����O�̂T�����A �|�X�^�[������A�\���Ă����������Ђ⏤�X��w�Z���Q�Ă� ��点�Ă��������Ă��܂��B �@�|�X�^�[���͂��������A�s���̖{���ʂ����ʂ�ɂ��� �m�荇���̏��X�ɁA�\���ĉ������Ƃ��肢����ƁA�F���� �u�|�X�^�[�Y��I�I�v�Ɗ��ʼn�����i�j�A�Q�Ԏ��ʼn����A �X���X�����s���N�ōʂ��Ă��܂��B�i�L��ł��I�j �@ �@����̃R���T�[�g�́A�\���C�����P�X�W�R�N�S���̑n������ ���N�łR�O�N���}����ɓ������āA���Ɛ��ƍu�t�̐搶�ŋL�O�� ���t���s���Ƃ������̂ŁA�\����A���T���u������荬���A���Ԃ� ������ׂ�Ōq���Ȃ���A�F����Ɋy����ł���������悤�A ������Â炵�Ă��܂��I�I �@�\���C���̃R���T�[�g�ł͏��o��ƂȂ�T�b�N�X�̐{�i�a�G�搶��A ���H�h�C�c���w����A�����A�A����A���ɓ��{�����łQ��̃��T�C�^���� �R���T�[�g���ɏo�����Ă���劈��̃s�A�j�X�g��a��i�^���搶 �i�a��搶�̓\���C���̑��Ɛ��ł����A���t����u�t�Ƃ��Ă��\���C���� ��i�̎w���ɓ������Ă��܂��I�j�ȂǁA���b��̃t���b�V���ȉ��y�Ƃ� ���t�����������������܂��B �@�{�i�搶�Əa��i�^���搶�́A�e�X�A�~���[��ȁs�X�J�����[�V���t�A �V���p����ȁs�p�Y�|���l�[�Y�t���A�\���ʼn��t���܂��B �@�\�����t�����邱�ƂȂ���A����̃R���T�[�g�̖����́A�o���҂P�Q���� �A���T���u���������߂�Ƃ���ɂ�����܂��B �@�x�e�����̈�ɓ�����(!!)�דc�G��搶�ƁA���т�ݐ搶�ɂ��Q��s�A�m�ł� �����F����ȁs���E���@���X�t�ł́A����ȑ�l�̉��y�����y���݂��������܂��傤�I �@���̗ǂ����e���̃��Y�������������A�����J�ւƗU���A�s�A�\����� �s���x���^���S�t�́A�דc�G��搶�E���т�ݐ搶�E�a��i�^���搶�E���Ɛ��� ����q�q�搶�̂S�l�ɂ��A���ȂQ��s�A�m�W��A�e�ʼn��t���܂��B�S�l�� ��M�I�ȃs�A�j�X�g�̔M�C���F�l�ɓ`��邱�Ƃł��傤�I �@���y��`�[�����ŋ��̕z�w�ł�!! �`���C�R�t�X�L�[��ȁs���y�Z���i�[�h�t�̑�Q�y�͂��A�Pst���@�C�I������ ���i��ΐ搶�A�Qnd���@�C�I�����ɑ��Ɛ��̐X�F�I����A�����āA���B�I��� �����̐搶�A�`�F����֓��͈�搶�Ƃ����A�܂��ɃS�[���f���E�J���e�b�g�� �����肵�܂��I �@���̑��ɂ��A���i�搶�̃��@�C�I�����Ǝ���搶�̃��B�I���ɂ��w���f����� �s�p�b�T�J���A�t�A�דc�搶�i�s�A�m�j����i�搶�i���@�C�I�����j�����搶 �i���B�I���j�ɂ��o�b�n��ȁs�C�^���A���t�ȁt�i�s�A�m��g���I����@�[�W�����j�ȂǁA �y��̕Ґ���ς��A���ʂɂ��͂����܂��B �@���y�g�R�l�́A�s�A�m�ƌ��y��Ɏx�����A�M��������ґ�Ȋ��ʼn̂킹�� ���������܂��B �@�e�m�[���̐_�J���搶���A���y�l�d�t�ƈꏏ�Ƀw���f����ȁs�I���u����}�C��t�t���A ���\�v���m�̏��ѐ^�ߎq���A�O�m�[��ȃI�y���w���~�I�ƃW�����G�b�g�x��� �s�W�����G�b�g�̃����c�i���͖��ɐ��������j�t���A�o���g���̊��쑾�Y�搶���A ���b�V�[�j��ȁs�_���c�@�t���A�����Đ_�J�搶�Ǝ��ŁA�I�y���w�֕P�x���s���t�̉́t�� ����I���܂��B �@�Ō�ɂ́A�����{��k�Е����̃e�[�}�\���O�ł���s�Ԃ͍炭�t��h���}�w��̏�̉_�x�� �e�[�}�\���O���A���������{�̉̂���ꂽ���h���[���A�s�A�m�A���y��A�̂̃A���T���u���� ���������������܂��B �@���̃R���T�[�g�̂��߂ɁA�l�X�ȕҐ��ŕҋȂ��ĉ�����̂́A��Ȃ̌���k���搶�B ����搶�̑f�G�ȃA�����W�ɂ������҉������I �@����̋Ȃ̃��C���A�b�v�������ɂȂ�A�������C�Â��ł��傤���H�@ �����A����̃R���T�[�g�̃e�[�}�́w���ȁx�B����̒ʂ�A�R�O���N�� �j�ՋC���Ȃɂ̂��Ă����肵�܂��B �@��ʂ̕��ɂ����ł���������悤�ɁA����搶�Ǝ����P�Ȃ��Ƃ� ���b�����A����グ�Ă����܂��I �@�W���R�O���i���j������ނ�z�[���ɂāA�P�W�F�R�O�J���ł��B �@�Ă̖�A���q�l�����l�̕��܂ŁA���ėǂ������ˁA�������y������ˁA �Ƃ����Ă���������������R���T�[�g�ɂ��Ă������Ǝv���Ă��܂��B �@�`�P�b�g�́A����ނ�A��؊y��A�\���C���������y�����Ŏ�舵���� ���܂��B����]�̕��ɂ͑������������܂��i10���O�܂łɗv�A���j�B �@�F�l�̂���������҂����Ă��܂��B�@